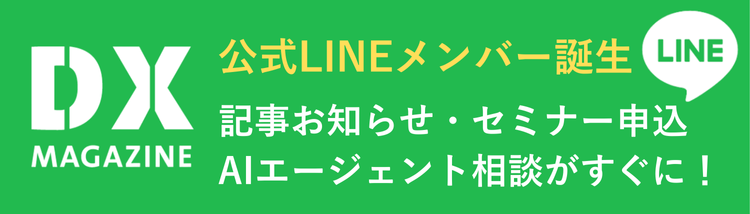多くの企業がDXに舵を切るものの、ゴールへと順調に進むケースは必ずしも多くありません。どんな課題に直面し、どのように乗り越えようとしているのか。ここでは飲食店を展開するスープストックトーキョー、ダイヤモンドダイニング、ニュートンの3社に、デジタル化に取り組む前の課題、具体的な解決策、今後のビジョンを聞きました。
コロナを機にモバイルオーダーなどを導入、アプリとEC連携で顧客向けサービスも強化
齋藤:当社は現在、駅ナカを中心に61店舗のスープ専門店を展開しています。ここ数年に限ると新型コロナウイルス感染症の影響で、利用形態に変化が出てきました。店舗ではなく、通販を利用する人が徐々に増えてきたのです。しかし当社では、店舗は店舗、通販は通販の利用者情報を別々に管理していました。主に店舗利用者が使用するスマートフォン向けアプリでは、利用者に適切な情報を案内できない状態でした。こうした状況を改善するのが急務でした。
――課題をデジタル化でどう解消した?
齋藤: 2019年にスクラッチで開発したスマートフォン向けアプリを2022年に刷新しました。SSO(シングルサインオン)を導入し、アプリ会員とオンラインショップ利用者のIDとパスワードを相互連携しました。アプリかオンラインショップいずれかの会員情報さえあれば、どちらのサービスも共通利用できるようになりました。顧客情報を一元化することで、店舗とオンラインショップが連動する企画や、利用状況に応じた案内を展開しやすくしたのです。
さらに、Uber Eatsをはじめとする主要な配達サービスの活用にも踏み切りました。店頭に並んで注文を待たずとも、事前に注文・決済できるモバイルオーダーも一部店舗で導入しました。
――今後の予定、目指すべき姿は?
齋藤:「Soup for all!」という価値観のもと、顧客一人ひとりに寄り添った施策を提供できるようにしたいです。例えば、パクチーが苦手というお客様がいるとします。これまでの利用履歴などのデータを使えば、利用者が「パクチーをトッピングしないで」と言わずとも、パクチーなしの商品をあらかじめ提供できるようになるはずです。店員が注文の度に「ガムシロップやミルクはいりますか?」と聞くのも、これまでの注文履歴さえ分かっていれば、毎回聞く必要はなくなるでしょう。いずれば、利用者が食品アレルギー情報を事前登録しさえすれば、利用者が注文時に食品アレルギーを含む商品なのかを調べる手間もなくせるのでは。そんな提案をできるアプリの開発やデータ活用を視野に入れています。
利用者の身近で些細な不満を解消し、声を上げることさえなかった要望を叶える手段となるデータ活用を模索します。そのために必要な社内の体制づくりやサービス拡充を進めていければと思います。
モバイルオーダーとダイナミックプライスを試験導入、デジタルの可能性をさらに模索
長瀬:新型コロナウイルス感染症がまん延する2020年以前から、人材不足や業務上のさまざまな不具合を解消しなければという課題が顕在化していました。その解決手段としてITの活用を模索するものの、「DX」と呼べるような大胆な施策を展開できずにいました。
さらにコロナを機に、飲食店に人が集まらない状況が続きました。こうした中でも来店してもらうには、どんな店舗を目指すべきか。さらには収益構造をどう変えるべきか。“店舗”を再定義する必要性にも迫られました。
――課題をデジタル化でどう解消した?
長瀬:当社は店舗スタッフの効率化を目的に、コロナ以前よりモバイルオーダーを試験導入しています。当時は珍しかったものの、今後はモバイルオーダーの時代が訪れるという仮説のもと、2021年に都内にオープンした「焼鳥IPPON」という店舗で効果を検証することにしたのです。来店者が自身のスマートフォンをメニュー代わりに注文できるようにしました。
モバイルオーダー導入によって店舗スタッフのオペレーションがどう変わるのかを事前にシミュレーションし、実際のオペレーションとの乖離を探りました。運用しながらオペレーションの課題を洗い出すことで、スタッフの負荷は徐々に軽減しました。来店者から「すみません」と声を掛けられることが減ったのも、負荷軽減の要因の1つですね。導入当初はスタッフの効率性などを目的に導入したモバイルオーダーですが、コロナによってその目的は大きく変わったと感じています。
スタッフの早期戦力化も見込めるようになりました。店舗のスタッフは一般的に、飲食店特有の接客スキルをきちんと習得しなければ現場には立てません。しかし、モバイルオーダーを導入したことで、そのハードルは下がりました。得手や不得手を理由に新人スタッフの活躍の場が制限されにくくなったのです。接客が未経験の新人でも、比較的早く現場に馴染めるようになったのはモバイルオーダーの導入効果と言えます。
なおモバイルオーダーの強みを活かし、当社では時間帯によって価格を変えるダイナミックプライシングも導入しました。メニュー価格を動的に変えられる、デジタルならではの施策です。予約状況や混雑状況などのデータをもとに、その時間帯に応じた最適な価格をモバイルオーダーのメニュー上に自動表示します。来店需要をある程度平準化できるほか、店舗スタッフの人員配置の効率化も見込めるようにしました。
――今後の予定、目指すべき姿は?
長瀬:モバイルオーダーの運用はまだトライアルの段階です。まずはデータを収集し、データに基づき店舗運営を効率化できればと考えます。さらに、「焼鳥IPPON」の運営ノウハウが他店に当てはまるのかも検証しなければなりません。当社はさまざまな業態の飲食店を展開していますが、それぞれの特性や立地などに応じ、デジタルをどう活用すべきかを模索していきます。もっとも、今回のトライアルによりデジタルの効果を感じつつあります。他飲食店を含む全社的な取り組みとしてデジタルの可能性をさらに広げられればと思います。
店舗の“健康状態”を把握する指標づくり、段階的なデータ活用で変革の土台を築く
北見:カラオケ店やレストランなどでは多くのデータが集まるものの、業態ごとにデータが点在していました。基幹システムにデータを集約し、財務や人事といった社内データと掛け合わせた売上分析には、データを都度ダウンロードする必要がありました。そのため、過去データの比較などは非常に時間のかかる作業でした。
“現場に神宿る”の言葉通り、日々起こることへの素早い対応を心掛けるものの、中には勇み足になってしまう案件もありました。カラオケ店の時間課金を管理するシステムが保有する大量データを活用した「営業状況の可視化」は誰もが望むものの、次のステップには進めずにいるのも問題でした。
――課題をデジタル化でどう解消した?
北見:店舗の現状を把握する指標づくりから始めました。店舗スタッフが接客に十分な時間を割いているか、接客以外の業務に忙殺されていないかなどを可視化し、店舗の“健康状態”を把握できるようにしました。店舗を管理・監督するスーパーバイザーが集まり、どんな指標を用いるべきかを議論し、30項目の指標を整理しました。例えば、電話の応答率。電話は忙しくても出るのが原則ですよね。しかし電話に出られない、つまり応答率が低い店舗は何かしらの問題があるのでは。こうした仮説のもと、新たな指標として設けました。スタッフの内定率や採用3カ月後のスタッフ定着率なども指標にしています。こうした指標を使い、売上低下や稼働率向上などの店舗向け施策立案のヒントを探れるようにしました。
――今後の予定、目指すべき姿は?
北見:当社のデジタル化の取り組みはまだ始まったばかりです。今も活用すべき多くのデータが埋もれたままです。現在は、データをシステム連携によって集約できる環境整備を進めています。システム改善によって個客の利便性をどこまで高められるのかを模索・検討しています。
当面は自社でデータ活用の土台づくりを進めます。その上で今後、「もっと楽に運用したい」「データ収集を自動化したい」「週次で集めるデータを日次で集めたい」などの声が上がれば、予算を投じて外部のSIerを活用していく考えです。
目指すのは「天気予報」のようなデータ活用です。誰もが一見するだけで起こすべきアクションを考えられる。そんな姿を描きます。データは集めようと思えば集められるし、ダッシュボード上に見やすく表示させることもできます。しかし大事なのは、そのデータを見て現場が動くかどうかです。これまで見えなかったデータが見えるようになったとしても、アクションにつなげられなければ意味はありません。店舗スタッフがデータの意味を容易に汲み取れるように伝えることが大切です。こうしたアクションに直結するデータ活用こそ、変革の第一歩だと考えます。