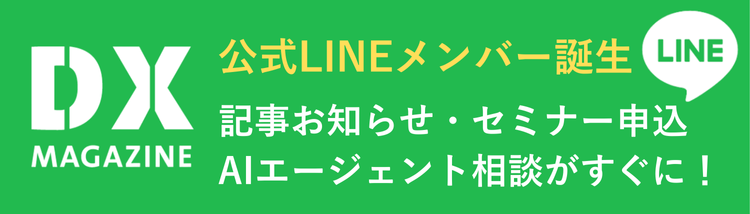DXマガジンは2023年8月23日、定例のDXセミナーを開催しました。今回のテーマは「従業員の共感を生み出すマネジメント~DXの第一歩は従業員の共感~」。ゲストのロイヤルホールディングス代表取締役会長の菊地唯夫氏が、同社の“共感”を生み出す秘訣について講演しました。
事業を成長させる源泉となる「従業員」。多くの企業が従業員教育に注力し、これからの事業を支える人材の輩出を目指しています。とはいえ、いくら育成しても従業員が成長しない。そう嘆く経営者は決して少なくありません。
では、事業の成長に直結する従業員を育成するには何に目を向けるべきか。その1つが「共感」です。自社のビジョンや事業に共感する従業員を育成し、全社で足並みを揃えて突き進む体制構築こそが不可欠です。さらには従業員の共感を生むマネジメントに取り組み、組織として取り組む環境づくりも必要です。
今回のセミナーでは、ロイヤルホールディングス代表取締役会長の菊地唯夫氏が登壇。従業員の共感を生むマネジメントについて解説しました。同社が“共感”を生み出すために取り組むこと、さらには“共感”を生み出すことが事業の成長にどう寄与したのかにも言及しました。
“増収増益”を目指すカギとなるのが「付加価値」の創出
44歳のときにロイヤルホールディングスの代表取締役社長に就任した菊地氏。就任当時、グループの業績は必ずしも健全ではなかったと振り返ります。「1997年から2010年の期間に限ると、3~4年周期で増収減益、減収増益を繰り返していた。既存店の売上が前年割する状況が続いたため、不採算店を閉店すると売上が下がる。新規出店すれば売上増を見込めるが、利益を見込みにくい。こうしたジレンマが続いていた」(菊地氏)といいます。そこで社長就任当初、菊地氏が目指したのは黒字化と、「増収減益・減収増益のサイクルから脱却し、増収増益を継続できる経営体制への転換」(菊地氏)でした。

具体的に取り組むのに先立ち、菊地氏は10年先を見据えた「経営ビジョン」を策定。事業ごとに優先すべき戦略を立案します。「当グループは、ロイヤルホストやてんやなどの外食事業に加え、機内食やホテルなどの事業も展開する。全事業共通の戦略を打ち出すのではなく、事業やブランドに応じて集中すべき戦略を打ち立てた」(菊地氏)といいます。例えばロイヤルホストなら「ブランドの再構築」、てんやなら「成長エンジンの育成」、機内食やホテル事業なら「収益基盤の拡大」といった具合に優先すべき戦略を打ち出します。もっとも、「事業ごとに取り組む内容は異なるが、グループとして取り組みを有機的に連携することに主眼を置いた」(菊地氏)といいます。「ロイヤルホストは当グループにとってブランドの発信源に位置付く。そのため、既存店を訪れるお客様の満足度向上がブランド再構築には欠かせない。こうした取り組みが他の事業の評価やブランド向上にも奏功する」(菊地氏)と指摘します。当時はロイヤルホスト1店舗につき約4000万円のコストをかけ、徹底した既存店の改修に踏み切ったといいます。
2009年から新規出店より既存店に投資する体制へ転換。その結果、2012年から増収増益の経営体制への転換を図れたといいます。
サービス産業に従事する立場として、セミナーでは生産性をどう高めるのかにも言及しました。「生産性を高める上で何より難しいのは、付加価値をどう見出すか。日本の場合、おもてなしという言葉がある通り、サービスに高い期待を寄せる。しかし一方、サービスの対価性は低い。つまり、どんなに十分なサービスを提供できたとしても、そのサービス自体が売上向上には直結しない」(菊地氏)と指摘。付加価値を創出する取り組みに注力すべきと訴えます。
付加価値を分解し、何が付加価値を生み出すのかも考察します。「ロイヤルホストの場合、多少高くても注文するメニューには付加価値がある。例えば食材に国産の農産物を使ったものが当てはまる。一方、サービスに目を向けると、マニュアルにとどまらない接客にも付加価値がある。『商品』と『サービス』の2つを軸に付加価値を創出することを模索しないといけない」(菊地氏)といいます。さらに、「これらに共通するのは、規模と相反するリスクを内在していることだ。規模が大きくなれば、国産の農産物を提供しにくくなる。マニュアルを超えた接客も難しくなる。つまり、規模を圧縮すれば、顧客が付加価値があると感じる商品、サービスを提供できるようになる」(菊地氏)と、付加価値の創出には規模を踏まえるべきと考察します。
例えばロイヤルホストでは当時、国産の車エビを使ったカレーを提供。しかし、国産の車エビを確保するのが難しく、1店舗につき4尾しか入荷できなかったといいます。「220店舗だった当時、1店舗につき4尾しか入荷できなかったが、もし新規出店を加速していたら、440店舗なら1店舗につき2尾しか入荷できない。これではお客様の満足度を得られない。付加価値創出にはつながらない。既存店舗強化に舵を切った取り組みが、ロイヤルホストの付加価値を認識してもらうことにつながった」(菊地氏)といいます。さらに営業時間も24時間営業を廃止し、より生産性の高い時間帯の営業に切り替えることで、付加価値を高められるようにしたといいます。
菊地氏は規模と付加価値の関係について、「規模拡大に進み続ければ、商品やサービスに付加価値をつけにくくなる。つまり、どのくらいの規模なら付加価値を最大化できるか。規模の“頂点”を探す取り組みが重要だ。営業時間や休店日などを勘案しながら、お客様が付加価値を感じ取れる商品やサービスを設計することが大切だ」(菊地氏)と分析します。もっとも「付加価値が最大化する頂点は市場によって変化する。人手不足が深刻になれば、規模をさらに縮小することも視野に入れなければならない」(菊地氏)といいます。しかし、規模を縮小し続けるだけでは成長曲線を描けません。「市場などに影響することなく、付加価値を最大化する頂点を意図的に維持する作る取り組みにも目を向けなければならない。このとき、こうそや取り組みを支えるのがテクノロジに他ならない」(菊地氏)といいます。付加価値を創出するには、単に規模に頼らず、テクノロジを活用することも必要だと訴えます。
そこで同社は2016年、当時の先端テクノロジを活用した実験店を開始。セルフオーダーやキャッシュレス、さらには調理を効率化する調理器具などを導入し、規模を縮小せずとも付加価値を生み出す体制づくりを模索します。「人にしか価値を生み出せない業務に集中できるようにした。その結果、接客や調理に費やす時間が55.9%から67.4%に増加した。テクノロジを活用することで一定の効果を見込めることが分かった」(菊地氏)といいます。
もっとも、「これまで人が担ってきた業務をロボットやAIに置き換えていこうということではない」(菊地氏)と強調します。「ロボットやAIで済む業務がある一方、人にしか価値を生み出せない業務がある。こうした価値を生む本質的な業務に集中できるようにすることがサービス産業には求められる。人による労働とテクノロジの関係は『or』ではない。人の業務をテクノロジがサポートする『with』の関係だ。笑顔や臨機応変な対応など、人によって生み出される付加価値は、テクノロジが業務をサポートすることで生まれやすくなる」(菊地氏)と指摘。店内の清潔感を維持したり、適切な時間に料理を提供したりするのにテクノロジを活用し、テクノロジでは得られない顧客満足度の獲得に人を割くべきだと訴えました。