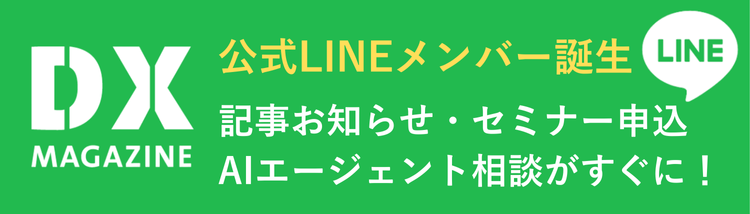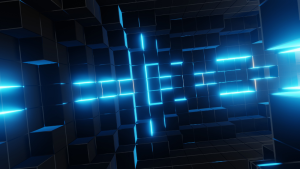DXでイノベーションや新規事業を創出。こんな構想を描く経営者は少なくなくありません。しかし、簡単に創出できないのも事実。企業がイノベーションや新規事業創出を苦手とする理由、要因には何があるのでしょうか。企業のイノベーションや新規事業の創出を支援するRelic 代表取締役CEOの北嶋貴朗氏に聞きました。
イノベーション創出に向けた再現性向上と成功確率引き上げを目指す
-日本ではイノベーションが起きにくいと言われている。
多くの企業はイノベーションの必要性を理解するものの、既存事業を改善し続けることでイノベーションから逃げてきた側面があることは否定できません。こんな経緯が、起きにくいと言われる背景にあると思います。自社が生き残るためにはイノベーションが不可欠と、本気で考えない企業がこれまでは多かったと感じます。
私の知る限りでも、新規事業やイノベーションのブームは過去に数回ありました。これまではブームに引きずられて取り組み出す企業が多かったと思います。しかしその取り組みは、会社の生き残りをかけるものでは必ずしもなかった。既存事業をどう存続させるかに注力し、既存事業の強化・拡充を優先するケースが大半でした。ブームはしょせん他人事で、危機感ありきで取り組む企業は稀だったのではないでしょうか。
-しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で状況は変わりつつある。
その通りです。コロナ禍でビジネスの前提条件が変わり、イノベーションを真剣に考えざるを得ないタイミングが想定していたよりも何倍も早く訪れました。新規事業やイノベーション創出を支援する当社への問い合わせも増えています。コロナという想定外の外的要因により、既存事業の改善だけではなく、イノベーション創出の優先度を高める企業が増えていると実感します。
-経営者がいよいよ危機感を持ち始めた?
新規事業はもちろんのこと、デジタルを前提に、既存事業をドラスティックに作り直そうと考える経営者が増えています。トップマネジメントで本気に取り組む動きが顕著ですね。
-それでもイノベーションを起こすのは簡単ではない。
もちろん、取り組む以上は絶対に成功させるという意思や覚悟を持ってプロジェクトを進めるべきです。一方、経営者やマネジメント側の人の心構えというと、このような不確実性の高い取り組みは、簡単に一発必中で起こせるものではないことを認識した上で、どうするべきかに向き合わなければなりません。企業はイノベーションを狙って一発で起こそうとするのではなく、イノベーションを阻害する要因を排除し、良質な挑戦が量産される状態を作ることで再現性を高めることを目指すべきです。こうした環境づくりがイノベーションを起こしやすくします。「狙えないなら、環境をコントロールする」。これしかないと思いますね。
そもそも、大半の企業はイノベーションや新規事業の不確実性や成功確率がどれくらいなのかを把握せずに取り組んでいるのではないでしょうか。さまざまな統計を見ると、新規事業や成功の定義にもよりますが、新規事業が成功する確率は3~30%程度。失敗する確率の方が当然高くなっています。短期的に成果がすぐに現れるものでもないので、中長期的に取り組みの質を高めることが大切です。また、自社のビジョンに基づき、イノベーションにどう取り組むのか、どんな方針を打ち出すのかといった戦略すら考えないまま取り組むケースも多いですね。
-戦略とは具体的に?
イノベーション創出に向けた再現性向上、成功確率引き上げの取り組みを実施すべきです。当社はこうした取り組みを「インキュベーション戦略」と呼んでいます。
例えば新規事業を作る場合、中核となる事業領域の周辺、近い領域で、ローリスク・ローリターンで事業化するケースがあれば、既存の顧客やビジネスモデルも異なるハイリスク・ハイリターンな革新領域を攻めるケースもある。どんな新規事業を作るのかにより、どれくらい投資するか、リスクに応じてどれくらいの投資配分にするのかなどを考えるべきです。短期的に手堅く利益を出すタイプの事業の立ち上げ方と、全滅するかもしれないが一発当たったら大きくスケールする事業の立ち上げ方は異なることを理解すべきです。このような性質や特徴を理解した上で投資の方針を決めたり、ポートフォリオを組んだりすることが必要になります。
事業領域によって事業開発のアプローチも変わります。例えば、革新領域を攻めるケースで、中長期で赤字を出し続ける投資をしなければならない新規事業の場合、基本的にはトップダウンで進めなければなりません。であるにも関わらずボトムアップで進めようとして、大きな裁量がない現場にロジカルな成功の理由を細部まで求めていては推進もままなりませんし、事業は高い確率で失敗しかねない。
一方で、隣接領域や不確実性が比較的低い周辺領域の新規事業に取り組む場合、現在の既存顧客の声を一番聞いている現場担当者が発案したボトムアップで事業を開発して進めた方が成功しやすいケースもあります。トップダウンかボトムアップか、オープンイノベーションかクローズイノベーションかなどの大分類だけでなく、その中でもさまざまな事業開発アプローチがあることを踏まえておくべきです。
-戦略を十分練らずに突き進む経営者は多い。
肌感としては少なくないと言えますし、そういった場合は手法論が先行しているケースが多いように感じます。例えばなぜ今、何のために、どんな事業に、誰が取り組むべきなのか、といった上流の検討が抜け落ち、個別の事業開発のための一手段である「リーンスタートアップ」や「オープンイノベーション」などの手法や理論が流行れば、とりあえず自社にも取り入れるといった具合です。しかし手法論は万能ではない。当てはまるケースがあればそうならないケースもある。すべての新規事業プロジェクトにリーンスタートアップを当てはめるのではなく、従来通りに企画をきちんと練り、ある程度大規模な投資をした方がよいケースもありますし、どのアプローチが適切かはその企業の文化や保有するアセットなどによってもまったく異なります。
インキュベーション戦略の不在、戦略を正しく実行して良質な挑戦を量産する組織がない、不確実性や自社・事業の性質に応じた適切な事業開発プロセスやアプローチを踏めてない。大別するとこの3つが、イノベーションが起こりにくい主な要因だと思います。
-企業がこれからイノベーションに取り組むためには何が必要?
イノベーション創出に本気で取り組むなら、経営者が中長期の時間軸で強いコミットメントのもとでリーダーシップを発揮して進めるしかないと思います。イノベーションや新規事業に正解なんてありません。だからこそ経営者の強い思いや意思が必要です。自社がどこに向かうのか。そのためには新規事業が必要で、どう作り上げるのかという取り組みは、経営者が主導しなければ成し得ません。
経営者が短期間で変わってしまうケースも好ましくありません。これではイノベーション創出の取り組みが道半ばで終わってしまいかねない。例外を除き、基本的には長期政権で取り組まなければいけないことも理解されるべきだと思います。一般的に、創業社長やオーナー経営者の方がイノベーションは成功するケースが多いと言われているのは、上記のような取り組みを実現しやすい構造になっているからだと考えます。
これはDXも同じです。何のためのDXなのか、デジタル技術を駆使して企業や事業にどのような変革をもたらすのか、エンジニアを含むIT人材・DX人材が躍動する組織体制を構築するのは一朝一夕では不可能です。中長期的な戦略や方針に基づいて強いコミットメントやリーダーシップのもとでやり切る、こういった思いが経営者には求められるでしょう。
長期的にデジタルテクノロジーの利活用を内製できる組織構築を目指す
-イノベーションを主導する人材が社内にいないという課題もある。
イノベーションや新規事業プロジェクトに、社内の優秀な人材をアサインするケースは多いですが、こうした人は既存事業において優秀とされるケースが大半です。新規事業に求められる能力は、志向性や資質、行動特性など、既存事業のそれとは大きく異なり、場合によってはこうした人材をアサインすることがプロジェクトを迷走させる要因になります。当社が独自に実施した調査では、新規事業のリーダーに適したイノベーター人材は企業内に約3~5%程度しか存在しないという結果が出ています。また、経験やスキルを積み上げることで要件を満たせそうなイノベーター候補人材まで含めても、約10%前後にとどまります。
この続きを読むにはログインが必要です
こうした人材を採用・育成したり、抜擢・活躍したりできるか、さらにはリーダーが伸び伸びと活躍できる組織体制や制度、企業文化があるかも大切です。多くの企業が、既存事業を前提とした組織や制度を新規事業にも当てはめています。新規事業では、新しいことにチャレンジしたり、売上に直結したりしない取り組みが増えます。こうした取り組みを制約する組織や企業文化は好ましくありません。
-イノベーションにはITが欠かせない。デジタルやITの理解不足も課題では?
日本は長い間「ハードウエア」で勝負してきた時代があり、その時代には世界を席巻しました。当時はハードウエアの品質や生産力に競争力の源泉があったのです。しかし現在、ビジネスの中心はソフトウェアに置き換わりました。IT革命の波に乗り遅れた多くの日本企業には、ソフトウエアビジネスにきちんと取り組んできた人材が社内にほとんど存在していないという問題が多発しています。情報システム部門があっても、部門の役割はITの社内運用や保守が中心であることが多く、ソフトウエアビジネス、つまりデジタル技術によって大きく前提やルールが変わったデジタルの世界でのビジネスの作り方、企画や事業開発ができる人材が圧倒的に不足していると感じます。
例えばデジタル時代のビジネスでは、プラットフォームビジネスやフリーミアムなどのように、それ以前では成立し得なかった新しい戦略やビジネスモデルが登場しています。製造コストやルールなどが従来と大きく変わっているのです。しかし、こうした新たなビジネスに触れたことがない経営者や従業員が大半を占める企業が多数存在します。このような状態でDXやデジタルを前提にした新規事業に取り組んでも成功するはずがありません。
そこで、成功に向けて本腰を入れている企業は、エンジニアを筆頭に、IT人材やDX人材の採用や育成に本気で取り組んでいます。中には、そういった人材に乏しかった企業がエンジニアの割合を全社員の5割以上にするという高い目標を立てて、積極的に採用や育成に注力しているケースもあります。実際、こうした会社は成果が出始めていますね。
-エンジニアが1人もいない会社が採用するのは難しい。
Webエンジニアやアプリエンジニアなどが1人もいない会社がエンジニアを採用したとしても、誰もマネジメントできないし、育成できません。まずはデジタルビジネスの事業を開発できる人、エンジニアをマネジメント、育成できる人材から採用すべきです。「CTO」の役割を担う人材がいるのは大きな強みです。こうした人を採用してから、エンジニア組織を少しずつ育てていくのが望ましいでしょう。
-システム開発を外注する体制ではなく、社内にエンジニアを抱えるべき?
現在、イノベーションを起こしている企業の大半が「テックカンパニー」と呼ばれる企業です。そこでは多くの優秀なエンジニアを抱え、また多くのIT人材・DX人材が自社開発するプロダクトに価値を生み出す体制を構築しています。
これまでは社内にシステムを開発する体制がなく、外注するケースが少なくなかった。新規事業を企画したとしても、これまで馴染みのある外注先に依頼してしまいがちだったりします。しかし、企業がこれまで外注してきたシステムの特性を考えると、既存の事業や業務の効率化やコスト削減を目的としたものではないでしょうか。これは単純に業務プロセスの一部をデジタル化しているに過ぎません。そしてこのように要件が明確なシステムを開発することに慣れた外注先に、デジタル技術を活用することで自社のビジネスモデルを変革し、新たな事業価値や顧客体験を生み出す取り組みを任せるのは必ずしも適切ではありません。
-システム開発を依頼する企業側のITリテラシーの欠如も問題だと思う。
その通りです。多くの企業が適切なベンダーを選定できないし、できたとしてもコントロールできていないことがほとんどです。外注するなら、社内の人が責任をもってマネジメントすることが前提です。こうした人材が社内にいなければ、適切なデジタルプロダクトなど作れるわけがありません。
ベンダー選びひとつ取っても、これまでの大手SIerやITゼネコンを前提とした発注構造からの脱却なくして変革は望めません。大切なのは決められた仕様書通りに「システム」を作れるかどうかではなく、「価値あるプロダクトやサービス」を作れるかどうかです。故に、エンドユーザーを想定したプロダクトやサービス開発の経験を積んだエンジニアの有無は極めて重要です。特に不確実性の高い新規事業ではできるだけコストをかけず、かつスピーディな開発を進めていく姿勢が欠かせない。こうした点も踏まえ、開発をコントロールしていかなければなりませんね。
-これからのシステム開発は外注から内製化へと進む?
短期的には外注しても構いませんし、せざるを得ないこともあるでしょう。また、必ずしもゼロから開発する必要はなく、SaaSやASP、ノーコードツールやローコードツールなどを駆使することで、エンジニアがいなくても十分に取り組めるケースもあります。しかし最終的には自社にとって真に重要な変革やプロジェクトをすべて既存のツールやサービスなどで賄うことは、現段階では難しい可能性が高い。そのため、いずれにしても内製化できる体制づくりを目指すべきだと思います。経営者は早急にこうした判断を下すべきです。また、外注するにしても昔から付き合いのある特定の企業への依存体制は健全とはいえません。運営体制にもメスを入れ、段階的に内製化に進むことが大切です。
イノベーション創出から事業化までの支援策を各種用意
-Relicは企業のイノベーション創出を支援している。具体的な支援策は?
当社は3つの事業を展開しています。1つめは「インキュベーションテック」。新規事業開発やイノベーション創出を実現するための仕組みや技術を企業に導入・実装するためのプラットフォームやプロダクト・サービスを提供しています。2つめは「事業プロデュース」で、企業ごとの目的や課題に合わせてオーダーメイドで支援するトータルソリューション新規事業開発や社内ベンチャー制度/新規事業プログラム、オープンイノベーション/アクセラレーションなどの戦略立案から実行、プロダクトやサービスの開発からマーケティングや営業の泥臭い実行も含めた事業成長までを一気通貫で支援します。そして3つめが「オープンイノベーション」。当社が出資やリソース、アセットの提供を行い、双方がリスクをとる事業パートナーとして共同事業開発やJVの立ち上げなどに取り組みます。企業が描くビジョン、現状、課題などに応じて適切な支援策を用意します。
-インキュベーションテック事業で提供される具体的なプラットフォームやプロダクト・サービスとは?
汎用的なさまざまなプロダクトを提供しています。例えば「Throttle」は、社内のアイデアやプロジェクト、イノベーター人材を一括管理するためのSaaS。イノベーションマネジメントという概念を企業に実装し、実現するために使います。アイデアを創出・共有するナレッジマネジメントの要素を備えつつ、ユニークなアイデアを提案する優秀な人材を育成・評価するタレントマネジメントの要素も包含します。業種を問わず、新規事業を開発したい企業を中心に、導入企業は1500社を超えます。そのほか、事業化に向けたテストマーケティングやプロモーション、資金調達などの用途を想定するクラウドファンディング構築SaaS「ENjiNE」や、事業が順調に進み出したときの顧客管理やMAの実施を支援するCRM「Booster」なども用意します。
もちろんこうしたプロダクトを活用するだけでイノベーションを創出できるわけではありません。企業規模や資本力、保有するアセット、狙う市場などを踏まえ、当社は事業化とその後の成長や成功を実現するまでのアプローチを包括的に支援します。
-「Throttle」を使わずとも、ナレッジマネジメントやタレントマネジメントツールを使えば新規事業の開発をサポートできる?
「Throttle」の強みは、企業全体の新規事業創出プロジェクトや制度の運用を一括で管理するだけでなく、ナレッジマネジメントやタレントマネジメントの機能を統合したり、データベースを備えたりしている点です。当社はアスタミューゼ社と業務提携しており、必要であればアスタミューゼ社の保有する世界最大級のイノベーションDBと連携できます。約2億件にもなる世界中のアイデアや特許、知財情報などを確認でき、創出したアイデアと類似するもの、競合するものを調べられるなど、さまざまな利活用の可能性があります。
-オープンイノベーション事業でRelicが出資することによるクライアントのメリットは?
資金だけでなく、実際に多数の新規事業開発や事業のグロースに携わってきた経験豊富なメンバーや、事業成長に必要なファンクションを網羅しており、それらを提供できるのがメリットかと思います。新規事業開発にはさまざまなリスクが伴いますが、そのリスクをRelicが代わりに引き受けるのもメリットです。特に大企業の場合、リスクを避けることや既存のルールや制約が優先される余り、スピーディに事業開発を行えないことが多い。クライアントの大企業が運営主体となって新規事業に取り組めば、事業的、財務的、法務的なリスクだけでなく、既存の自社ブランドを毀損させてしまうリスクやレピュテーションリスクなども考えられます。そこで当社がクライアントに代わり、事業化まで、もしくは事業を成長させるまでのフェーズを運営主体となって進めます。その後、本事業化のタイミングに合わせて主導する組織を当社からクライアントに引き渡すなどの柔軟なスキームを実現すれば、クライアントはスピーディに事業化を果たせるし、新規事業開発のリスクも自社で抱えずに済みます。実際に当社がこのようなスキームで大手メーカーや大手通信会社、大手インフラ企業などの新規事業を成長させるまでを支援した実績もあります。