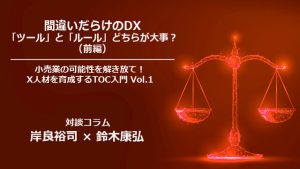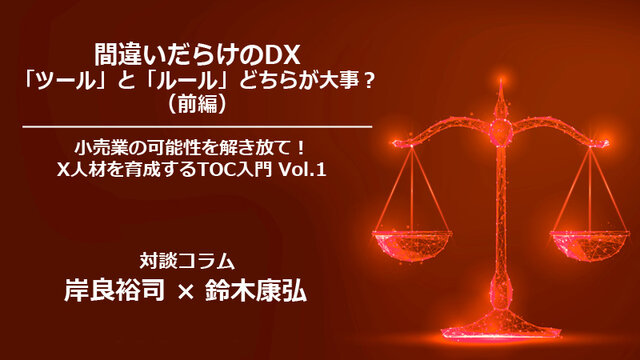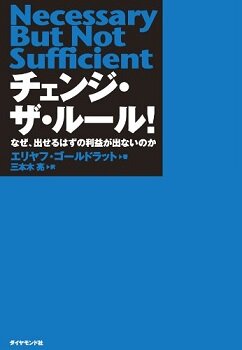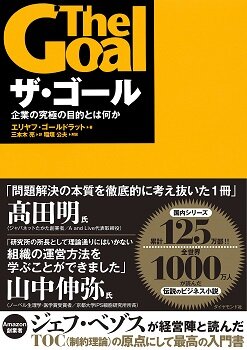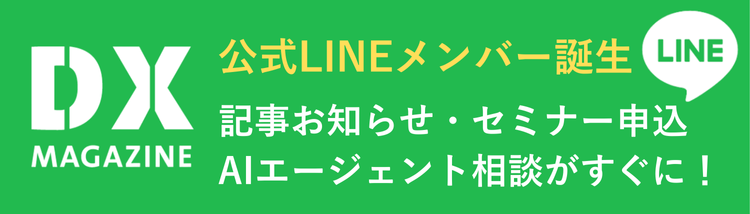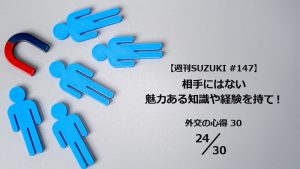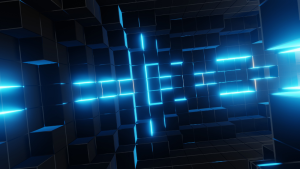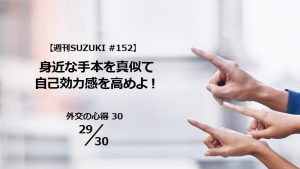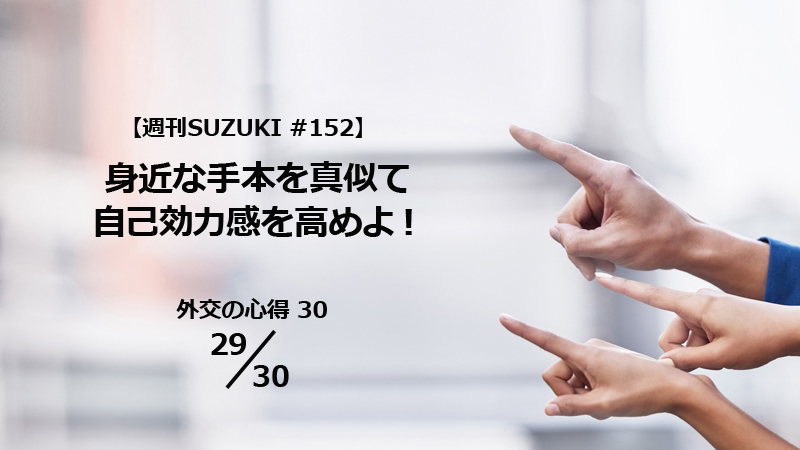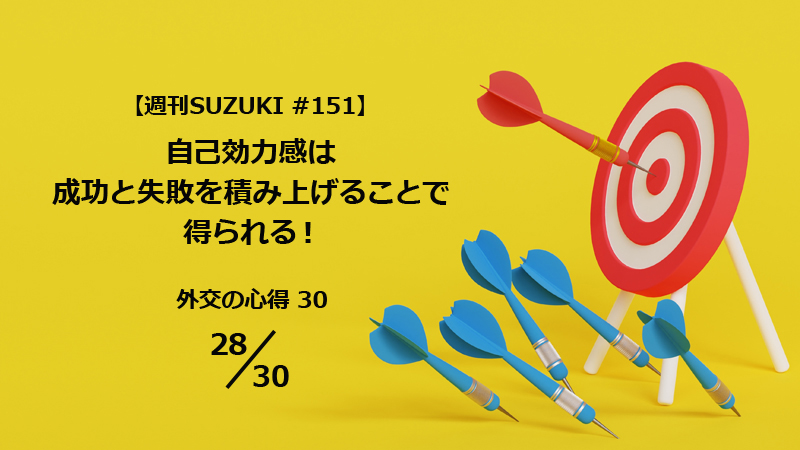DXを進めているのに自社が変わらない…。なぜこうした企業が多いのか。理由の1つが「DX」という言葉の理解不足に他なりません。自社を新たなステージへと導くためには「DX」をどう捉えるべきか。日本の小売業のDXに精通するデジタルシフトウェーブ 代表取締役社長の鈴木康弘氏(元セブン&アイ・ホールディングス CIO)と、全体最適のマネジメント理論TOC(Theory Of Constraints)(*)を駆使し、グローバルにDXの最前線で活躍するゴールドラット・ジャパンCEOの岸良裕司氏がDXの本質を議論します。
DXの「X」を見逃すな
岸良:「DX」という言葉がここ数年で一気に注目されるようになりました。しかし私は「またか…」って感じましたね。IT業界ではこれまで、AIやRPA、IoTなどの用語が次々登場し、DXもこれらに続く新たなバズワードなのではと思ったからです。私はこうしたバズワードに踊らされ、導入に踏み切った企業をたくさん見てきましたが、それらを活用して「成果が出ました!」なんて話、聞いたことがありません。
鈴木:IT業界では新たなバズワードが現れては消えの繰り返しですよね。新たなシステムを売りたいと考えるIT企業がもっともらしいキーワードを作り、ユーザー企業を煽っているだけのように感じます。
岸良:こうしたキーワードに踊らされるユーザー企業にも問題があるのではないでしょうか。しかし、今回の「DX」はこれまでのAIやRPA、IoTなどの用語と決定的に違う点があります。それは「X(変革)」の意味を含んでいることです。AIやRPA、IoTなどのこれまでの用語は「D(デジタル)」、つまり手段を表すだけでしたが、「DX」は「デジタルで変革する」という目的を含んでいます。
鈴木:手段であるデジタルばかり重視せず、自社をデジタルでどう変革するのかを考えることこそ「DX」の本質になるわけですね。
岸良:「DX」の提唱者であるエリック・ストルターマン氏は、DXについて「人々の暮らしをデジタル技術で革新する。それがDXの原点」と述べています。一方で日本企業のDXの取り組みを見ると、「デジタル化」に終始しています。同氏は「デジタル化=DX」とは言っていません。「D(デジタル)」と「X(変革)」、この2つの言葉の意味と関係を正しく理解することが何より大切です。以前、ある企業の「DX人材教育のプログラム」を見せてもらったのですが、その内容のほぼすべてがD(デジタル)教育で、X(変革)の教育なんて入っていませんでした。これには言葉を失いましたね。
鈴木:興味深い調査結果があります。あるIT企業が日本の大企業にDXの取り組み状況を聞いたものですが、DXに取り組み中と答えた割合は半数超えの59%を占めていたのに、「DXとデジタル化の違いを説明できない」と答えた割合が73%を占めたのです。DXが何かを分からないまま取り組んでいることを物語っていますよね。
岸良:この結果には愕然としますね。だから日本は諸外国から「DX後進国」なんて言われてしまうのではないでしょうか。DXとデジタル化の違い、それは「X」に他なりません。例えば、紙の書類をデジタル化しても、X(変革)しなければDXではないのです。デジタル化して自社の事業や業務をどう変革するか。この論点に向き合うことがDXでは不可欠です。そもそもデジタルは手段で目的ではないですから
鈴木:多くの経営者と話をする中で、DXをデジタル化と勘違いする人は少なくないですね。その結果、これまでの既存の枠組み内の取り組みにとどまり、変革までたどり着けないケースが多いと感じます。
岸良:ただITシステムを導入したりデジタル化したりするだけでは不十分です。このとき考えなければならないのは「ルール」です。ITシステムを使って業務の進め方や収益構造が変わるなら、その変化に追随するルールを策定しなければ意味がありません。社員の働き方がITで変わったのに、10年以上前のルールを順守し続けているようでは「X(変革)」なんてありえないですよね。
鈴木:私が以前、ソフトバンクに在籍していたとき、新たな申請システムが導入されました。代表の孫正義氏はこのとき、稟議の申請を24時間以内に処理する「ルール」を打ち出しました。上長が部下から申請された稟議を24時間以内に処理しないと自動承認されるというものでした。その結果、申請から承認までの時間が飛躍的に短縮しましたね。デジタル化によって日々の業務がどう変わるのか。それを見据えて「ルール」を策定した最たる例ですね。
岸良:デジタル変革のバイブルとも言われている「チェンジ・ザ・ルール」という本の中で、著者エリヤフ・ゴールドラット博士は「ルール」に目を向けるべきだと訴えています。
IT投資によるテクノロジー装備だけでは、利益向上にはつながらない。なぜなら、何もルールが変わっていないからだ
この本の序文では、ゴールドラット博士が次のようにも述べています。
ここ数年、コンピュータシステムにはどの企業、組織も多大な投資をしてきました。中には数千万ドル、数億ドルという莫大な投資をしてきたところも少なくなりません。しかしこうした多額の投資をしてきたにもかかわらず、コンピュータシステムを導入して利益を飛躍的に伸ばした企業を、少なくとも私は一つとして知りません。
さらに、新たなITやテクノロジーを活用するなら、次の質問に向き合うべきとも主張しています。
1.テクノロジーの真のパワーとは何か?
2.テクノロジーを用いると、どのような限界が取り除かれるのか?
3.これまでの限界に対応していた古いルールとは何か?
4.どのような新しいルールを用いればいいのか?
5.ルールの変化に併せて、システムにどのような変化が求められるか?
6.いかに変化を起こすか?
1.テクノロジーの真のパワーとは何か?
2.テクノロジーを用いると、どのような限界が取り除かれるのか?
3.これまでの限界に対応していた古いルールとは何か?
4.どのような新しいルールを用いればいいのか?
5.ルールの変化に併せて、システムにどのような変化が求められるか?
6.いかに変化を起こすか?
デジタルを活用するなら同時にルールにも踏み込まなければなりません。この取り組みが自社のX(変革)を促す大きな一歩となります。DXを加速させるならツール導入だけで終わらず、ツールの効果を最大化するルール策定も進めなければ意味はありません。
鈴木:2000年ごろから欧米を中心にERPパッケージの導入が進みました。欧米企業はこのとき、ERPパッケージに合わせて自社の業務を見直しました。つまり自社のこれまでの「ルール」を見直し、「ツール」の導入効果を高められるようにしたのです。しかし日本企業の場合、自社のルールに合わせてERPパッケージをカスタマイズするケースが少なくありません。昔のルールが今後も通用すると思いますか。DXを進めるなら、今こそ既存のルールにメスを入れるべきです。「これまではこうだった」という無意味な慣習を疑うことから始めるべきです。
(*)TOC(Theory Of Constraints)
イスラエルの物理学者エリヤフ・ゴールドラット博士によって開発された全体最適のマネジメント理論。この理論が発表された「ザ・ゴール」は、経営危機の逆境から飛躍の道を切り拓く小説仕立てのストーリーで構成。全体最適のマネジメントを分かりやすく学べることもあり、世界で一千万人が読んだベストセラーとなっている。アマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏やジャパネットたかた創業者 髙田明氏なども愛読。あらゆる産業界で名経営者を輩出し、全世界の著名ビジネススクールの必読書となっている。
via promo.diamond.jp
岸良裕司氏 ゴールドラット・ジャパン CEO
1959年生まれ。ゴールドラットジャパンCEO。全体最適のマネジメント理論TOC(Theory of Constraints:制約理論)をあらゆる産業界、行政改革で実践。活動成果の1つとして発表された「三方良しの公共事業改革」はゴールドラット博士の絶賛を浴び、2007年4月に国策として正式に採用された。成果の数々は国際的に高い評価を得て、活動の舞台を日本のみならず世界中に広げている。2008年4月、ゴールドラット博士に請われてゴールドラットコンサルティング(現ゴールドラット)ディレクターに就任し、日本代表となる。
鈴木康弘氏 デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長、一般社団法人日本オムニチャネル協会 会長
1987年富士通に入社。SEとしてシステム開発・顧客サポートに従事。1996年ソフトバンクに移り、営業、新規事業企画に携わる。 1999年ネット書籍販売会社、イー・ショッピング・ブックス(現セブンネットショッピング)を設立し、代表取締役社長就任。 2006年セブン&アイHLDGS.グループ傘下に入る。2014年セブン&アイHLDGS.執行役員CIO就任。 グループオムニチャネル戦略のリーダーを務める。2015年同社取締役執行役員CIO就任。 2016年同社を退社し、2017年デジタルシフトウェーブを設立。同社代表取締役社長に就任。 デジタルシフトを目指す企業の支援を実施している。SBIホールディングス社外役員、日本オムニチャネル協会会長、学校法人電子学園 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授を兼任。
DXマガジン編集部編集後記
ITツールが無事に稼働した時点で「IT導入プロジェクトは終了」と考える日本企業は少なくありません。しかし、本当の終了はITツールの運用が定着し、数カ月先、数年先に効果をきちんと生み出し、投資以上の利益が得られたときです。そのためにはITツールの定着を支援し、効果を最大化するためのルールづくりこそ重要です。ITツールを導入すると業務はどう変わるのかを考え、IT運用と並行してルールも策定すべきです。 ツール導入よりルールの見直しが大事…。これまで多くのIT導入プロジェクトを見てきた岸良氏と鈴木氏だからこそ気づく視点です。次回の対談では日本企業の何を“ダメ出し”するのか。楽しみです。