最近の企業のプレスリリースを見ると、パートナーシップや業務提携、包括的連携などといった言葉をよく目にします。ここ数年の動きとして、企業や団体、自治体などが手を組み、ともに新たな事業を模索するケースが増えつつあります。連携によって自社の弱みを補完しようと考える企業は少なくないようです。
例えばサプライチェーンの場合、開発や製造、流通、販売、サポートなどといった業界の企業が集まらなければ構築できません。製造業やメーカー、小売業、流通業などが手を組み、効率的かつ収益の見込めるサプライチェーンを構築しようとする取り組みは、共創なくして成し得ません。
特にここ数年、1つの業界に1つの業態で参入するといった従来のビジネスモデルを展開しにくくなっています。これからは業界や業態の壁を超えた共創、さらには企業同士の融合が事業の創出や成長に欠かせなくなると考えるべきです。
一方、企業に目を向けると、組織間にも「壁」があります。多くの企業が縦割りの組織体制で、他部署との連携が希薄です。オフィスで隣に並ぶ他部署の人がどんな仕事をしているのかが分からない、なんて話は珍しくありません。しかし今後、こうした組織の壁を取り払わなければ事業を成長させらないでしょう。新規事業の成長も見込めません。これまでの組織構造を見直し、他部署など連携しやすくする組織構造への移行がより求められるようになるはずです。
とは言うものの、こうした壁を取り払う仕組みはすでに整いつつあります。それがITによるインフラです。企業への導入が当たり前となったITを使えば、情報連携や共有は容易です。リアルタイムな情報共有さえ可能です。今後は自社の文化や風土を定着、共有するといったソフト面の整備を進めることに目を向けるべきです。ITを使ってコミュニケーションしやすい環境を整備したとしても、どんな思いで自社を成長させるのか、何のために他部署と連携するのかといった姿勢や考え方を部署間で同じにしない限り、組織の壁を超えた取り組みは見掛け倒しに終わります。
変革するという強い目的意識も共有すべきです。DXに取り組みたいという経営者と話をしていると、多くの経営者が何のためにDXを推進したいのかを答えられません。目的なしに、ただDXに取り組みたいと言うのです。これではDXの取り組みは必ず失敗します。DXで大事なのは、デジタル化を意味する「D」より、変革を起こす「X」です。つまり、「X」を具体的にイメージする企業こそ、DXによる成果を上げられるのです。こうした企業の多くが、社内の組織はもとより、業界の壁を超えた取り組みを進めています。さらに言えば、組織同士、企業同士で共通の目的を設定しています。明確な目的の設定と共有は、組織や業界の壁を取り払う上で極めて重要です。
では壁を取り払うのに必要な人材とは、どんな人を指すのでしょうか。1つは、自社に閉じこもらず、他社や他の業界関係者と多くの意見を交わせる人です。広い意見や考え方を学び、吸収し、自社の課題解決や事業創出に応用できる人材が求められるようになるでしょう。
さまざまなスキルを持つ「マルチスキル」であるかどうかも大切です。例えば、エンジニア出身の営業担当者、営業経験のある製品開発者、プログラミングできる経営者などといった具合です。複数職種のノウハウを持つ人材は、業界の壁を取り払う上で貴重な戦力となるはずです。
こうした人材に共通するのは、相手の立場で考えられるということです。他業界ではどんなことを危惧しているのか、他部署の担当者はどう考えているのかといったように、相手の痛みや苦労を理解し思いやることが、壁を取り除きやすくします。相手と同じ境遇を実際に経験しているかどうかは問いません。経験を積まずとも、相手を理解する姿勢を示しさえすれば、相手との壁をなくせます。理解しない限り、壁はいつまでも残り続け、組織や企業同士の融合は進まないでしょう。
なお、ここで言う相手とは、自社の顧客にも当てはまります。例えば小売業の場合、自店舗を利用する来店者、もしくは自社ECサイトを利用する訪問者の消費行動を分析しがちです。こうした取り組みはもちろん間違えではありません。しかしその顧客は、飲食店も訪れるし、銀行に足を運んで行員に相談しているかもしれません。顧客を理解するには、自社の店舗やECサイトといった限られた接点の行動を把握するだけでは不十分です。顧客が自社との接点以外でどう行動し、何を求め、何に不満を感じているのか。他の業界も含めて行動を把握しない限り、顧客の理解を深められません。そしてそのためには、他の業界や業態との壁を超えた共創こそが不可欠です。
少々前なら「共創なんて難しい」。そう思う経営者が少なくなかったでしょう。しかし今は、当たり前と受け止めるべきです。共創することでどんな新規事業を見込めるのか、既存事業をどう変えられるのか。こうしたアイデアを膨らませ、他業界や他業態の企業とともに具現化してください。ITが整備された今、足りないのは「人」の行動力だけです。これからは経営者が主導し、全社の取り組みとして業界の壁を取り壊すことが求められるのです。





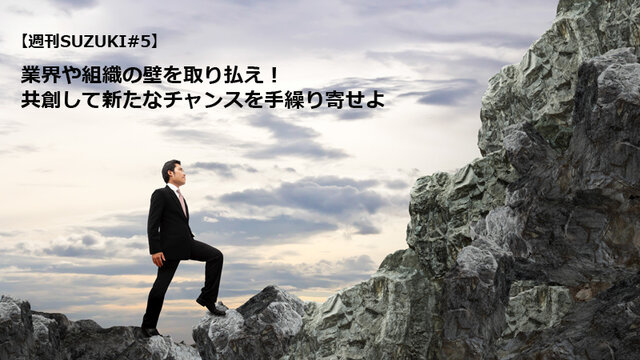



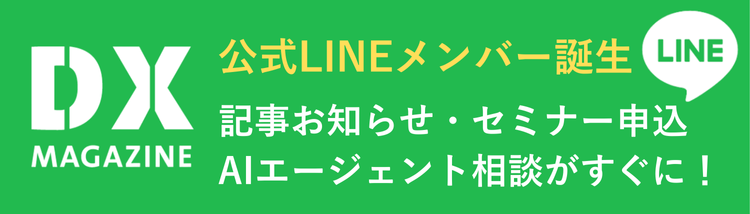







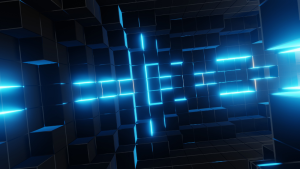

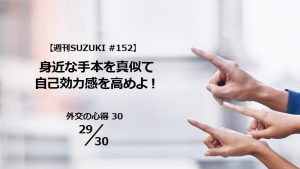
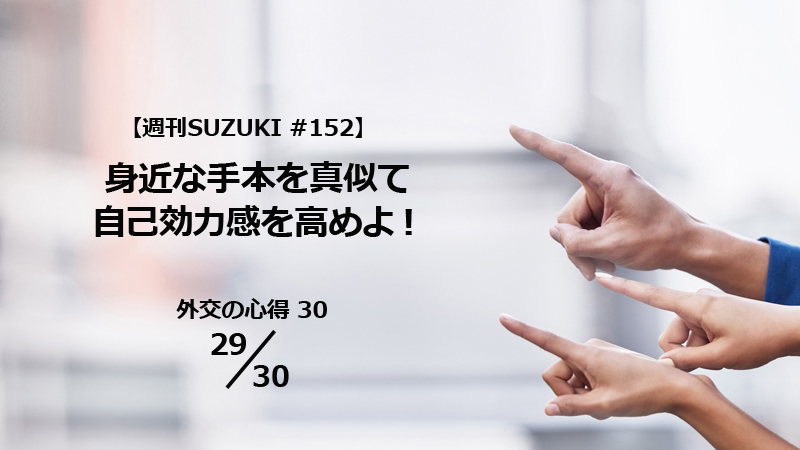
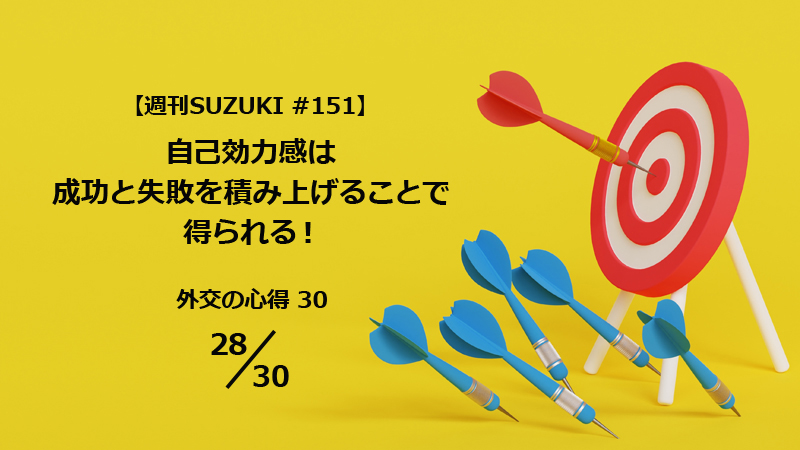




株式会社デジタルシフトウェーブ
代表取締役社長
1987年富士通に入社。SEとしてシステム開発・顧客サポートに従事。96年ソフトバンクに移り、営業、新規事業企画に携わる。 99年ネット書籍販売会社、イー・ショッピング・ブックス(現セブンネットショッピング)を設立し、代表取締役社長就任。 2006年セブン&アイHLDGS.グループ傘下に入る。14年セブン&アイHLDGS.執行役員CIO就任。 グループオムニチャネル戦略のリーダーを務める。15年同社取締役執行役員CIO就任。 16年同社を退社し、17年デジタルシフトウェーブを設立。同社代表取締役社長に就任。 デジタルシフトを目指す企業の支援を実施している。SBIホールディングス社外役員、日本オムニチャネル協会 会長、学校法人電子学園 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授を兼任