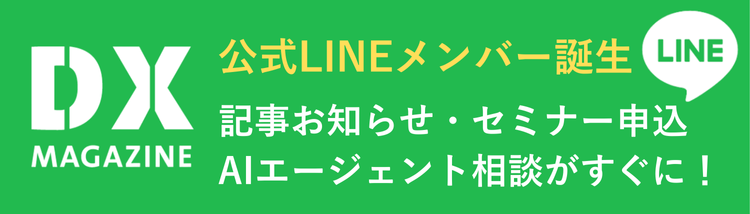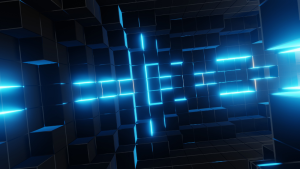読売ジャイアンツの本拠地である東京ドームをはじめ、遊園地やホテル、複合商業施設などが集まる東京ドームシティ。都内随一のエンターテインメント施設として、年間4000万人(2019年度調査)の来場者を誇ります。ファンを迎え入れ、喜ばすためにどんな施策に打って出るのか。デジタルを事業にどう取り入れるのか。獣神サンダー・ライガーのマスクをかぶって取材に応じた株式会社東京ドーム 代表取締役会長 CEO 北原義一氏に、ファンを大切にする思いを聞きました。(聞き手:株式会社デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長 鈴木康弘氏)
鈴木:今日は獣神サンダー・ライガーさんに…。いえいえ、東京ドーム 代表取締役会長 CEOの北原さんにお話しをお聞きします。
北原:獣神サンダー・ライガーとお呼びください(笑)。
鈴木:(笑)。今日はどうしてマスクをかぶって来られたのですか?
北原:実はプロレスやボクシングなどの格闘技が大好きで、今回の取材を通してプロレスの魅力を少しでも伝えられればと思い、こんな格好で登場してしまいました。
鈴木:東京ドームシティといえば、格闘技の聖地「後楽園ホール」がありますものね。今日はそんなたくさんの魅力にあふれる東京ドームの目指す姿に迫りたいと思います。東京ドームは2021年に三井不動産グループの一員となり、北原さんは同年東京ドームの経営に参画、翌2022年に現職につかれることになりました。東京ドームの事業を携わることになったときの印象を教えてください。
北原:誤解を恐れずに言えば、東京ドームは予想以上のアナログカンパニーでしたね。多くの企業がITやデジタル、DXに取り組む中、それらの取り組みがあまり進んでいないことに当時は驚きました。ただし、それが必ずしも悪いとは思いません。アナログにはアナログの良さがあります。その良さを消し去らずに、事業に活かせればと考えました。例えるなら、古き良き昭和のイメージでしょうか。社員はもちろん、東京ドームシティを訪れる多くの方々が、昭和のころの楽しさや賑わいを感じられる魅力を引き出そうと思いました。

鈴木:古き良き昭和の時代。最近は当時の良さが失われていると私も感じます。私は仕事柄、企業のDX推進を支援する立場ではありますが、変革するなら人が変わるべきと常々訴えています。一人ひとりの変わろうとする意識が全社員に伝播し、全社一丸の姿勢を生み出すと考えます。昭和の時代は、全員でやり遂げよう、成し遂げようとする雰囲気が社内全体に満ち溢れていました。あの高揚感こそ、企業の変革を後押しするのです。

北原:オフィスビルや商業施設を開発する三井不動産から当社に移籍した立場だからこそ強く感じるのですが、コストをどれだけ投じても建物は建物でしかありません。その中で働く人がどんな体験を得られるのか。訪れる人がどんな喜びを感じられるのか。さらには人と人がどうつながるのか。いわゆるソフトウェアとセットで考えない限り、建物の価値は高まりません。人によって生み出される魅力こそ大切にすべきと考えます。
鈴木:昭和の時代には、ソフトウェアと呼ばれる体験が日常の中にありましたね。
北原:その通りです。私は東京の下町で育ちましたが、小さいころはまさに「向こう三軒両隣」。夕食の献立が何なのかも私が自転車に彼女を乗せて走っていても、それらの情報が瞬時に筒抜けになっていましたね(笑)。三世代同居が当たり前でしたし、そこにはたくさんのコミュニティが存在していました。しかし現在は、個人のプライバシーを尊重する時代です。核家族化が進み、近年は単身の高齢世帯も増えつつあります。こうした社会課題ときちんと向き合い、失ってはいけないものを大切に育まない限り、ハードウェアを用意するだけでは何も変わりません。そんな思いを少しでも東京ドームの事業で具現化できればと思い、経営に参画することにしたのです。
鈴木:東京ドームの経営に関わり始めて約3年。これまでどんな点に注力し、事業のあるべき姿を模索してきたのでしょうか。
北原:年間4000万人の利用者数を5000万人、6000万人に増やしたいと常々考え、その手段としてDXの推進を検討しています。DXを成功させない限り、利用者数の増加は見込めません。それだけDXの重要性は増し、当社もDXの波に乗り遅れないようにしたいと考えます。
とはいえ、当社にはこうした知見もノウハウもありません。そこでこの2年間、新たなビジネスモデル創出に向けて取り組み続けてきました。特に東京ドームの魅力を世界に発信し、世界中の方々が東京ドームシティに足を運ぶようなビジネスモデルを描ければと考えます。現在はこうしたビジネスモデルのヒントを得ようと、新規事業室をはじめあらゆるセクションの社員に海外を視察してもらい、最先端の技術や人材の動向を当社に取り込もうと活動しています。米国シリコンバレーなどの現地でしか感じられない体験を社員に味わってもらい、その価値を事業創出に結びつけることに注力しています。
鈴木:オンラインではなく現地を視察するからこそ得られる体験があるわけですね。
北原:はい。東京ドームにとって、リアルの体験は強みの1つです。つまり、現地に足を運んで楽しんでもらうといったリアルにこそ、東京ドームならではの価値があるのです。リアルの体験を重視しようとする姿勢は、東京ドームで働く全社員共有の認識ですね。この2年間でこうした姿勢はより強くなったと感じます。今では何かあれば翌日には航空券を購入して現地を訪れるほど、新規事業室のメンバーは機敏に活動できるようになりました。この積極性やフットワークこそが、新規事業創出を加速させていると考えます。
新規事業室の社員の中には年に数回もの出張を繰り返し、現地の企業とのネットワーク構築に取り組むものもいます。こうした地道な活動を通じて、現在は具体的なプロジェクトを複数進行させています。肝心の内容は残念ながらお伝えできないのですが…。
鈴木:アナログ文化だった会社の体制は、社員の意識を含めて大きく変わりつつあるのですね。
北原:一足飛びに変革できるとは必ずしも思っていません。例えばインターネットの世界では、進化の過程を「Web1.0」「Web2.0」「Web3.0」で表しますよね。「Web1.0」だった当社がいきなり「Web3.0」の世界に足を踏み入れられるとは考えていません。確実に一歩ずつ取り組み、「Web2.0」の土台を築いてから「Web3.0」を目指すべきと考えます。当社は現在、まさに「Web2.0」の土台作りを進めている最中で、東京ドームシティの事業を通じて取得するさまざまなデータを集約、活用するデータプラットフォームの整備に着手しています。さらに今年度の下期からは「Web3.0」に向けても動き始めている状況です。ブロックチェーン技術やNFTを活用し、事業の価値を引き上げられないかを模索します。

鈴木:来場者を喜ばす新たな施策が次々と登場しそうな予感しか感じられません。
北原:東京ドームシティには東京ドームのほか、遊園地やホテルなどのさまざまな施設が集約しています。これらを密に連携し、唯一無二のエンターテインメントシティを作り出せればと考えます。それぞれの施設には、その施設ならではの魅力があります。その施設しか作り出せないコンテンツも豊富に揃えています。こうした唯一無二の特徴を全面に打ち出し、東京ドームシティ全体の価値を高められればと考えます。その取り組みが周囲の街づくりにも寄与し、ひいては東京の魅力を高めることにも貢献できるのではと期待します。
鈴木:施設1つひとつの取り組みがファンを呼び、その取り組みを続けることでファン同士のコミュニティが形成される。同じ熱意を持った同士が集まれば、そこからトレンドのきっかけとなるムーブメントが起こる…。東京ドームシティは、こうした流れを生み出す起点としての役割を担っているのかもしれません。
北原:そのためには、東京ドームシティに足を運ぶファンの「熱狂度」を大切にしなければなりません。どうすればファンが夢中になってくれるのか、ファンがより楽しんでくれるのか。東京ドームシティに何度も足を運んでくれるのか。「熱狂度」を引き上げる取り組みに注力し、熱狂的なファンを1人でも多く増やすことが当社の役割だと考えます。
鈴木:現在はファンの熱狂度を高める取り組みを必ずしも打ち出せていないのでしょうか。
北原:東京ドームに限らず、多くの企業は投資家や株主の満足度を満たすための取り組みに注力しがちです。市場が自社を評価する施策に舵を切りがちです。株価やROE(自己資本利益率)、さらにはPLやBSといった財務諸表などの指標ばかり気にする傾向があります。会社として必ずしも間違った考え方ではありませんが、会社が何より大切にすべきはコンシューマでありユーザーです。ユーザーの満足度を満たす取り組みに注力しない限り、ユーザーは次第に離れ、会社の価値も下がりかねません。ユーザーを熱狂させるための指標を可視化し、その指標を引き上げる取り組みこそが求められるのです。東京ドームもファン一人ひとりの声に耳を傾け、不満を1つずつ解消する取り組みを持続しなければならないと考えます。「東京ドームは誰の期待に応えるのか」と問われたら、自信を持って「ユーザー1人ひとりです」と即答できる姿勢を打ち出せるようにしたいですね。
鈴木:東京ドームとして今後、取り組みたいこと、目指すことなどがあれば教えてください。
北原:東京ドームシティは、いろいろな宝物が詰まったジュエリーボックスのような存在です。今後は1つひとつの宝物、つまり各施設をひたすら磨き上げることに注力します。その先には日本という国を超えたビジネスモデルを必ず描けると信じています。そのためには、東京のど真ん中に位置するという「場所」の強みに依存すべきではないと考えます。「場所」という制約にとらわれない魅力や強みを世界に発信することが求められているのです。その魅力や強みとなるのが、東京ドームシティならではのコンテンツです。東京ドームシティには世界から認められるコンテンツが豊富に揃っていると自負します。DXに取り組むことでこれらを世界に展開し、東京ドームシティでしか味わえない体験を訴求できればと考えます。コンテンツのバリエーションを増やすとともに、楽しく喜んでもらえるソフトウェアを整備し、世界中の方々が東京ドームシティを訪れるような未来を描きます。
鈴木:東京ドームシティの魅力は読売ジャイアンツだけではありませんよね。そこには当然、プロレスもあるしボクシングもある。格闘技好きな北原さんとしてはこうしたコンテンツも充実させたいと考えているわけですね。
北原:おっしゃる通りです。後楽園ホールで開催するプロレスやボクシングも、試合をコンテンツ化すれば世界への配信ももちろん可能です。世界をまたいでファンを獲得したり、世界規模のコミュニティさえ築けたりできるようになるわけです。実はすでに、格闘技に関するプロジェクトは水面下で動き出しているんですよ。現時点で内容までは話せないのが残念ですが…。
鈴木:東京ドームシティからどんなコンテンツが登場するのか、世界に向けてどう発信するのか。今後の取り組みがとても気になります。子供のころから熱狂的なジャイアンツファンの私にとっては、東京ドームの改革が常勝ジャイアンツを生み出すきっかけになるのではと期待します。今日は北原さんとお話でき、とても楽しかったです。貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。
北原:鈴木さんと話していたら、つい余計なことまで口走ってしまいました。本日は楽しい時間をいただき、こちらこそありがとうございました。