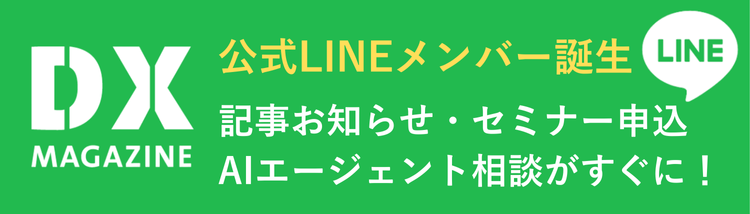昨年、グループの事業再編を断行したデジタルホールディングス。広告事業から“デジタルシフト”事業へと主力事業をピボットし、新しい価値創造を見据えた変革をどう進めているのか。事業再編の経緯と、デジタルシフトを進められずにいる企業の課題を、デジタルホールディングス代表取締役社長 グループCEOの野内敦氏に聞きました。(聞き手:DXマガジン総編集長 鈴木康弘)
経営者の思いをメンバーに届けて理解を深めよ
鈴木:デジタルホールディングスといえば社名を変えたばかり。その経緯を教えてください。
野内:2020年7月1日に社名をオプトホールディングからデジタルホールディングスに変更し、新たに「デジタル」という言葉を冠に沿えました。社名変更してまだ1年足らずですが、デジタル=当社という認知がようやく浸透してきた感じですね。
DXやデジタルシフトといった支援事業を拡大したいというのが社名変更の狙いです。当グループにとって屋台骨だったインターネット広告代理事業からの依存体制脱却という思いもあった。さらに、国内企業の多くが人手不足という課題を抱える中、デジタルシフトには生産性向上に寄与できる側面が大きい。これからの企業がさらに悩むであろう大きな課題解決の支援ができる組織になりたいと考えました。
鈴木:社名を変えなくても、デジタルシフト支援事業をできるはず。
野内:オプト=インターネット広告代理店と思われるほど世間に認知され、その結果、オプトの存在が強くなり、インターネット広告代理事業以外の事業が生まれにくくなった。広告案件の相談はあるが、それ以外の与件をなかなかもらえないという課題が顕在化してきたんです。また、インターネット広告市場は徐々に成熟化し、また自動化が進み人の手が介在しないプロダクトも増えた。過去のような大幅な増加は見込めないとも考えていました。
そんな中、顧客ニーズの変化も感じるようになりました。広告を使って集客しようという考えから、広告以外の手でマーケティングを強化したいという考えにシフトするようになった。当社としては当然、こうしたニーズに応えたいと思いました。当社の事業構想はネット広告だけにもちろんとどまりません。そこでオプトの存在感をあえて弱め、新たな社名、体制でデジタルシフト事業に舵を切ろうと決めたのです。
鈴木:知名度のある「オプト」という社名を残さなかった。事業の方針転換も含め、反対意見もあったのではないでしょうか。
野内:いろいろな意見があったと思います。ネット広告をやりたくて入社した人が大半なので、変化を受け入れられずに辞めていった人もいるでしょう。しかし、企業が存続していくためには、時代に合わせた変革が不可欠です。企業のデジタル化は必ず必要な取り組みになると信じていましたし、デジタルシフトを支援して企業や社会に貢献できるチャンスがあるなら、当然やるべきだと判断しました。メンバーたちも時代の変化を実感し、変革が必要だと考えるメンバーも多く、役員含め協力的で進めやすかったですね。
鈴木:確か創業時のメンバーは今、野内さんと代表取締役会長の鉢嶺さんのお二人。これまで何度も変革を断行してきた二人にとって、今回の変革をどうとらえていた?
野内:私はもちろん、鉢嶺もワクワクしていたと思います(笑)。我々は変革が大好きですから。成長しそうな市場を見つけたときのワクワク感は、グループ内の誰より持っているかもしれません。
鈴木:トップの楽しそうな思いが、変革を進めるときには必要なのかもしれませんね。
野内:ただ、経営者がいくら旗振りしても現場は白けているケースがあります。経営者の覚悟があればいいというものでもないと思います。組織やメンバー、トップという垣根を超えて共創する企業風土が大切です。
鈴木:同感です。デジタルシフトやDXを推進させる上で大事なのはまず経営者、次が企業風土。つまり人の意識だと思います。私もクライアント企業のデジタルシフトを支援する際、経営者の声はもちろん、メンバーの意識や思いにまで気を巡らせるようにしていますね。
野内:メンバーの不満などをヒアリングすることもありますか?
鈴木:はい。特に現場の理解を徹底します。例えば、ピザをデリバリーする会社を支援するなら、当社のスタッフは実際にピザを焼くなどして、身を持って現場を知るよう努めます。経営者の言っていることと現場の思いって温度差があることが少なくない。こうした差を埋めるには、現場の状況やメンバーの思いを理解することが大切ですね。
野内:経営層と現場の思いが乖離するのは、どの企業でも起こり得るもの。当グループも例外ではありません。そこで当グループは月に一度、グループ全社会議の場で15分ほど、私がメッセージを発信する機会を設けています。私が事業をどう進めようと考えているのかをグループ全体で共有するのが狙いです。さらに四半期ごとの決算報告をグループに説明する機会も設けています。私が決算情報と今後の事業展開や改革案などを説明します。どんな方法や手段でも、徹底したコミュニケーションを図ることが大切なのではと考えます。
とはいえ、全員が全員、最初から私の考えに共感してくれるとは思っていません。そんな中でも変革を断行するには、共感するメンバーから浸透を図り、次第に定着させていくのもありかと思います。
鈴木:「2:6:2の法則」ってありますよね。企業変革を進めようとするとき、熱意のある優秀なスタッフが2割、中間層が6割、否定的な意見を持つスタッフが2割に分かれると思います。このとき、中間層と否定的な意見を持つ層をどう巻き込むかを考えることが大事だと思います。変革を断行したものの定着しなければ、せっかく巻き込めたとしても中間層や否定的な意見を持つスタッフの層に戻ってしまう。どう定着させ、根付かせるか。ここにも目を向け、取り組まないとですね。
野内:メンバーに対し、分かりやすいメッセージを発信することも経営者の役割の1つです。経営者って一般的に、「市場」や「夢」「社会性」などの言葉を使いがちです。現場のメンバーにとっては、未来の話すぎて、今の自分の仕事とどう関係するのかが分からないということもあるでしょう。こうした理解度を高める工夫や配慮が経営者には求められるでしょう。理解度を高められなければ、変革を定着させることもできませんしね。
変革を想定した危機感を持つデジタル人材育成を
鈴木:DX推進を阻害する要因の1つに、ITやデジタルに精通する人材が社内にいないことが挙げられます。デジタル人材を育成できないという問題もあります。デジタルホールディングスはクライアント企業の人材不足に対し、どんな解決策を提示していますか?
野内:確かに「人材不足」を課題に掲げる企業は多いですね。そこで当社は現在、「デジタルシフトアカデミー」というデジタル人材を育成する教育講座を展開しています。まだ開設して間もないですが、受講生の半数以上が会社の役員なんです。講座で学んだことを自社に持ち帰り、イノベーション創出に寄与できるようにします。
「社長のためのデジタルシフトクラブ」というサービスも提供しています。DXやデジタルシフトの必要性や危機感はあるものの、“何から手を付けて良いか分からない”といった企業に対し、セミナーを通した情報提供や月額50万円で全従業員がDX講座を受講できるといったサービスです。このようなソリューションを通して、日本のDXを底上げしていきたいと考えています。
一方で、スタートアップ企業の中にはメンバー全員がデジタル人材というケースもあるはず。「デジタル人材がいない」と嘆く大企業と対照的に、デジタル人材は豊富にいるように思います。極端かもしれないが10年後20年後、こうしたスタートアップ企業が現在の大企業に成り代わって台頭していることもあり得るのではないでしょうか。
鈴木:楽天やソフトバンクが好例ですね。これらの企業はデジタルを駆使し、わずかな期間で一気にトップに上り詰めた。ご指摘の通り、スタートアップ企業が少ししたら大企業になっていることは十分考えられますね。
確かに「デジタル人材がいない」「優秀な人材がいない」と話す一部上場企業の経営者もいますね。しかし、一流大学を卒業して狭き門を潜り抜けてきた人たちが優秀でないはずがない。もし優秀でなく何もできないなら、育成を間違えているんじゃないですかね。もしくは、営業や開発などの特定職種の専門性を追求するといった従来の育成手法が当てはまらなくなっているのかもしれません。これからのDX時代は、マルチスキルが求められます。職種や業種の垣根を超え、共創を前提にした事業を展開するなら、いろいろな経験やスキルを持つ人材を育成することが欠かせません。
野内:変革を前提とした仕事をしていないのが、「育たない」要因かもしれません。特に大企業の変革は、既存事業を守りたいというバイアスが働くこともあってなかなか進まない。危機感を持てないという状況が、デジタル人材を育てにくくしているのでしょう。
この続きを読むにはログインが必要です
まずは紙のデジタル化を完了し、業務プロセス改革に着手せよ
鈴木:新型コロナウイルス感染症のまん延は、企業のデジタルシフトを加速させる大きな契機となりました。追い詰められてデジタル化に踏み切った企業も多いが、DXはこの先2~3年が勝負になると見ています。
野内:デジタル化なんて必要ないという考えを一蹴したのが新型コロナウイルス感染症です。例えば飲食店の場合、おいしい料理と集客しやすい立地さえ考えればよいと思われていた。しかしコロナによってデジタル化が急速に進みました。観光業や宿泊業も同様です。いろいろな状況を想定し、当然のこととしてデジタルを活用するフェーズに入ったと感じます。
鈴木:しかし、デジタルシフトの取り組みは企業によってまちまち。取り組みが不十分なケースも多い。
野内:デジタルシフトを分解すると、コンテンツをデジタル化する「デジタイゼーション」、プロセスをデジタル化する「デジタライゼーション」、ビジネスモデルそのものをデジタルで変革する「デジタルトランスフォーメーション」の順にステップアップすることになります。現在、大半の企業がデジタイゼーションとデジタライゼーションの間という認識です。ここ数年で、最低でも紙の書類をデジタル化するデジタイゼーションを完了させないといけないと思います。
今からデジタイゼーションに取り組めば、すぐにでも次のデジタライゼーションに着手できると思います。多くの企業がSaaSを導入し、バックヤード業務の効率化を進める動きが活発化するのではと見ています。
鈴木:SaaSを導入するにあたり、やはり業務プロセスの見直しは避けられない。業務プロセス改革でつまずく企業も増えるのではないでしょうか。
野内:確かに無駄を洗い出し、効率的でボトルネックを解消する業務プロセスを設計するのは大変です。しかし一方で、業務を支援するSaaSを次々導入し、SaaSに合わせた業務プロセスに改修するという手もある。これならゼロから業務プロセスを見直す手間を省けるし、無駄のない業務プロセスを容易に導入できるようになります。こうしたアプローチで業務プロセスを見直してもよいかもしれません。もし業務プロセスが自社に合わなければSaaSを解約して別のSaaSを導入すればよい。割り切って導入できるのがSaaSのメリットです。SaaSのメリットを存分に活用し、デジタライゼーションを進めるべきだと考えます。
鈴木:SaaSの利点を活かすにしても、業務プロセスを見直す取り組みはデジタイゼーション以上に高いハードル。乗り切るために大切なことは?
野内:当グループも手を焼いていますね。今回の事業再編を機に、BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)部門がすべての業務プロセスをチェックしています。当然そこには無駄があるし、無駄を省いたと思っていた業務プロセスでも省力化できる要素がいくつも残っています。それだけ手間のかかる作業なので、十分な期間と綿密なスケジュールを設けて取り組むことが必要ですね。
鈴木:デジタルホールディングスのような変革を起こしたいと考える企業は多いが、できずに苦しんでいる。こうした企業が成功への踏み出すためには大切なことは?
野内:失敗を恐れずに続けること。これ以外ないですね。例えば新規事業って失敗するリスクが高い。だからといってやらないという選択肢はない。失敗したから止めようではなく、チャレンジし続ける「覚悟」が大切です。失敗して「だからデジタル化って無意味なんだよ」なんて思ってほしくないですね。
鈴木:DXでは経営者の役割が極めて大きい。失敗を恐れてブレーキをかけず、どれだけアクセルを踏み込めるか。その覚悟が大切ですね。
野内:経営者にどれだけの責任と権限があるかも大事です。例えばオーナー企業の“オーナー経営者”や“創業社長”は責任も権限もある。だからこそ変革を断行できるのだと思います。しかし、”サラリーマン社長”では必ずしもそうではない。リスクの高いDXに失敗すれば責任を問われ、社長を退任させられるかもしれない。取締役会で同意を得られなければ改革案すら進められない。しかし、DXを断行しないことには、その後の成長に確実に影響があるはずです。オーナー経営者や創業社長に負けないためには、変革を断行する強い意志と行動力のあるプロ経営者を登用するのも手だと思いますね。
鈴木:なるほど。DXを実践してきたからこそ重みのある言葉をたくさんいただきました。本日はありがとうございました。
野内:ありがとうございました。