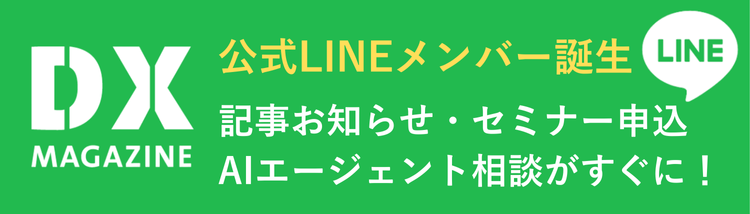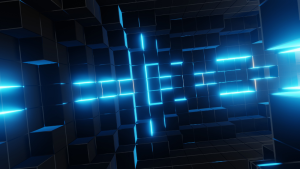日本オムニチャネル協会の活動をサポートする「フェロー」。分科会に参加してオブザーバーとして意見したり、会員にアドバイスしたりとその取り組みは多岐に及びます。オムニチャネルやDXに取り組む企業に対し、どんな課題を払拭し、どんな一歩を踏み出すべきと考えるのか。今回は、EC事業やデジタルマーケティング、CRMなどの領域に精通する大西理氏に話を聞きました。(聞き手:DXマガジン編集部)
大西:デジタルマーケティングを推進する部署の若手に目を向けると、目の前の業務をさばくだけで手いっぱいの状況です。これでは情報収集もままなりません。上司は外部からの情報を積極的に収集してインプット量を増やせるよう配慮すべきでしょう。上司は部下に対し、デジタルマーケティングを始めとする新たな動向について学べる環境をきちんと用意することが大切です。
もっとも事例に偏重する傾向は好ましくありません。イベントなどで講演すると、聴講者から「事例をもっと聞きたい」という声をよく聞きます。しかし事例をただ真似するだけでは再現性はありません。事例先の企業と自社とでは取り扱う商品・サービスや顧客が異なります。会社が顧客に対し、どんな価値を重視するのかも異なります。こうした状況で事例を真似しても、参考にはなれどもその通りなぞることはできません。大切なのは、事例を自社独自にアレンジして考えられるかどうかです。自社の顧客だったら何を求めるのかという視点を組み合わせてアレンジ法を模索することが大切です。
ツールの導入事例も然りです。事例同様の効果を見込めるとは限りません。事例企業と自社とでは業務設計や企業文化、組織構造など、さまざまな面で異なります。ツールを導入したとき、自社の課題がどう解決するのかを描けなければ意味はありません。こうした視野を持つことが重要です。
では、デジタルマーケティングを検討する上で何を重視すべきか。それは、自社にとってのクライアント、顧客が何を望むのかに尽きます。BtoB向けでもBtoC向けの事業でも、顧客を理解することを優先すべきです。自社の顧客は何をしたら喜ぶのか。この問いに徹底して向き合うことがデジタルマーケティングでは欠かせません。
企業の取り組みを見ると、顧客の理解が圧倒的に足りていないように感じます。顧客を無視してマーケティング施策を突き進める企業さえあります。こうした企業は、自社の課題を明確に把握できずにいるケースが少なくありません。「売上が伸びない」「顧客が増えない」といった漠然とした課題認識ではなく、その理由を突き詰め、課題の本質を探ることに取り組むべきでしょう。
顧客を十分理解していない例として、SNSの活用があります。ある企業はプロモーションにInstagramを活用しようとしていたとします。しかしそもそも、その企業の顧客は本当にInstagramを活用しているのでしょうか。もしかしたらTwitterユーザーの方が多いかもしれません。反応率もTwitterの方が高いかもしれません。こうした調査なしにSNSでプロモーションを実施しても十分な効果を見込めません。限られた人員でプロモーションを展開するならなおさらです。まずは顧客を理解し、SNSによる効果を正しく、公平に見極めるようにすることが大切です。
――小売業に限ると、顧客一人ひとりと向き合うパーソナライズの重要性が増しています。企業はパーソナライズを前提としたマーケティングをどう展開すべきでしょうか。
大西:小売業ではこれまで顧客を一人ひとりで識別できずにいました。今なお、多くの小売事業者が識別できずにいます。これからは本腰を入れて顧客のパーソナライズ化に取り組むべきです。そのための体制やシステムに投資できるか。経営者の判断も求められるでしょう。
顧客一人ひとりを理解するには、店舗やEC、アプリなどのチャネルごとにどうアクションしたのかをほぼリアルタイムに分析できる環境をつくるのが望ましいでしょう。このとき必要となるのがCDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)です。
もっともCDPにデータを貯めるだけでは十分な効果を見込めません。データを集約するものの、使えないデータを蓄積するケースがあります。収集したデータの活用方法が分からないという企業も少なくありません。商品マスターが古く、顧客理解に適さないものを運用し続ける企業も珍しくありません。
趣味や関心、嗜好といった顧客理解に欠かせないデータを収集できるかどうかがカギです。例えば、「味が濃い食べ物が好き」「赤いワインを好む」などの嗜好を見極める要素をデータとして蓄積することが求められます。どんなデータを収集すべきかはマーケティング部門が主導し、CDPをきちんと活用できる体制をつくるようにします。
ただ、CDPを構築しても、用途はメール配信に限られるケースが散見されます。これでは趣味や嗜好に関するデータ、さらには購買データ、POSデータ、ECの利用履歴などをCDPに統合しても意味はあまりありません。CDPの効果を最大化するためにはデータサイエンティストなどを活用し、メール配信以外のマーケティング施策を立案、実施できるようにすべきです。もし社内にデータサイエンティストなどの人材がいなければ、コストはかかるかもしれませんが、専門の外部企業と組んでマーケティング施策を実施し続けると腹をくくることも必要になるでしょう。
新型コロナウイルス感染症のまん延を機に、多くの小売業がDXに取り組み出しています。大切なのは一過性の取り組みとして終わらせないことです。コロナ終息やインバウンド需要回復などによりDX推進を必要と考えなくなるケースが懸念されます。1年後の市場変化を読み取るのでななく、5年後、10年後といった中長期の視点で目標を立て、ブレることなくロードマップを突き進むべきです。DXへの思い、ビジョンをロードマップに落とし込み、数年先を見据えて地道に取り組むことが大切です。
――人材不足に悩む企業も多い。デジタル人材を育成、確保するためには企業は何をすべきでしょうか。
大西:人材不足は何年も前から企業が直面する課題です。大切なのは、デジタルに精通する人材をとりあえず確保するのではなく、DXやデジタルを推進する組織形成をきちんと検討することです。入社した人材が社内できちんと立ち回れるか、さらには人材を正当に評価する人がいるかどうかも重要です。もし正当に評価できれなければ、その人材は長続きすることなく辞めてしまうでしょう。こうした評価体制を用意せずにデジタル人材を迎え入れようとする企業は少なくありません。まずは組織形成を主導し、人材を評価できる責任者から確保し、その後、組織構成を踏まえた人材を採用するのが望ましいでしょう。
【JOAフェロー岩瀬昌美氏に聞く】セグメントの重要性高まるマーケティング、基礎知識ナシに施策は成功しない –

DXの取り組みは“勝つまで諦めるな”、毎日の成長を感じられる楽しみこそDXの魅力/日本オムニチャネル協会 フェロー対談 –