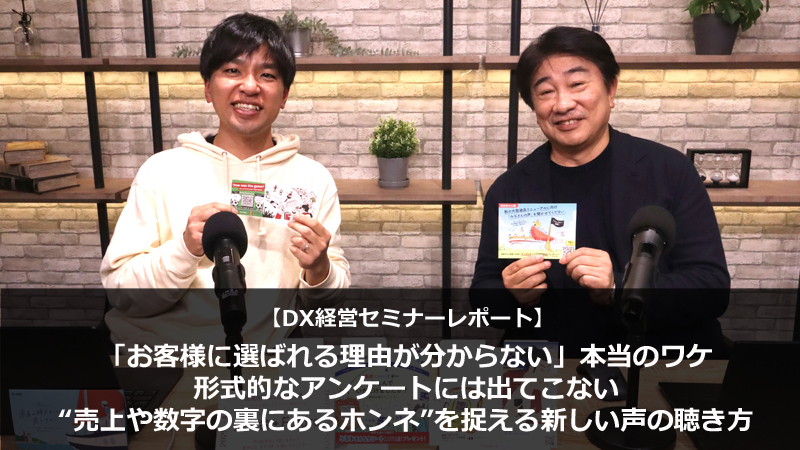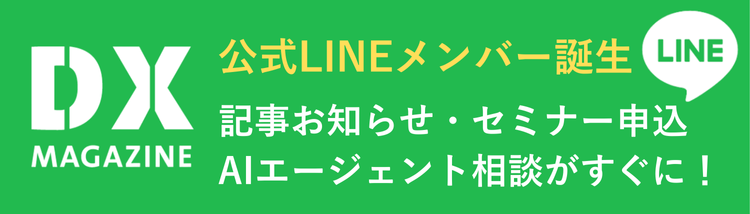デジタルシフトウェーブは2025年12月9日、定例のセミナーを開催しました。今回のテーマは「現場に埋もれている『お客様のホンネ』を経営に活かす~アンケートの常識をひっくり返す、新しい声の聴き方『ホンネPOST』~」。売上や来店数、満足度スコアは把握できている。アンケートも定期的に実施している。それでも「なぜ選ばれているのか」「なぜ離れていくのか」が、腹落ちする形では見えてこない。そんな企業担当者の実感を出発点に、形式的なアンケートでは拾えない“数字の裏側”に目を向け、これからの顧客の声との向き合い方を議論しました。
「売上や数字は悪くない。でも、なぜかリピート率は伸びない」、「来店はある。けれど、“なぜ選ばれているのか”を自信をもって説明できない」。
多くの企業担当者が、こうした言語化しきれない違和感を抱えています。その背景にあるのが、“声を出さないお客様=サイレントカスタマー”の存在です。クレームも要望も言わず、静かに離れていく顧客。一方で、特に何も言わないまま、密かに応援し続けてくれている顧客も多くいます。見えていない顧客はリスクであると同時に、価値のある“手がかり”を持った存在でもあります。
問題は、その声が売上データにも、NPSにも、そして形式的なアンケートにも、ほとんど表れないことです。結果として、「数字は見ているが、判断材料としては足りない」、「集めた声が、集計で止まり、意思決定に届かない」という状態に、多くの企業が陥っています。
では、どうすればサイレントカスタマーの声を可視化し、現場と経営の“使える情報”に変えられるのか。
今回のセミナーでは、この問いを起点に「顧客の声」に真正面から向き合いました。形式的なアンケートでは拾いきれないお客様のホンネを、どう引き出し、どう施策につなげるのか。ゲストに株式会社はこぶん 代表取締役・森木田剛氏を迎え、同社が提供する顧客コミュニケーションツール「ホンネPOST」の活用事例をもとに、売上改善やリピート率向上につながる具体的な実践アプローチが紹介されました。
言いづらい」社会と「ニーズの複雑化」、そして「伝わらない」組織構造が生む経営の死角
なぜ今、顧客の声はこれほど見えにくくなっているのか。その背景には、「社会・市場・組織という三つの構造変化が重なっている」(森木田氏)といいます。

1. 社会背景:「言いたいことが言えない」空気の常態化
まず前提として、社会全体に「言いづらさ」が広がっています。SNSでの炎上リスクやコンプライアンス意識の高まりなどを背景に、言葉を発することのコストは年々上がり、沈黙は最も安全な選択肢になりました。また企業側も、個人情報保護の強化もあり踏み込んだ感想や個人的な体験を気軽に尋ねることが難しくなっています。
かつては、対話の中での多少の言い過ぎや行き違いも「お互い様」として受け流されていました。しかし現在は、特にSNSの発展によって、一つの発言が予期せぬ形で切り取られ、評価され、拡散される可能性を常に意識せざるを得ません。
その結果、社会全体に「間違えないこと」「目立たないこと」を優先する空気が広がり、互いの言動を監視する感覚に近い、粗探し中心の構造が強まっています。こうした社会背景のもとでは、企業に対して意見や感想を伝える行為そのものが、「コミュニケーションコストの高い行為」として受け止められがちになります。
モノや情報はかつてないほど豊かになった一方で、人は本音を気軽に語れる場を失い、たとえ何かを感じていても、言葉になる前に飲み込んでしまいます。
ビジネスの現場では、効率化や自動化が進んだことで、偶発的な会話や「気軽なコミュニケーション」の接点そのものも減少しました。その結果、顧客の多くが喜びも不満も口にしないサイレントカスタマーになりやすい環境が生まれ、かつて企業と顧客のあいだにあった自然な対話の機会は、静かに遠のいています。
2.市場環境:「情緒的価値」が選ばれる“決め手”になる時代
同時に、市場そのものも成熟しています。機能・品質・価格といった一次ニーズはすでに満たされ、商品やサービスの水準は全体的に底上げされ、「明確に悪い選択肢」は少なくなっています。その結果、顧客の判断軸は「どれが一番優れているか」から、「どれが自分に合っていそうか」へと移っています。ここで効いてくるのが、「二次ニーズ」です。店員のひと言、待ち時間の印象、ふと目に止まった案内…。顧客が「これにしよう」と決める瞬間は、実はとても些細で、「なんとなく」の直感や印象です。
しかしその一方で、この二次ニーズは顧客ごとに細かい感情のニュアンスを含むため、点数評価や選択式の形式的なアンケートでは捉えにくく、企業側から見ると、「なぜ選ばれているのかが分からない」「何が効いているのか確信が持てない」という状態を生み出す原因にもなっています。
3. 組織構造:「間接情報」で本質が削ぎ落とされる
こうした「二次ニーズ」は、非常に微細なニュアンスを含むため、従来の組織構造では経営層まで届きにくいという課題もあります。最大の障壁となるのが、「間接情報」です。
現場スタッフが肌で感じ取る、顧客の表情や言葉のトーンといった生の情報は、会議資料や報告書にまとめられる過程で要約され、整理され、無難な表現に置き換えられていきます。結果として経営層に届くのは、感情や文脈が削ぎ落とされた“整理済みの情報”です。間接情報に依存すればするほど、「なぜそれが起きたのか」という本質的な要素は見えにくくなります。
その結果、企業は売上や数値は追えているのに、選ばれる理由や離脱の理由を、手応えとして掴めない状態に陥ります。情緒的価値が競争の決め手になる時代において、この“情報が届くまでに薄まってしまう構造”こそが、現場と経営のあいだに生まれる、もう1つの大きな死角と言えるでしょう。
つまり、「顧客は本音を言いづらく(入口の摩擦)」、「選ばれる理由はデータ化しにくい情緒的価値へシフト(ニーズの複雑化)」、「そのわずかな手がかりが組織の中で間接情報で削ぎ落とされる(伝達の劣化)」。この三重の構造こそが、多くの企業が直面している「お客様に選ばれる理由が分からない」という経営課題の正体です。
「調査」から「対話」へ。サイレントカスタマーの“無言の関心”を経営資産に変える
では、この三重の経営課題をどう突破すべきなのか。森木田氏は、その鍵は従来の「アンケート調査」の概念を捨て、「顧客との対話(コミュニケーション)」へと仕組みを根本から転換することにあると提言します。
- 既存アンケートの限界
まず直視すべきは、従来のアンケート手法が抱える構造的な欠陥です。多くの企業が実施する設問式アンケートは、顧客にとって回答欄を埋める「作業」でしかありません。企業都合の問いに対し、顧客は「答えさせる」体験です。この受身の調査プロセスにおいて、人は無意識に「理屈」を探そうとします。
本来、購買の決定打となる「二次ニーズ」は直感的で感情的なものですが、このアプローチでは、顧客は論理的思考(もっともらしい説明)で回答を構築してしまいます。その結果、企業の手元には建前のデータばかりが集まり、本当に知りたい「熱量」や「感情の機微」が抜け落ちてしまうのです。
2. アプローチの転換:「答えさせる」から「伝えてもらう」へ
そこで同社が提唱するのが、「デジタル手紙」というアプローチです。「ホンネPOST」は、アンケートではなく、「お店への気持ちを手紙を綴る」という世界観で設計されています。
最大の違いは、主語の転換です。「企業が知りたいことを聞く(調査)」のではなく、「顧客が言いたいことに耳を傾ける(対話)」という構えを、現場の案内表現(デザイン・コピー)から投稿画面のUIや言葉づかいまで、一貫して徹底しています。
無機質な設問フォームで情報を“取る”のではなく、適切な距離感と、感情を乗せやすいデザインと言葉で体験を設計することで、顧客の中に眠っていた「ちょっと伝えてみようかな」というマイクロモチベーションが自然に引き出されます。こうしたUIと現場体験を一体で設計するアプローチによって、寄せられる声の多くは、クレーム対応を前提としたアンケートで想定されがちなネガティブなものではなく、「ちょっとした喜びの声」や「応援したい気持ち」といったポジティブな声が中心になります。
実際、全体の約6割がポジティブな内容で占められており、これまで沈黙を守っていたサイレントカスタマー、特にサイレントファンの「無言の関心」が言葉として届くことが可能になっています。
3. 感情分析AIで「情報の鮮度」を保つ
集まった顧客の「ホンネ」を経営に活かすためには、組織の壁(間接情報の弊害)も取り払う必要があります。 「ホンネPOST」では、投稿された生の声を、現場の店長から本部の経営層までが同じダッシュボードでリアルタイムに閲覧できる仕組みを構築しています。膨大なテキストデータは感情分析AIによって解析され、「好意的な点」「改善の余地がある点」などに精緻に分類・順位化されます。顧客の声を「感情の温度」を保ったまま可視化し、分かりやすい・共有しやすいカタチで組織全体に循環させる。この仕組みこそが、現場と経営の分断を解消し、選ばれるための「二次ニーズ」を掴むための核心となるのです。
セミナーでは、「ホンネPOST」の導入事例も紹介されました。
カレー専門店を展開する飲食チェーンでは、従来のハガキ型アンケートと比べ、投稿数が約20倍に増加。声の量だけでなく、その“質”にも大きな変化が見られたといいます。寄せられたのは、点数評価では捉えきれない声でした。
「学生の頃から数十年以上通っている」「この新商品があまりにも美味しくて思わず書き込んだ次第です」といった、数字の裏にある関係性や感情がにじむ言葉が多く集まり、これまで把握しきれていなかった“選ばれている理由”が言語化されたといいます。
さらに、集まった声は現場と本部でリアルタイムに共有。同じダッシュボードを見ながら、改善の議論が即座に行われ、定性情報を起点にした現場改善がスピーディに回り始めたとのことでした。形式的なアンケートでは集計で止まっていた声が、「感情の温度」を保ったまま組織に届き、現場と経営が同じ材料をもとに意思決定できる状態が生まれ始めています。
モデレータを務めた鈴木康弘氏は事例を踏まえた上で、「経営者が顧客の声に真摯に向き合う姿勢が何より大切だ。迅速に反映できる環境が整えば、組織には自然と緊張感とスピードが生まれる。特に即時性が求められる飲食や小売の現場では、顧客の本音をいかに早く事業に活かせるかが、競争力を左右する」と語りました。

これからの顧客コミュニケーションのあり方ついて、森木田氏は「顧客分析の取り組みは、ネガティブな声への対処だけで終わらせてほしくない。何も言わないサイレントファンの中にこそ、なぜ選ばれているのかという“本当の理由”が眠っている。そうしたポジティブな声が届く仕組みを作ることで、企業は初めて、自分たちの提供価値の核心に気づけるようになる」と視点の転換を促しました。言いづらさが常態化し、本音が表に出にくい時代だからこそ、企業側から歩み寄り、気軽な対話が生まれる余白をつくること。集めた声を“使われる情報”として循環させていくこと。
森木田氏は最後に、本音で語り合える関係性が社会に広がることで、企業の創造力そのものが高まっていく未来への思いを語りました。
【関連リンク】
株式会社はこぶん:https://hako-bun.com/
ホンネPOST:https://honne-post.com/