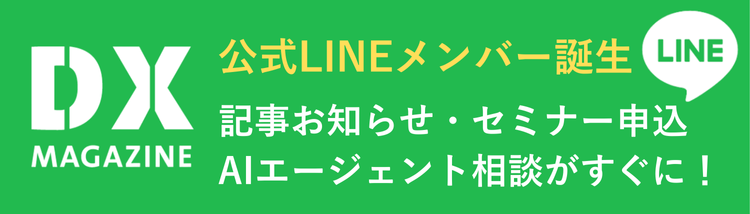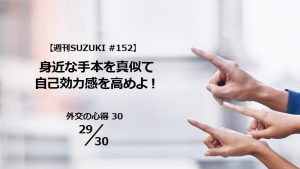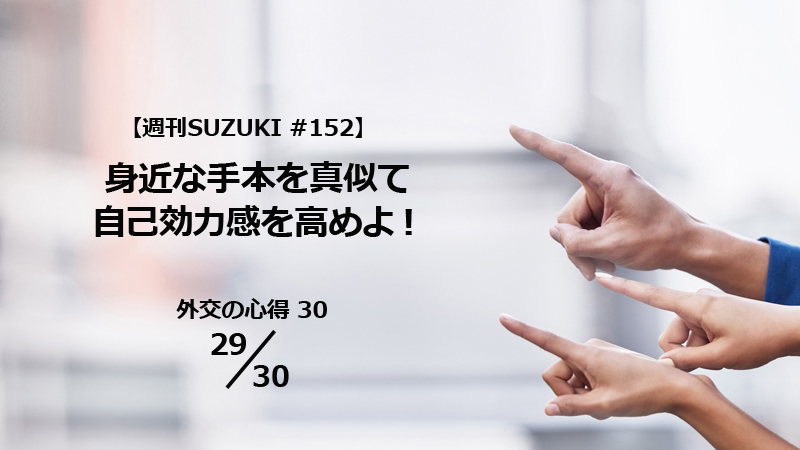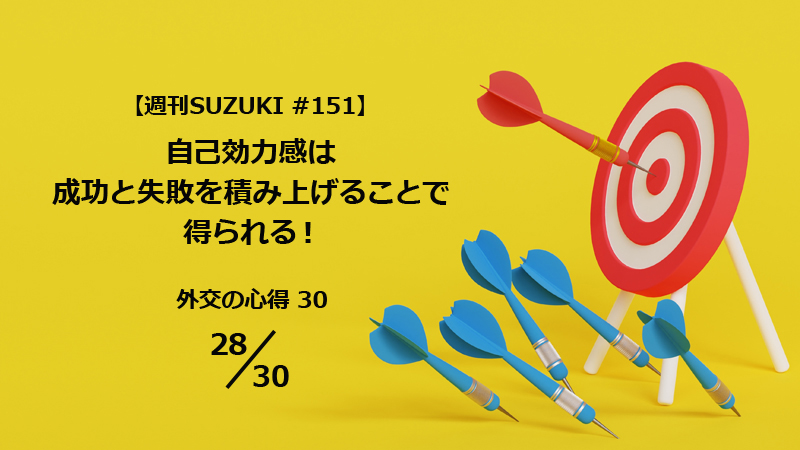日本オムニチャネル協会は2023年11月28日、定例のウェビナー「IT勉強会」を開催しました。特定領域のITの動向や製品・サービスを解説する勉強会で、今回はHR(Human Resource)や教育領域の最新動向について解説しました。
多くの企業が喫緊の課題として取り組む人材育成。自社の成長に貢献する人材をどう育成すべきか、さらにはスキルや経験に基づく最適な人員配置をどう進めるべきかなど、人を起点とした組織づくりに取り組む動きが加速しています。
とはいうものの、「優秀な人材が育たない」「せっかく育てたのに離職してしまった」「従業員の長所や強みを見極められない」などの課題を抱える企業は少なくありません。
そこで、人材の育成や教育、さらには最適な人員配置などを支援するHR領域のIT製品・サービスの導入を検討する動きが広まりつつあります。具体的にどんな機能を備え、企業の「人材」にまつわる課題をどう解決するのか。今回のIT勉強会では、HRや教育関連のサービスを提供する3社が登壇。各社が提供するサービスの特徴や強みを解説しました。
人事・労務業務の煩わしさ解消を図る
最初に登壇したのは、SmartHR プロダクトマーケティングマネージャーでタレントマネジメント事業 事業責任者の重松裕三氏。「SmartHRで実現する人事労務のDXとタレントマネジメント」をテーマに、同社が手掛ける人事労務サービス「SmartHR」の特徴を紹介しました。
重松氏は「SmartHR」を活用することで人事や労務に携わる業務負荷を軽減できると指摘します。「人事や労務の手続きにはさまざまな書類を用いることが少なくない。SmartHRを使えば、こうした書類のペーパーレス化を図れる。紙の処理に時間を割いたり、ハンコを使ったりといった無駄を省ける。人事情報をクラウドで一元化するので、各組織の最新状況を容易に把握できるようになるのも利点だ。従業員のスキルや経験を可視化するタレントマネジメントとしても利用でき、離職率低下やスキルに応じた最適な人員配置も見込める」(重松氏)とメリットを強調します。
従業員のデータベース機能のほか、入社手続きを支援する機能、スキル管理や評価機能、さらに従業員をある部署に配置したときの効果を把握するシミュレーション機能なども備えるといいます。「人材・労務部門の業務は煩雑なケースが少なくない。こうした煩わしさをいかに解消するかに主眼を置いている。作業時間を短縮すれば、新たな施策立案や優秀な人材獲得などの業務に集中できる。企業のこうした取り組みを支援するのが当社の役割であり、目指すべき世界感である」(重松氏)と述べます。

「SmartHR」の具体的な機能にも言及します。例えば、申請・承認機能では、給与振込口座や通勤経路の変更、資格取得の申請などを迷わず進められるといいます。「SmartHRの登録済情報を容易に変更できるよう配慮する。従業員が操作に迷うことなく情報を変更できるよう、フォームを自由にカスタマイズできる」(重松氏)といいます。さらに、年末調整に関する機能では、「アンケート形式で年末調整を済ませられるよう工夫する。『はい』や『いいえ』などと回答し、設問に答えるだけで申請を完了できる。分かりにくい設問にはヒントを設け、従業員が迷うことなく年末調整を進められるようにする」(重松氏)と、細かな点まで配慮している点を売りにします。
一方、タレントマネジメント機能の利点にも触れます。SmartHRは、従業員の最適な人員配置を可能にするための機能を装備。「多くの企業が十分な根拠なしに人員を配置しているのが現状だ。しかし、SmartHRを使えばデータに基づく人員配置を可能にする」(重松氏)と声高に強調します。SmartHRでは、人員配置の参考となる人事情報を整理、表示。従業員の特性を見極めた上で人員を配置できるようにします。例えば、従業員の希望キャリアや、直近の評価、経歴、家族構成などの参考情報を一覧表示し、誰がどの部署に相応しいのかを選ぶ際の指標にすることができます。「人事担当者や営業部長、マーケティング部長などの配置決定に関わる人が同じ情報を参照できる。偏った評価や思い込みなしに適正に従業員を評価し、最適な部署に配置できるのが利点だ」(重松氏)と指摘します。さらに、「評価の結果やスキル・資格、希望キャリアなどの情報と組み合わせれば、配置シミュレーションによって効果を事前検証できる。SmartHRでは複数のサービス・機能と連携し、より多くの人事情報を活用できるようにする世界観を目指す」(重松氏)と、人事データを利活用する業務のあり方を提言しました。
シフト管理を軸に多様な働き方を支援
次に登壇したのは、クロスビット 代表取締役社長 小久保孝咲氏。「店舗ビジネスの採用/離職と就業環境、採用~定着~活躍-シフト管理と付随するオペレーション」と題し、同社のシフト管理サービス「らくしふ」の特徴を紹介しました。
同社は、パートやアルバイトなどを含む従業員のシフトを管理・作成するクラウドサービス「らくしふ」を提供する企業。「働くための体験をどう高めるかといった『働き方』に主眼を置く。自由に働きたい、実績に見合う報酬を得たいなど、働くことに関するさまざまな要望に応える製品・サービスのラインナップ拡充を目指す」(小久保氏)と、同社の目指すビジョンを説明します。

シフト管理サービス「らくしふ」の特徴について小久保氏は、「店舗などのシフト作成・管理を効率化する用途に留まらない。『らくしふ』では、店舗などの売上やPOS、さらにはスタッフとのチャット履歴などのさまざまなデータを活用する。こうしたデータを企業の採用活動や派遣/スポットバイトの採用に活用する用途も想定する。さらにはシフトの実績と売上を使った予実管理も可能だ。来月のシフトを組んだ場合の人件費が高すぎないか、適正なシフトなのかを、過去のシフトを参考に比較できる。『らくしふ』というサービスを起点に、さまざまなデータを駆使した働き方体験を提案できるようにする」(小久保氏)と、サービスの強みを説明します。
シフト管理以外の支援サービスのラインナップを揃えるのも売りの1つです。「採用から入社、定着、活躍、評価、支払いといった一連の流れを支援するサービスを揃える。例えば『らくしふワーク』は、企業の採用活動を支援するサービス。『何曜日の何時』といった具合に、シフトをもとに求人を募集できる。『らくしふ労務管理』は、採用する従業員の情報を管理したり、契約締結までのやり取りを支援したりする。さらに評価や給与の支払い機能を備える『らくしふ別払い』も用意する。『働く』に関わるさまざまな業務や手続きを支援し、従業員の満足度向上や業務の効率化を図れるようにする。これにより企業は、人事戦略の改革を着手、実現できる」(小久保氏)と、包括的なラインナップを揃える強みも打ち出します。
「らくしふ」を使ってシフト管理業務を効率化すれば、業績向上も見込めると小久保氏は続けます。「不十分なシフトの作成・管理は、人件費の管理精度の低下を招く。結果として利益を圧縮しかねない。シフトを作成する作業工数が増えれば、業務負荷の増大はもとより、QSC(Quality(品質)、Service(接客)、Cleanliness(清潔さ))の低下や売上の停滞さえ招きかねない。もちろん従業員の満足度も低下し、離職率増加や採用費高騰をも招く。こうした事態を回避するには、緻密なシフトを作成することが欠かせない。専用のシフト管理サービスを活用することで、結果として売上を最大化できるようになる」(小久保氏)とメリットを強調しました。
業績や売上向上に直結する学習支援サービス
最後に登壇したのは、グロースX 取締役COOの山口義宏氏。「デジタル人材をつくる最速の6ヶ月」と題し、同社のサービスを紹介しました。
同社は、DXやマーケティングなどに精通する人材の育成を支援する学習サービスを提供する企業。DXなどを推進する上で必要な知識を体系化し、短時間で効率よく学習できる仕組みに強みを打ち出します。「デジタル人材をただ育成することを目的とせず、企業の業績向上に直結する人材をどう育成するかに主眼を置いている。売上や利益を見込める人材育成を前提としているのが、競合の類似サービスにはない強みである」(山口氏)とメリットを説明します。同社のサービスを利用する企業は、2023年11月までに500社、育成対象ユーザー数は約2万人を数えるといいます。

職種別の育成支援ソリューションを用意するのも同社の特徴です。具体的には「マーケティング」「BtoBマーケティング&セールス」「AI・DX人材」「無敗営業」といったソリューションを用意。例えば「マーケティング」の場合、営業人材の高度化やデジタル化、事業・マーケ・広告・事業開発部門のマーケ人材育成、全社的なデジタル・CX人材育成などのニーズに応える育成支援を手掛けます。「無敗営業」の場合、営業人材の基礎育成・底上げを目的としたカリキュラムを用意します。
具体的にどのように人材を育成するのかにも言及します。「人材育成に乗り出す多くの企業が、『相応しいカリキュラムがない』『課題図書やeラーニングを導入しても続かない』『学んでも業績や成果につながらない』などの課題を抱える。こうした課題を取り除けるのが、当社の育成支援ソリューションの特徴である」(山口氏)といいます。具体的には、「eラーニングだけでは学習が長続きしないという企業に対し、eラーニングと集合研修を組み合わせたハイブリット研修を提供する。一緒に学べる環境を用意することでモチベーションを持続しやすくする。同僚と学習の取り組み内容を共有したり、上司が部下の進捗を把握するダッシュボードを用意したりし、一人ではなく周囲とともに学べるよう配慮する。マーケティングやDXに精通する人が監修としてカリキュラムを作成しているので、売上や利益を想定した実践的な内容を学べるのも利点だ」(山口氏)と、ソリューションの独自性を売りにします。
なお、同社のソリューションでは断片的な知識を教えるのではなく、多くの企業を業績向上に導いてきたフレームワークやケーススタディを学べる点を特徴にします。学んだことを確認するクイズや考え方を問うアンケートなども用意し、回答結果をもとにきちんと習得したのかを確認することも可能です。さらに、1カ月ごとに新しいコンテンツを公開するのも大きな特徴です。200分から400分相当のコンテンツを毎月更新し、社内の同僚などとともに学習進度を競い合う環境を醸成しやすくします。「6ヶ月のカリキュラムを通じて、従業員はもとより組織を成長させられる。チームで学習に取り組む環境を提供することで、途中で挫折することなく学びを継続できる」(山口氏)といいます。