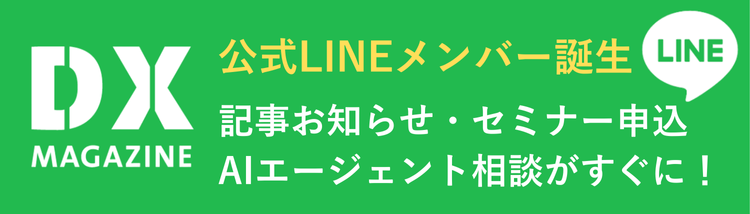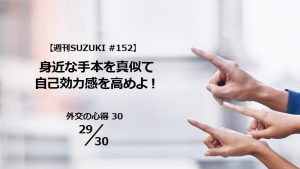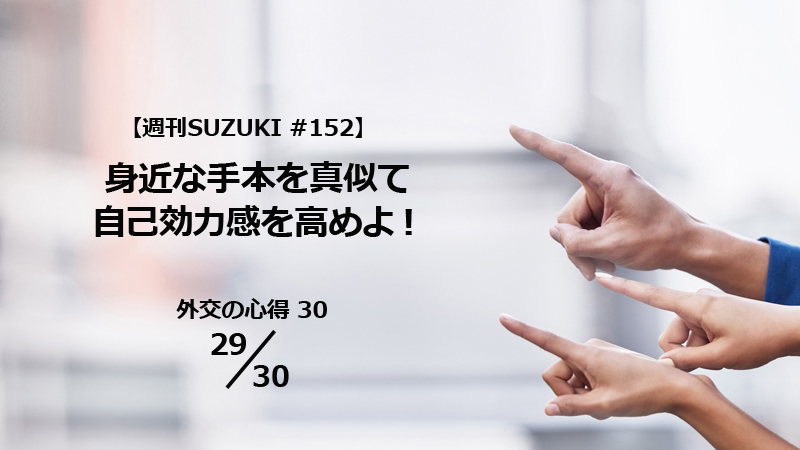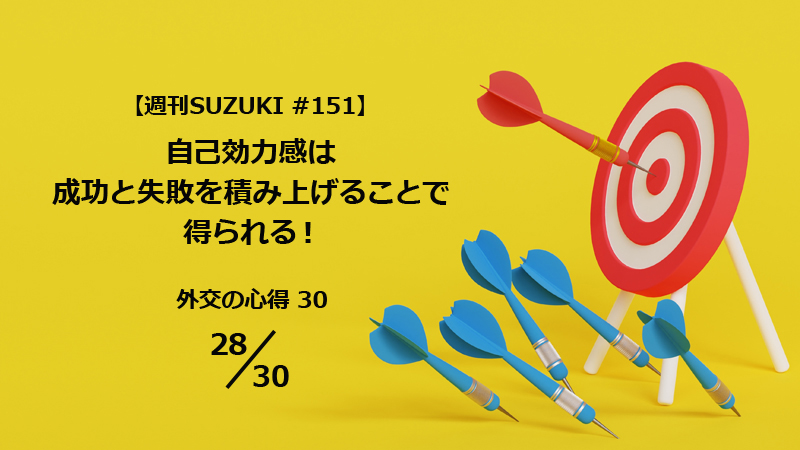新規事業を成功させるためには、周囲を巻き込み賛同を得られる企画書や資料のクオリティこそが重要。「意味が分からない」「理解しにくい」という文章を並べるだけでは事業推進すらままなりません。では簡潔で要領を得た文章で「伝える」ためにはどんな工夫が必要か。【DX時代を生き抜く文章術 第16回】は、テーマに沿った文章を書くときのコツと、テーマに関する資料収集の方法を紹介します。なお、本連載は「即!ビジネスで使える 新聞記者式伝わる文章術」(CCCメディアハウス)の内容をもとに編集しております。
今回は、ひとつ具体的な練習問題に取り組んでみましょう。
【練習問題】「記念日」ブームと呼ばれるほど、毎日のようにテレビのワイドショーで様々な記念日が紹介されています。記念日ビジネスの実態を紹介してください。
【 想定読者=販売促進または営業企画のスタッフ 】
【 目的=年間キャンペーン企画立案のための会議資料 】 まず何について書くかを明確にします。ここでは「記念日ビジネスの実態」となるでしょう。 これがひとまずタイトルになります。 そして情報収集ですが、まずはインターネット検索が一般的でしょう。 「記念日」と打ち込んでグーグル検索すると、トップに「一般社団法人日本記念日協会(https://www.kinenbi.gr.jp/)」が登場しました。検索結果ページには、日本記念日協会に続いて、ウィキペディアの「記念日」「日本の記念日一覧」があります。これらをざっと読んでみると、日本記念日協会は企業や団体などからの記念日申請を認定登録していることが分かりました。 また、暦や二十四節気について調べると、土用や大寒などの季節に根ざした行事があり、勤労感謝の日といった歴史や伝統に根ざしている〝記念日〟があることもわかりました。 ただ、これではネット検索しただけの、誰もが知っている文章になってしまいます。ここで思いを巡らし、想定読者の関心や興味があることに引き付けてリサーチを進めましょう。 例えば「ショートケーキの日」なんてあるのかな、と思ったとします。日本記念日協会のサイト内の検索機能を使ったところ、協会での登録はありません。こうなればしめたもの。グーグルで「ショートケーキの日」を検索すると、簡単に出てきました。カレンダーをみると、15(いちご)が上に載っている毎月22日がショートケーキの日だ、と。銀座コージーコーナーなどの洋菓子店が、ショートケーキの日をプロモーションに使っていることも検索結果ページからうかがえました。 次いで、追加情報を得るため、同じような面白い記念日はないか、自分の興味ある食べ物などの記念日はないか、ちょっと検索してみましょう。なんと「かき揚げの日」や「ロールケーキの日」などがヒット。記念日は企業や関係団体のプロモーションやPRで使われることが多いことが分かりました。 設問では、「記念日ビジネスの実態を紹介してください」とあります。以前、バレンタインデーはメリーチョコレートという会社がはやらせたのだと聞いたことも思い出し、「記念日ビジネスは花盛り」というファクトを盛り込んでいくことにします。 次のステップとして、集めた情報を箇条書きにしてみます。
・一般社団法人日本記念日協会
・協会の趣意に「記念日により日々の生活に潤いが生まれ、歴史が刻まれ、産業が盛
んになり、社会的に大切な情報が多くの人に届く」とコメントあり
・二十四節気、暦、伝統行事
・ショートケーキの日は、カレンダーの日並びから設定された
・銀座コージーコーナーなどがPRとして活用
・同様の事例として「かき揚げの日」や「ロールケーキの日」
・ポッキー&プリッツの日(11月11日)
・バレンタインデーが走り? 練習問題ではタイトル(見出し)は求められていませんが、ここであえてつけるとしたらどうでしょうか。 メモ書きしたキーワードを眺めた結果、「記念日ブーム、企業のPR活用が拍車」「記念日ブーム、今や2100超──語呂合わせや変わり種も」といった見出しをイメージしてみました。タイトルが決まると、箇条書きのキーワードにヌケやモレがあること、つまり、もっとほかに欲しい情報があることが見えてきます。 ちなみに、最初のメモ書きでは日本記念日協会の認定登録数が抜けていました。記念日ブームを裏付ける数字を、ということで、協会のサイトから「2020年3月末現在で2100を超える記念日が認定登録されて」いるという情報を追加しました。このデータがなければ、「画竜点睛を欠く」ことになってしまいます。 さて、いよいよタイトルを意識しながら、メモ書き情報を肉付けして文章を構成していきます。以前触れた基本のPREP法で書くことにします。 第一段落(P)で、記念日ブームの一般的な情報を紹介しつつ、企業などの民間がビジネスに活用している背景に触れます。 それを「世の中、記念日ばやり」の一言で表現し、第二段落以降でその実態を肉付けしていきます。理由(R)として、一般社団法人の日本記念日協会に登録されている記念日が2100件以上にのぼることを紹介。続いて具体的な事例(E)を持ってくることにします。記念日ビジネスの走りと言われるバレンタインデーを持ち出し、ビジネス活用の歴史は案外古いことを指摘しようと思います。 その上で、「意外な」記念日である「ショートケーキの日」を取り上げて、話を転じる工夫をします。同様な事例として「かき揚げの日」を紹介し、関連として「めんの日」「ポッキー&プリッツの日」などへと話を広げることにしました。 最後に結論として、記念日協会のコメントを使い、記念日ビジネスのさらなる拡大を見通し、冒頭の「世の中、記念日ばやり」を補強することにします。 【回答例】
(タイトル)記念日ブーム、企業のPR活用が拍車 世の中、記念日ばやり。例えば11月は暦(二十四節気など)の上では立冬や文化の日、勤労感謝の日などがあるが、民間などが自主的に決めた記念日には「いい夫婦の日」(11月22日)や「ポッキー&プリッツの日」(11月11日)などがある。制定理由はさまざまだが、メーカーや小売り、業界団体などが需要拡大を狙って記念日を制定する例が増えている。 1991年設立の一般社団法人・日本記念日協会(長野県佐久市)は、企業や団体、個人の申請を受けて、記念日を認定・登録している。2020年3月末で2100件を超え、その数は増える一方だという。 日本では女性が男性にチョコレートを贈る日になっている2月14日の「バレンタインデー」。1958年にメリーチョコレートカムパニー(東京・大田)が伊勢丹新宿本店でキャンペーンを展開したことから広まった。もともとはローマ皇帝の迫害にあって西暦270年に殉教した聖ヴァレンティヌスに由来する。 「憲法記念日」や「ひな祭り」など、国や公的機関が制定した祝日や記念日は伝統や歴史に根ざしたものが多い。これまで民間が決める記念日は「語呂合わせ」が多く、いい夫婦の日もしかり。毎月の29日は「肉の日」というのがスーパーマーケットの特売や飲食店で定着している。 ちなみに、ショートケーキの日が何日なのかをご存じだろうか。 ヒントはカレンダーの日付の並びだ。 答えは毎月22日。理由は「イチゴ」が上にのっているから。1週間ごとに数字が並んでいるカレンダーをみると、毎月22日の上には必ず15日がくる。イチゴのケーキの定番と言えばショートケーキ。22日のケーキの上に1(イチ)5(ゴ)がのっているというわけだ。仙台の洋菓子店が発案したといわれる。 同じような理由で制定されたのが「かき揚げの日」。細い麺のように数字が並ぶ11月11日が「めんの日」であることから、カレンダーでは11月11日の上にくる11月4日が答えだ。うどんやそばにのせる代表的な具材であるかき揚げを、冷凍食品メーカー、味のちぬや(香川県三豊市)が取り上げた。 めんの日の11月11日は「ポッキー&プリッツの日」でもある。発売元の江崎グリコが棒状の形状から決めた。数字の形状から取られたものには「ロールケーキの日」(6月6日)もある。記念日は日々の暮らしに潤いを与えたり、思わぬ語呂合わせで人々を笑顔にさせたりする。話のネタやビジネスのヒントにもなる。日本記念日協会も「歴史が刻まれ、産業が盛んになり、社会的に大切な情報が多くの人に届く」と記念日の効用を説く。さて、これからどんな記念日が登場するのだろうか。 この練習問題は、一般社団法人日本記念日協会のサイトにアクセスし、ウィキペディアなどで調べれば概要は理解でき、書ける問題です。回答例では、二十四節気のような季節感のあるものや国民の祝日などとは違った、語呂合わせや少しひねった記念日が増えていることを紹介しました。読み手に「ヘーっ」と思わせる文章にするには、意外なものや定番のファクトを混ぜながら書くことです。納得感が高まります。
【 想定読者=販売促進または営業企画のスタッフ 】
【 目的=年間キャンペーン企画立案のための会議資料 】 まず何について書くかを明確にします。ここでは「記念日ビジネスの実態」となるでしょう。 これがひとまずタイトルになります。 そして情報収集ですが、まずはインターネット検索が一般的でしょう。 「記念日」と打ち込んでグーグル検索すると、トップに「一般社団法人日本記念日協会(https://www.kinenbi.gr.jp/)」が登場しました。検索結果ページには、日本記念日協会に続いて、ウィキペディアの「記念日」「日本の記念日一覧」があります。これらをざっと読んでみると、日本記念日協会は企業や団体などからの記念日申請を認定登録していることが分かりました。 また、暦や二十四節気について調べると、土用や大寒などの季節に根ざした行事があり、勤労感謝の日といった歴史や伝統に根ざしている〝記念日〟があることもわかりました。 ただ、これではネット検索しただけの、誰もが知っている文章になってしまいます。ここで思いを巡らし、想定読者の関心や興味があることに引き付けてリサーチを進めましょう。 例えば「ショートケーキの日」なんてあるのかな、と思ったとします。日本記念日協会のサイト内の検索機能を使ったところ、協会での登録はありません。こうなればしめたもの。グーグルで「ショートケーキの日」を検索すると、簡単に出てきました。カレンダーをみると、15(いちご)が上に載っている毎月22日がショートケーキの日だ、と。銀座コージーコーナーなどの洋菓子店が、ショートケーキの日をプロモーションに使っていることも検索結果ページからうかがえました。 次いで、追加情報を得るため、同じような面白い記念日はないか、自分の興味ある食べ物などの記念日はないか、ちょっと検索してみましょう。なんと「かき揚げの日」や「ロールケーキの日」などがヒット。記念日は企業や関係団体のプロモーションやPRで使われることが多いことが分かりました。 設問では、「記念日ビジネスの実態を紹介してください」とあります。以前、バレンタインデーはメリーチョコレートという会社がはやらせたのだと聞いたことも思い出し、「記念日ビジネスは花盛り」というファクトを盛り込んでいくことにします。 次のステップとして、集めた情報を箇条書きにしてみます。
・一般社団法人日本記念日協会
・協会の趣意に「記念日により日々の生活に潤いが生まれ、歴史が刻まれ、産業が盛
んになり、社会的に大切な情報が多くの人に届く」とコメントあり
・二十四節気、暦、伝統行事
・ショートケーキの日は、カレンダーの日並びから設定された
・銀座コージーコーナーなどがPRとして活用
・同様の事例として「かき揚げの日」や「ロールケーキの日」
・ポッキー&プリッツの日(11月11日)
・バレンタインデーが走り? 練習問題ではタイトル(見出し)は求められていませんが、ここであえてつけるとしたらどうでしょうか。 メモ書きしたキーワードを眺めた結果、「記念日ブーム、企業のPR活用が拍車」「記念日ブーム、今や2100超──語呂合わせや変わり種も」といった見出しをイメージしてみました。タイトルが決まると、箇条書きのキーワードにヌケやモレがあること、つまり、もっとほかに欲しい情報があることが見えてきます。 ちなみに、最初のメモ書きでは日本記念日協会の認定登録数が抜けていました。記念日ブームを裏付ける数字を、ということで、協会のサイトから「2020年3月末現在で2100を超える記念日が認定登録されて」いるという情報を追加しました。このデータがなければ、「画竜点睛を欠く」ことになってしまいます。 さて、いよいよタイトルを意識しながら、メモ書き情報を肉付けして文章を構成していきます。以前触れた基本のPREP法で書くことにします。 第一段落(P)で、記念日ブームの一般的な情報を紹介しつつ、企業などの民間がビジネスに活用している背景に触れます。 それを「世の中、記念日ばやり」の一言で表現し、第二段落以降でその実態を肉付けしていきます。理由(R)として、一般社団法人の日本記念日協会に登録されている記念日が2100件以上にのぼることを紹介。続いて具体的な事例(E)を持ってくることにします。記念日ビジネスの走りと言われるバレンタインデーを持ち出し、ビジネス活用の歴史は案外古いことを指摘しようと思います。 その上で、「意外な」記念日である「ショートケーキの日」を取り上げて、話を転じる工夫をします。同様な事例として「かき揚げの日」を紹介し、関連として「めんの日」「ポッキー&プリッツの日」などへと話を広げることにしました。 最後に結論として、記念日協会のコメントを使い、記念日ビジネスのさらなる拡大を見通し、冒頭の「世の中、記念日ばやり」を補強することにします。 【回答例】
(タイトル)記念日ブーム、企業のPR活用が拍車 世の中、記念日ばやり。例えば11月は暦(二十四節気など)の上では立冬や文化の日、勤労感謝の日などがあるが、民間などが自主的に決めた記念日には「いい夫婦の日」(11月22日)や「ポッキー&プリッツの日」(11月11日)などがある。制定理由はさまざまだが、メーカーや小売り、業界団体などが需要拡大を狙って記念日を制定する例が増えている。 1991年設立の一般社団法人・日本記念日協会(長野県佐久市)は、企業や団体、個人の申請を受けて、記念日を認定・登録している。2020年3月末で2100件を超え、その数は増える一方だという。 日本では女性が男性にチョコレートを贈る日になっている2月14日の「バレンタインデー」。1958年にメリーチョコレートカムパニー(東京・大田)が伊勢丹新宿本店でキャンペーンを展開したことから広まった。もともとはローマ皇帝の迫害にあって西暦270年に殉教した聖ヴァレンティヌスに由来する。 「憲法記念日」や「ひな祭り」など、国や公的機関が制定した祝日や記念日は伝統や歴史に根ざしたものが多い。これまで民間が決める記念日は「語呂合わせ」が多く、いい夫婦の日もしかり。毎月の29日は「肉の日」というのがスーパーマーケットの特売や飲食店で定着している。 ちなみに、ショートケーキの日が何日なのかをご存じだろうか。 ヒントはカレンダーの日付の並びだ。 答えは毎月22日。理由は「イチゴ」が上にのっているから。1週間ごとに数字が並んでいるカレンダーをみると、毎月22日の上には必ず15日がくる。イチゴのケーキの定番と言えばショートケーキ。22日のケーキの上に1(イチ)5(ゴ)がのっているというわけだ。仙台の洋菓子店が発案したといわれる。 同じような理由で制定されたのが「かき揚げの日」。細い麺のように数字が並ぶ11月11日が「めんの日」であることから、カレンダーでは11月11日の上にくる11月4日が答えだ。うどんやそばにのせる代表的な具材であるかき揚げを、冷凍食品メーカー、味のちぬや(香川県三豊市)が取り上げた。 めんの日の11月11日は「ポッキー&プリッツの日」でもある。発売元の江崎グリコが棒状の形状から決めた。数字の形状から取られたものには「ロールケーキの日」(6月6日)もある。記念日は日々の暮らしに潤いを与えたり、思わぬ語呂合わせで人々を笑顔にさせたりする。話のネタやビジネスのヒントにもなる。日本記念日協会も「歴史が刻まれ、産業が盛んになり、社会的に大切な情報が多くの人に届く」と記念日の効用を説く。さて、これからどんな記念日が登場するのだろうか。 この練習問題は、一般社団法人日本記念日協会のサイトにアクセスし、ウィキペディアなどで調べれば概要は理解でき、書ける問題です。回答例では、二十四節気のような季節感のあるものや国民の祝日などとは違った、語呂合わせや少しひねった記念日が増えていることを紹介しました。読み手に「ヘーっ」と思わせる文章にするには、意外なものや定番のファクトを混ぜながら書くことです。納得感が高まります。
———————————————————————————
本連載は、CCCメディアハウス刊行の「即!ビジネスで使える 新聞記者式伝わる文章術」の内容を一部編集したものです。
CCCメディアハウス「即!ビジネスで使える 新聞記者式伝わる文章術」(白鳥和生著)
本連載は、CCCメディアハウス刊行の「即!ビジネスで使える 新聞記者式伝わる文章術」の内容を一部編集したものです。
CCCメディアハウス「即!ビジネスで使える 新聞記者式伝わる文章術」(白鳥和生著)
筆者プロフィール
白鳥和生
株式会社日本経済新聞社 編集 総合編集センター 調査グループ次長。
明治学院大学国際学部卒業後、1990年に日本経済新聞社に入社。編集局記者として小売り、卸・物流、外食、食品メーカー、流通政策の取材を担当した。「日経MJ」デスクを経て、2014年調査部次長、2021年から現職。著書(いずれも共著)に「ようこそ小売業の世界へ」(商業界)「2050年 超高齢社会のコミュニティ構想」(岩波書店)「流通と小売経営」(創成社)などがある。日本大学大学院総合社会情報研究科でCSRも研究し、2020年に博士(総合社会文化)の学位を取得。消費生活アドバイザー資格を持つほか、國學院大学経済学部非常勤講師(現代ビジネス、マーケティング)、日本フードサービス学会理事なども務める。