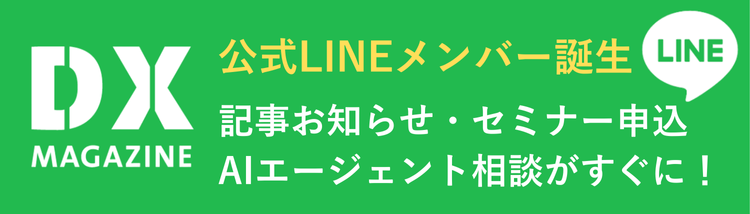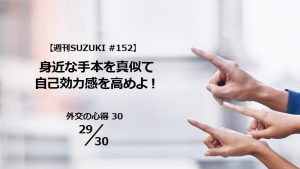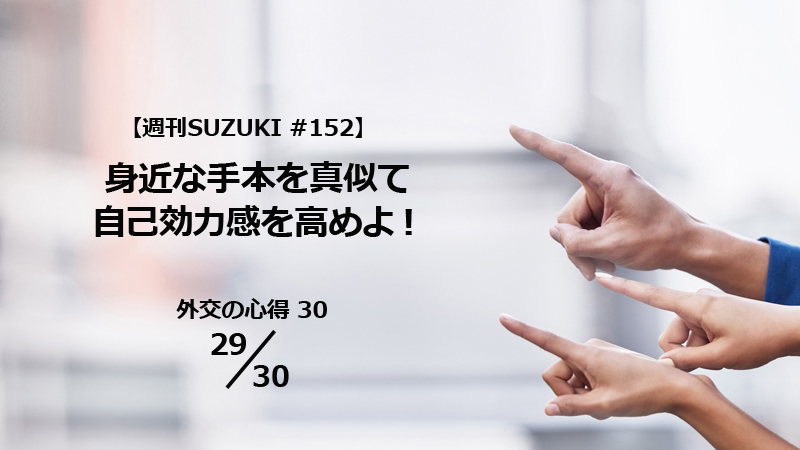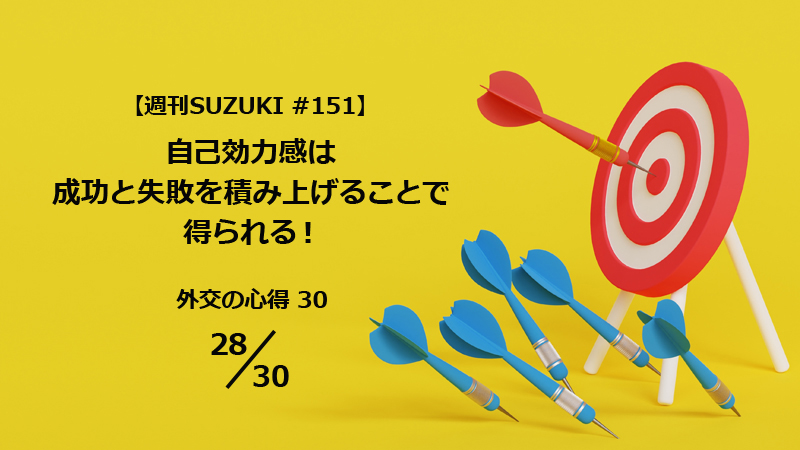Symmetry Dimensions Inc.は2022年12月21日、デジタルツインの業界カオスマップを公開しました。カテゴリ別に2022年の業界の構図を整理しています。複数のカテゴリをまたがったサービスを展開する企業もあります。
デジタルツインは、物理空間に存在する場所や事象を、IoTデバイスなどを用いてデータ化し、デジタル空間上に再現することで分析・予測などに役立てる技術。日本でもIoTや5Gなどのテクノロジ進化とともに、工場施設内や生産ラインを可視化する動きが起きつつあります。
カオスマップを公開したSymmetry Dimensions Inc.によると、デジタルツイン業界の主な動きは次の3つです。
・ヘルスケア領域の発達、拡大するデジタルツイン活用領域
・スマートシティ実現に向けた都市のデジタルツイン構築の活発化
・社会実装フェーズへ進むデジタルツイン ヘルスケア領域の発達、拡大するデジタルツイン活用領域
世界中でデジタルツイン関連のコンソーシアムやコミュニティが立ち上がり、各国で進むデジタルツイン技術を用いた実証実験、サービス活用の知見が共有されつつあります。デジタルツインはこれまで、製造業や建設業を中心に活用が見込まれていましたが、ヘルスケア領域などの分野での活用を見込む企業も増えつつあります。 第5世代移動通信システム(5G)の普及、さらには5Gに比べて100倍高速な第6世代移動通信システム(6G)の登場を控え、データのリアルタイム性は一層高まります。これにより、広範囲、高精度なデータに基づくデジタルツイン環境の構築が可能になります。幅広い業界でデジタルツイン技術も活用が見込まれます。 スマートシティ実現に向けた都市のデジタルツイン構築の活発化
日本は2022年6月、「デジタル田園都市国家構想」が閣議決定しました。イギリスでは「Digital Twin Hub(National Digital Twin Program)」、シンガポールでは「Smart Nation Singapore」といったように、スマートシティ実現に向けた官民連携の取り組みが世界で活発化しています。こうした背景から、スマートシティを実現する技術インフラとしてデジタルツインに注目が集まります。 国内では国土交通省が推進する「Project PLATEAU」、海外では韓国ソウル市の「S-MAP」、EUの「DUET」 など、都市のさまざまなデータ可視化を可能にする3D Webビューワーの整備が加速しています。都市課題の可視化、解決方法検討にデジタルツインが一役買っています。 都市のデジタルツインは実用化が進む社会実装へ
デジタルツイン構築のため、世界の都市情報をデータ化、収集、整備する「デジタライズ」が進んでいます。さらに、収集データの活用方法や応用方法を模索する「ビジュアライズ」の取り組みも活発化しています。 今後は世界中でデジタルツイン技術を用いたユースケース実証が進みます。デジタルツインの理解が深まることで、具体的な社会課題解決を試みる「社会実装」フェーズに移行することが見込まれます。 「社会実装」のフェーズでは課題ごとのサービス化・アプリケーション化が進みます。このとき、デジタルツインを使って検出した課題やシミュレーション結果を、よりシームレスにユーザーが受け取れるようになり、業務での活用が促進されます。 一見デジタルツインが使われていないサービスやアプリにも、バックエンドでデジタルツインの導入・活用が進むでしょう。多くのエンドユーザーが知らぬところでデジタルツインが使われる環境が整い始めます。生活を支えるインフラとしてデジタルツインが使われるようになります。 Symmetry Dimensions Inc.は今後も継続的に業界リサーチを続け、カオスマップを更新していきます。デジタルツインの活用領域、トレンドを明確にしていく考えです。
・スマートシティ実現に向けた都市のデジタルツイン構築の活発化
・社会実装フェーズへ進むデジタルツイン ヘルスケア領域の発達、拡大するデジタルツイン活用領域
世界中でデジタルツイン関連のコンソーシアムやコミュニティが立ち上がり、各国で進むデジタルツイン技術を用いた実証実験、サービス活用の知見が共有されつつあります。デジタルツインはこれまで、製造業や建設業を中心に活用が見込まれていましたが、ヘルスケア領域などの分野での活用を見込む企業も増えつつあります。 第5世代移動通信システム(5G)の普及、さらには5Gに比べて100倍高速な第6世代移動通信システム(6G)の登場を控え、データのリアルタイム性は一層高まります。これにより、広範囲、高精度なデータに基づくデジタルツイン環境の構築が可能になります。幅広い業界でデジタルツイン技術も活用が見込まれます。 スマートシティ実現に向けた都市のデジタルツイン構築の活発化
日本は2022年6月、「デジタル田園都市国家構想」が閣議決定しました。イギリスでは「Digital Twin Hub(National Digital Twin Program)」、シンガポールでは「Smart Nation Singapore」といったように、スマートシティ実現に向けた官民連携の取り組みが世界で活発化しています。こうした背景から、スマートシティを実現する技術インフラとしてデジタルツインに注目が集まります。 国内では国土交通省が推進する「Project PLATEAU」、海外では韓国ソウル市の「S-MAP」、EUの「DUET」 など、都市のさまざまなデータ可視化を可能にする3D Webビューワーの整備が加速しています。都市課題の可視化、解決方法検討にデジタルツインが一役買っています。 都市のデジタルツインは実用化が進む社会実装へ
デジタルツイン構築のため、世界の都市情報をデータ化、収集、整備する「デジタライズ」が進んでいます。さらに、収集データの活用方法や応用方法を模索する「ビジュアライズ」の取り組みも活発化しています。 今後は世界中でデジタルツイン技術を用いたユースケース実証が進みます。デジタルツインの理解が深まることで、具体的な社会課題解決を試みる「社会実装」フェーズに移行することが見込まれます。 「社会実装」のフェーズでは課題ごとのサービス化・アプリケーション化が進みます。このとき、デジタルツインを使って検出した課題やシミュレーション結果を、よりシームレスにユーザーが受け取れるようになり、業務での活用が促進されます。 一見デジタルツインが使われていないサービスやアプリにも、バックエンドでデジタルツインの導入・活用が進むでしょう。多くのエンドユーザーが知らぬところでデジタルツインが使われる環境が整い始めます。生活を支えるインフラとしてデジタルツインが使われるようになります。 Symmetry Dimensions Inc.は今後も継続的に業界リサーチを続け、カオスマップを更新していきます。デジタルツインの活用領域、トレンドを明確にしていく考えです。
あわせて読みたい編集部オススメ記事
世界の7割がデジタルツインを活用、59%の日本は10カ国中9番目の低さ/アルテアエンジニアリング調べ – DXマガジン

アルテアエンジニアリングは2022年11月22日、デジタルツインに関する調査結果を発表しました。日本のほか、米国や中国、英国、韓国など10カ国の技術者など2007人に聞いた結果です。デジタルツインの国別の活用状況、重要度などを聞いています。
デジタルツイン – DXマガジン

デジタルツイン(DigitalTwin)は、IoTなどで収集したデータを活用し、現実世界にあるモノや空間を仮想世界上に再現する技術です。 IoTで収集した実データに基づいたシミュレーションを実施できるのが特徴です。例えば生産機器を仮想世界上に再現した場合、IoTを使って機器の稼働時間や負荷、部品の摩耗具合などを収集し、それらデータから故障する時期を予測することができます。稼働時間をあと何時間増やせば、故障時期がどれだけ早まるのかなどをシミュレーションできます。実際の生産機器を使ってシミュレーションする必要がないため、生産ラインに影響を与えない、実データに基づく高精度な予測が可能などのメリットがあります。生産ライン全体を仮想世界上に再現すれば、より緻密な生産計画の立案や、製造機器の買い替え時期の予測も可能です。5GやVRと組み合わせれば、仮想世界上で実施したシミュレーション結果を、製造現場でほぼリアルタイムに確認できるようになります。 なお、海外では都市全体を仮想世界上に再現し、交通渋滞の予測や災害時の被害状況把握などに役立てる動きもあります。