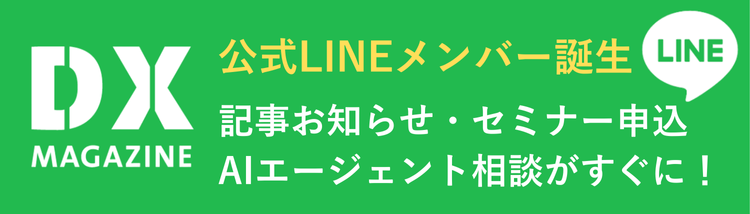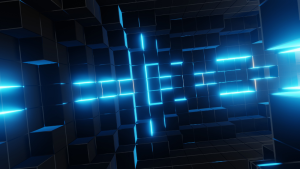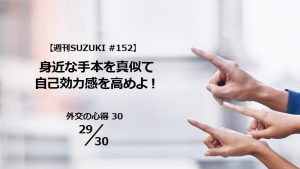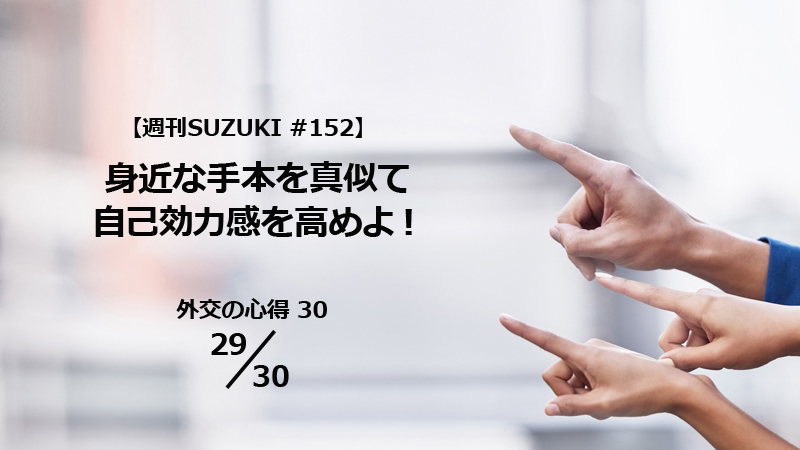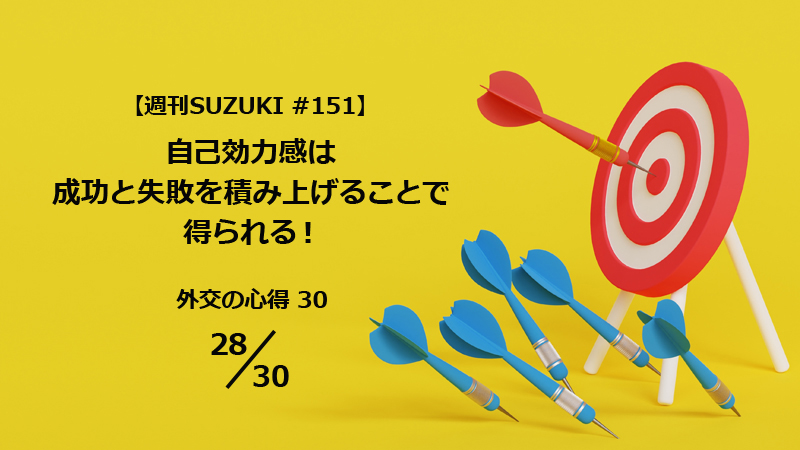日本オムニチャネル協会は2025年2月28日、年次カンファレンス「オムニチャネルDay」を開催しました。ここではクラシコム 代表取締役社長 青木耕平氏と、モデレータの日本オムニチャネル協会 渡部弘毅氏が登壇したセッションの様子を紹介します。「D2Cの本質を探る!!エンゲージメントファーストを実現する『北欧、暮らしの道具店』の過去、現在、未来」というテーマで、クラシコムの事業を例にD2Cビジネスを考察しました。
D2Cで何を成し遂げるのかの本質を見失わないことが重要
D2Cブランドの先駆けとして注目を集める「北欧、暮らしの道具店」。運営企業であるクラシコム 代表取締役 青木耕平氏は講演で、単なる成功事例の紹介にとどまらず、D2Cビジネスモデルの本質を深く掘り下げました。青木氏は、「なぜクラシコムがD2Cという形で事業を行っているのか」という問いに対し、徹底的に突き詰めた哲学とそこから導き出された実践の積み重ねの必要性を終始訴求しました。
青木氏はD2Cの本質について、「D2Cとは単なる販売手法やトレンドではない。“ブランドの夢”を叶えるための構造であるとも言える。ブランドが本来やりたかったはずの理想形、つまり製品、価格、販路、プロモーションのすべてを自らの意思で決め、お客様に最良の体験を届けること。それを可能にするのがD2Cだ」と述べました。D2Cを単なる直販モデルではなく、理想を形にするための構造的なアプローチとして捉えていることの重要性を聴衆に訴えました。
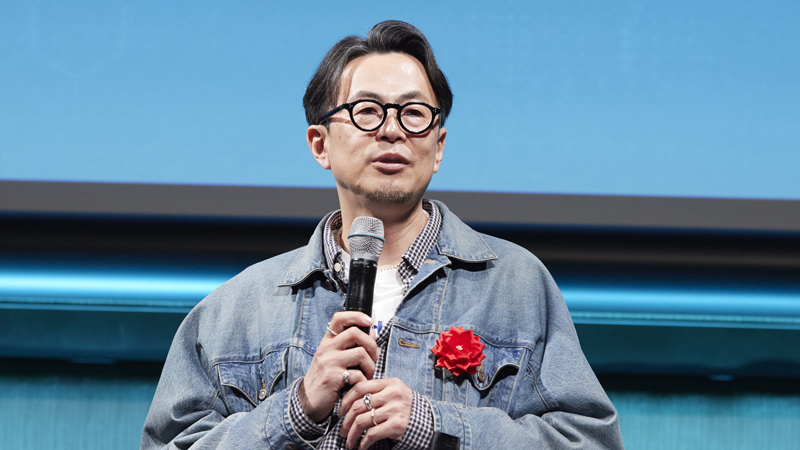
D2Cのヒントを得たきっかけにも言及しました。それが、渋谷PARCOでの体験です。青木氏は、多くのショップが閑散とする中、唯一大行列ができていたポケモンセンターの印象が強く残っているといいます。この体験をもとに、D2Cの構造を「観光地の温泉」に例えて解説。「ポケモンというブランドは、アニメやゲームといった“温泉”で世界観に没入する体験を提供する。さらに、そこから派生するグッズという“お土産”でマネタイズしている。つまり、まず魅力的な世界観を構築し、人が集まる体験を生み出した上で、その延長線上に物販があるという構造だ」と青木氏は考察します。
この「温泉とお土産」という構造こそ、クラシコムのビジネスに当てはまります。YouTubeチャンネルで配信している動画や、アプリで提供される読み物コンテンツ、丁寧に作られた写真やストーリーなどは、すべてが「温泉」の役割を果たします。ブランドの世界観に触れた人が自然とファンになり、最後に商品を「お土産」として手に取るという流れを構築しているのです。
モデレータの渡部氏もこの比喩に強く共感。「通常のD2Cは“お土産”を売ることから始めてしまう。しかしクラシコムは“温泉”を掘ることから始めている。これこそが本質的に異なる点だ。クラシコムの事業の成功を支えている」と語りました。
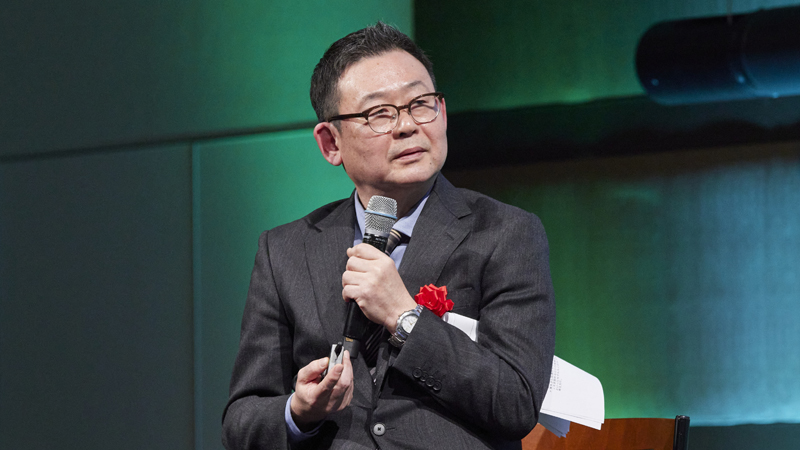
このようなブランド体験の重視は、経営の指標管理の考え方にも現れています。一般的なEC企業が重視しがちなKPIやコンバージョン率などの数値目標について、クラシコムはノルマを設けません。青木氏は「KPIをモニタリングするが目指さない、というのが当社の考え方だ。数字の変化から学ぶことは多く、すべての業務の始まりは記録=レコーディングであると考える。しかし、ノルマ化すると過剰に販促するなど、本質から逸れた行動が生まれやすい」と指摘します。
では、社員が何をもって行動の判断軸としているのか。それは「より良い店をつくる」という共通の目的意識です。クラシコムでは、業務を「研究・開発・企画・業務」の4層に分け、スタッフがそのすべてを自分ごととして捉えられるよう、仕事の構造を設計しているといいます。「水平的な多能効果ではなく、垂直的な多能効果を重視している。つまり、SNS担当、商品開発担当など縦割りの分業ではなく、全員が自分の仕事を深く理解し、責任を持って実装まで関わることが重要である」と青木氏は強調します。
その結果として、売上が急成長しても、社員数を過剰に増やす必要がなく、現在の体制でも安定的な経営が可能となっているのです。

では、D2Cが「スケールしにくい」と言われる中、クラシコムはどのように成長を描いているのでしょうか。青木氏は、成長の鍵を「供給面の拡張」と「需要創造の継続的な発明」にあると指摘します。
「私たちは“カテゴリーの花束戦略”を取っている。ジャンルが異なる商品群を、一貫した世界観でまとめ上げることで、統一感のあるブランド体験を提供している。これは顧客が長く接点を持ち続けられる仕掛けであり、ビジネスとしての供給の幅を広げることにつながっている」
需要面では、SNSやデジタル広告の変化が早い現代において、過去の成功体験を惰性で繰り返しても成長は持続しないとし、「少なくとも3年に1度は、新しい“発明”が必要である」という認識のもと、常に新しい取り組みを模索しているとのことです。近年では、アプリのダウンロード広告に大規模投資を行い、これが極めて高い効率で成果を上げたことから、今後の成長の柱として位置付けられているそうです。
「今になってようやく分かったことだが、これまで地道に積み重ねてきた世界観の発信活動が、今の広告効率を大きく引き上げているのである。つまり、CM的な価値を自らのメディアで蓄積していたということだ」と青木氏は語ります。
クラシコムのように、ビジネスの構造自体に「体験の設計思想」を織り込むことは、D2Cが“売ること”から“繋がること”へと価値を変える時代において、非常に重要な示唆を与えてくれます。青木氏の話を通して見えてきたのは、D2Cとは手段ではなく、哲学であるということ。そして、理想を追いながらも地に足のついた実装力を持つことが、その哲学を現実のものにする鍵であるということでした。
関連リンク
日本オムニチャネル協会