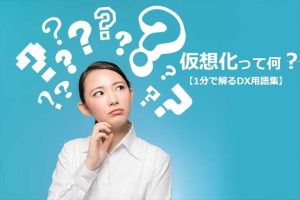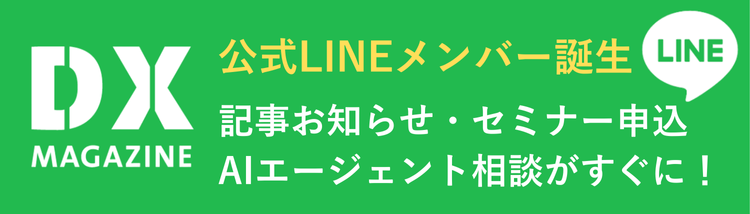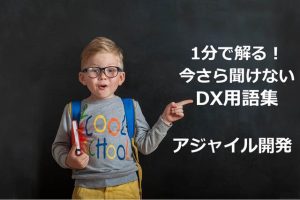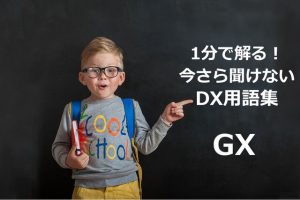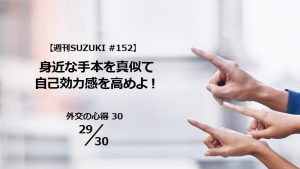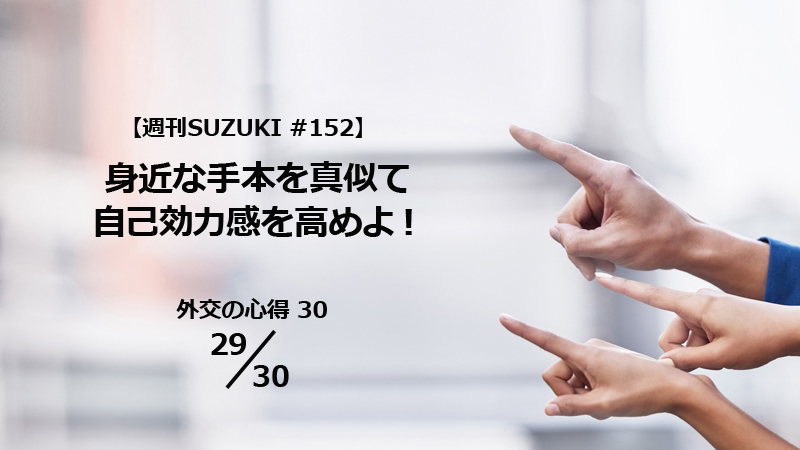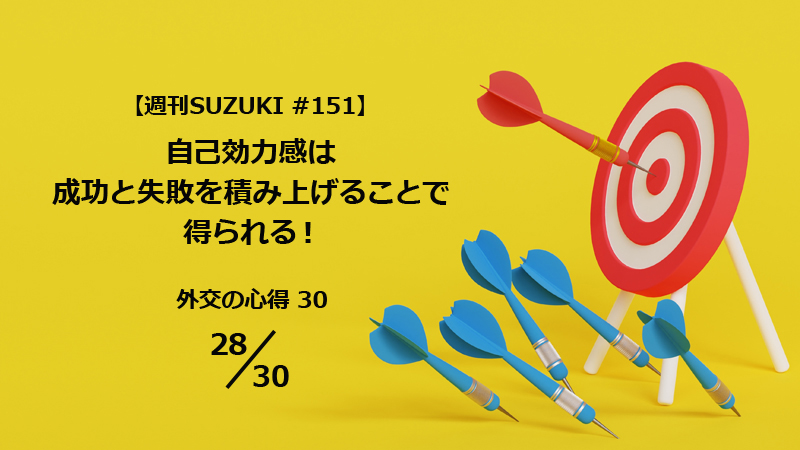仮想化とは、CPUやメモリ、ストレージといったサーバーのハードウエアリソースを抽象化する考え方、技術を指します。物理的なハードウエアリソースを抽象化することで、ソフトウエアで制御、運用できるようにします。 例えば100GBの容量を持つストレージがあったとします。これを仮想化すると、10GBの容量を持つストレージを10台用意したり、20GBのストレージを3台、10GBのストレージを4台用意したりといったように、物理的には分割不可能なストレージを柔軟に分割、運用できるようになります。容量の無駄を省いたり、リソースを有効活用したりできるのがメリットです。 CPUやメモリといったリソースも仮想化により、必要なリソースで仮想サーバーを構築できるようになります。仮想化技術を活用することで、サーバーを集約して導入コストを抑えられる、古いOS上でしか稼働しないシステムを仮想環境上で運用し続けられるなどのメリットを見込めます。 仮想化するには、専用の仮想化ソフトウエアを使うのが一般的です。サーバーのほか、ネットワークやデスクトップ(PC)を仮想化する技術、サービスもあります。
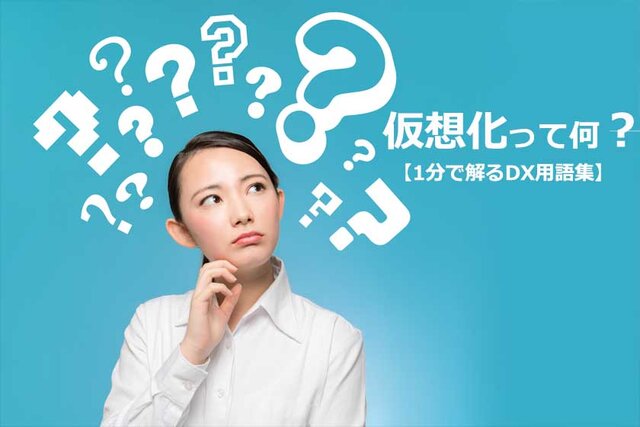
仮想化とは、CPUやメモリ、ストレージといったサーバーのハードウエアリソースを抽象化する考え方、技術を指します。物理的なハードウエアリソースを抽象化することで、ソフトウエアで制御、運用、管理できるようにします。
例えば100GBの容量を持つストレージがあったとします。これを仮想化すると、10GBの容量を持つストレージを10台用意したり、20GBのストレージを3台、10GBのストレージを4台用意したりといったように、物理的には分割不可能なストレージを柔軟に分割、運用できるようになります。容量の無駄を省いたり、リソースを有効活用したりできるのがメリットです。なお、100GBのストレージを10台用意し、1TBの1台のストレージに見たてることもできます。物理的な容量を上回るストレージを仮想的に作成するといったことも可能です。
CPUやメモリといったリソースも仮想化により、必要なリソースで仮想サーバーを構築できるようになります。仮想化技術を活用することで、サーバーを集約して導入コストを抑えられる、古いOS上でしか稼働しないシステムを仮想環境上で運用し続けられるなどのメリットを見込めます。
なお仮想化するには、専用の仮想化ソフトウエアを使うのが一般的です。サーバーリソースのほか、ネットワークやデスクトップ(PC)を仮想化する技術、サービスもあります。