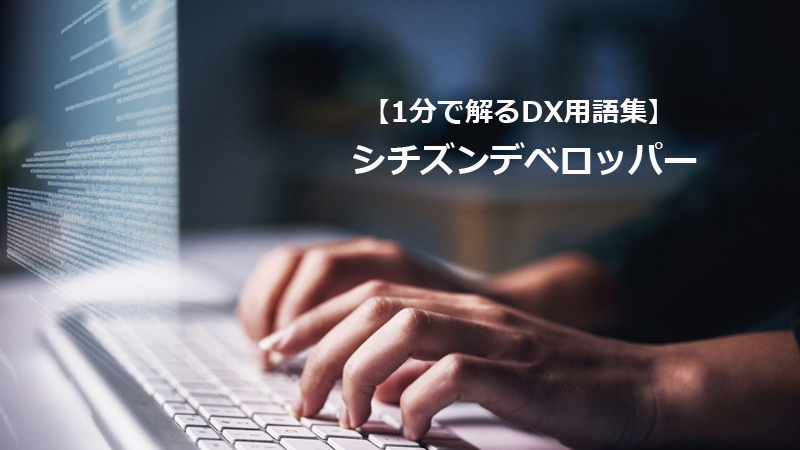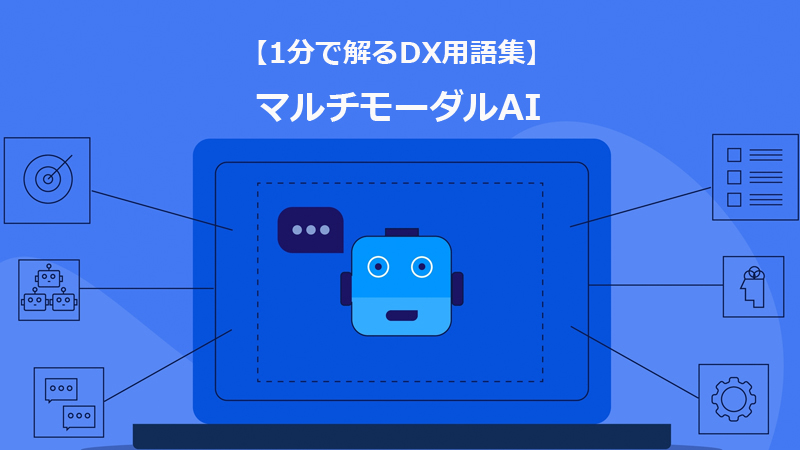競争社会では競合となる他社の動きが気になるもの。しかし、本当に気にすべきは、絶えず変化する顧客ニーズに他なりません。脇目も振らず自社を顧客にどう訴求すべきか。そのために必要な商品・サービスをどう拡充すべきか。ここでは、「セブン‐イレブン・ジャパン」を創設したセブン&アイ・ホールディングス名誉顧問の鈴木敏文氏の著書「鈴木敏文のCX(顧客体験)入門」の内容をもとに、異業種を含む競合との向き合い方について解説します。
競争を勝ち抜く土俵を築け
真の競争相手は絶えず変化する顧客ニーズである――。
これは、セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問の鈴木敏文氏が顧客起点を発想するときの考え方です。同業他社に目を向けるのではなく、常に顧客のニーズに目を向けることの必要性を訴えています。自社の商品が同業他社の商品より品質などで上回っていたとしても、顧客の満足を得られなければ単なる自己満足に過ぎないのです。もちろん、同業他社の商品を真似たり似せたりするのも、他社との差は縮まれども顧客は満足しません。
いかに顧客の支持を得るか。得られさえすれば、他社に対して競争優位に立つことができるといいます。
鈴木氏の著書「鈴木敏文のCX(顧客体験)入門」では、同様の考え方を持つ経営者の方々にも触れています。その一人がFrancfranc創業者である高島郁夫氏です。著書では高島氏が次のようなことを話していたと鈴木氏が述べています。
わたしは同業がどうかということはまったく考えませんでした。ですから、会社を設立してから十数年間、外部の(同業の)人とはほとんど会うことはありませんでした。自分たちの土俵をしっかりつくらないと、他社との激しい競争を勝ち抜くことができません。まず、自分たちの土俵をしっかりつくることに専念して、独自の正解を探求し続けました。そして、自分たちをお客様がどう判断してくださるか、それだけを見て、ビジネスに取り組みました。
鈴木氏も同様に、社員が他社の店舗を見に行くのを禁止したことがあったといいます。自分たちの「土俵」をつくり、顧客と1対1で向き合えることこそ重要なのです。
あるべき姿を目指す絶対価値を追求せよ
競争社会にいると、どうしても他社の動きが気になりがちです。「競合他社に勝つ」という思いも強くなってしまいます。
経営においては、競争相手との競争に勝つという「相対価値」を追求する経営と、自分たちの理想や信念を大切にするという「絶対価値」を追求する経営があります。競争社会では前者、つまり「相対価値」に目を奪われがちになってしまうのです。
しかし鈴木氏は、自社のあるべき姿をひたすら目指す「絶対価値」を追求すべきと述べています。このとき重要なのは、「そこそこいい」「まあまあいい」といった妥協を徹底的に排除すべきとも述べています。セブン-イレブンでは、提供する商品がレベルの低いままなら、即時に店頭から撤去、生産を中止させていた。それだけ妥協を取り除き続けていたのです。
売れているからいいのか。自分たちが納得できない味の商品が売れていることにこそ危機感をもつべきだ。セブン-イレブンのチャーハンはこの程度かと思われては、売れれば売れるほど信用が失われていくんだ
著書の中で鈴木氏は、「あるべき姿」を追求する姿勢を担当者に徹底させていたと述べています。たとえコストがかかり、効率が悪くても、お客様がおいしいと満足し、共感・共鳴するものをつくっていけば、結果は必ず出ると考えています。
異業種間競争下でも顧客に目を向けよ
そもそも「同業他社」という考え方自体、近年は無意味になりつつあります。他の業界の大企業が別業界へ新規参入するのが珍しくなくなった今、同業他社の動向を逐一追いかけても意味はありません。他業種も含め、異業種間の競争を前提としたビジネスを考えることが求められるようになっているのです。
こうした動きを紐解くと、セブン-イレブンこそ先立って異業種間競争を展開した典型と言えるでしょう。飲食店やレストランに行かず、コンビニ弁当を買う人が増えた、カフェに寄らずともコンビニで上質なコーヒーを買えるようになった…。これらはセブン-イレブンが飲食店などと異業種間競争を展開していると言えます。
では異業種間競争時代における価値をどう見出すべきか。鈴木氏は、消費者起点で新たな事業連鎖を考えることだと指摘します。消費者が商品やサービスを購入するまでの、アフターサービスを含む一連の過程で、さまざまな事業のつながりを模索するのです。企業内の閉じた活動によって価値を創出するのではなく、これまでの活動範囲や業界の境界を超え、消費者が満足する価値を模索すべきだというのです。
もっとも鈴木氏は、異業種間競争を勝ち抜くために商品群を拡充していったわけではありません。異業種の他社を意識したこともありません。あくまで「お客様の立場」で考え、お客様にとって利便性という価値を追求していったのです。
セブン-イレブンを始めるとき、小売業の専門家やマスコミからは「うまくいくはずない」と指摘され続けたそうです。店舗の大型化こそ成功モデルとも言われました。であるなら、お客様のニーズに徹底して向き合った商品やサービスをつくりしかないと考え、今日に至るまでオリジナル商品やサービスの開発に注力してきたのです。その結果が、異業種間競争を展開することになったに過ぎません。
お客様のニーズに応えるなら、既存の活動範囲や自社の業界を超えることもあります。大切なのはお客様を起点に、新たな事業連鎖を模索することです。
DXマガジン総編集長 鈴木康弘の提言「競合他店には行くな!」
鈴木敏文氏は、競合他社のお店には決して行きません。私が「なぜ競合のお店に行かないのですか」と尋ねると、「競合店に行っても意味がない。競合店より優れていてもお客様が買ってくださるわけではない」と明確な答えが返ってきました。なるほど、だから常に自社の店舗に行き、毎日商品を試食するのかと納得したことを思い出します。 DXも同様です。自らが生活の中にデジタルを取り込み、生活者の立場で考えることが一番大切です。ただ、より異業種を意識することが求められるようになっています。皆さんがお持ちのスマートフォンを考えてみると分かります。スマートフォンの画面上でさまざまななメッセージ、情報を知り、さまざまなな買い物をできるようになりました。異業種のサービスに影響を受けつつ、自社のサービスを同じスマートフォン上で使っているのです。 デジタル社会がますます進み、生活者から見て自社のサービスに価値はあるのか、異業種のサービスも活用する生活者の心理を考え続けていくことこそ真のCXと言えるのではないでしょうか。
本書のご購入はこちらから。
https://www.amazon.co.jp/dp/4833424495/
https://www.amazon.co.jp/dp/4833424495/
| information | |
|---|---|
| 書名 |
鈴木敏文のCX(顧客体験)入門 |
| 著者 | 鈴木敏文 取材・構成:勝見明 |
| 出版社 | プレジデント社 |
| 発売日 | 2022年5月31日 |
あわせて読みたい編集部オススメ記事
顧客起点を発想するなら「お客様のため」から「お客様の立場」への転換こそ重要【鈴木敏文のCX(顧客体験)入門 Vol.4】 –

顧客への体験価値提供がカギを握るCX経営では、顧客の視点を徹底して模索することが大切です。このとき注意すべきは、「お客様のため」という考えではなく「お客様の立場で」という発想の切り替えです。両者は何が違うのか。「お客様の立場」とはどんな視点を指すのか。ここでは、「セブン‐イレブン・ジャパン」を創設したセブン&アイ・ホールディングス名誉顧問の鈴木敏文氏の著書「鈴木敏文のCX(顧客体験)入門」の内容をもとに、「お客様の立場」が指すCX経営の本質を読み解きます。
常識にとらわれない商品づくり、消費者の五感に訴えるデザインも重要に【鈴木敏文のCX(顧客体験)入門 Vol.3】 –

年間の売上高が1.4兆円となるセブンプレミアム。これまでの概念を打ち破り、“CX型の商品”として価値を提供できるようにしたことが大ヒットを下支えしています。具体的にどんな戦略を打ち出したのか。ここでは、「セブン‐イレブン・ジャパン」を創設したセブン&アイ・ホールディングス名誉顧問の鈴木敏文氏の著書「鈴木敏文のCX(顧客体験)入門」の内容をもとに、セブンプレミアムの成功要因を探ります。


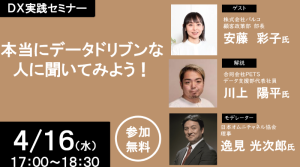
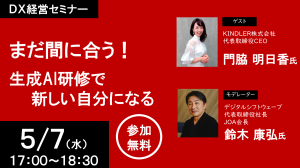

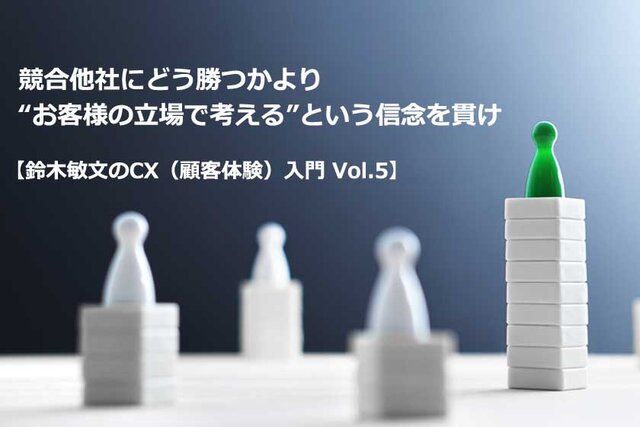






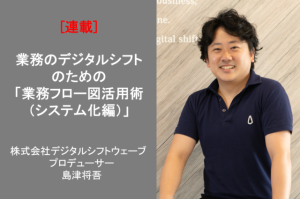






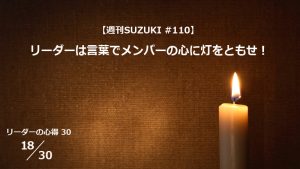
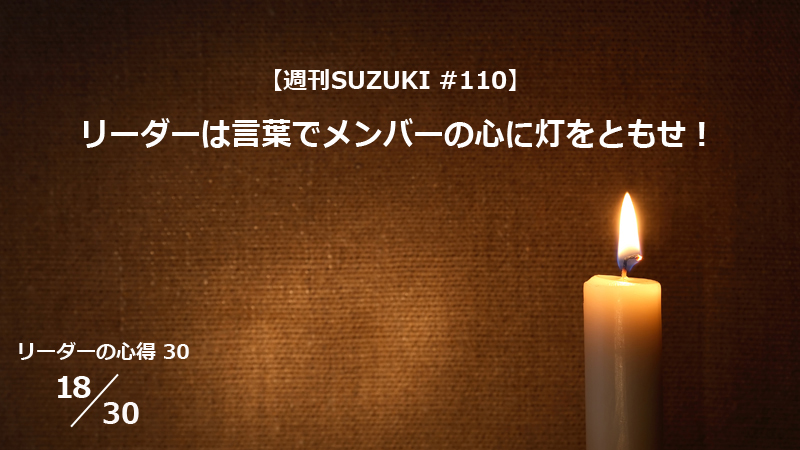
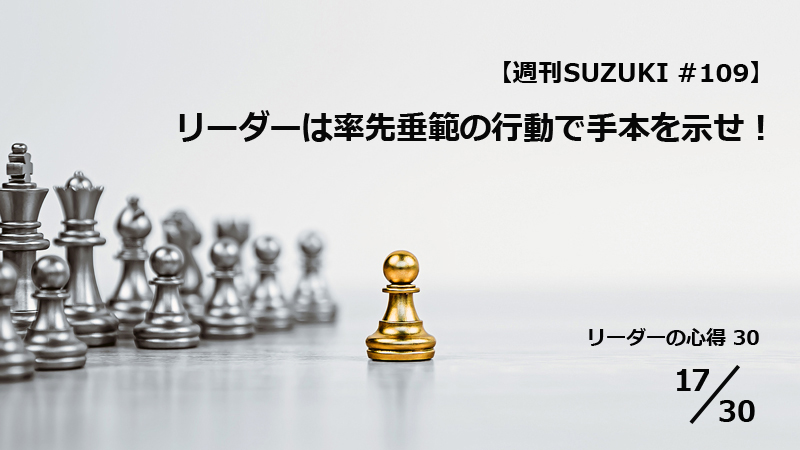

.png)