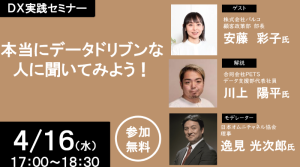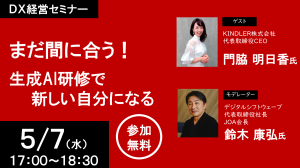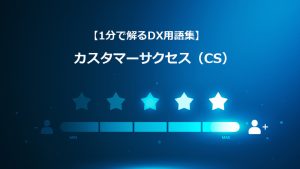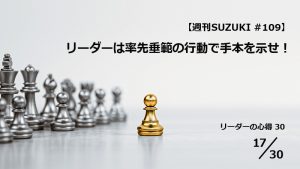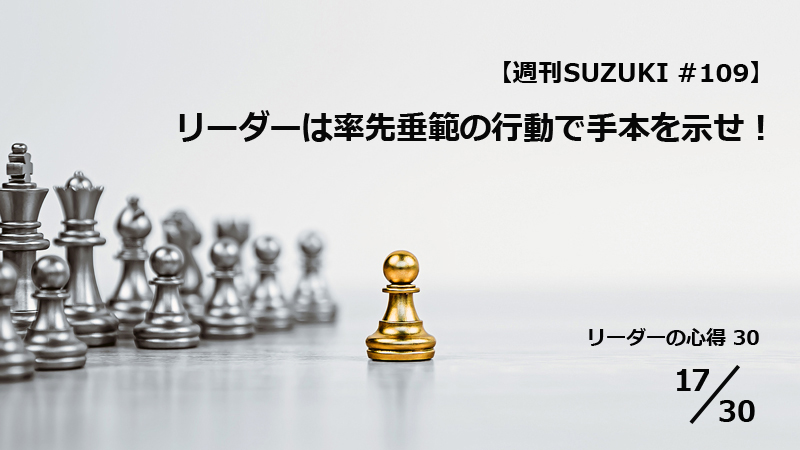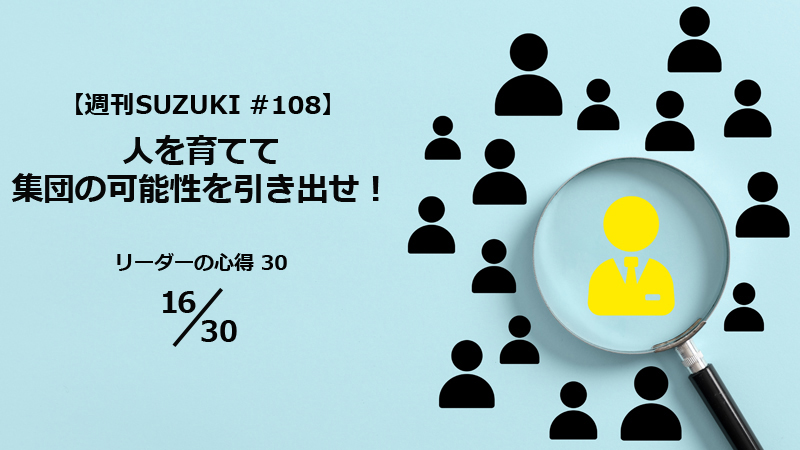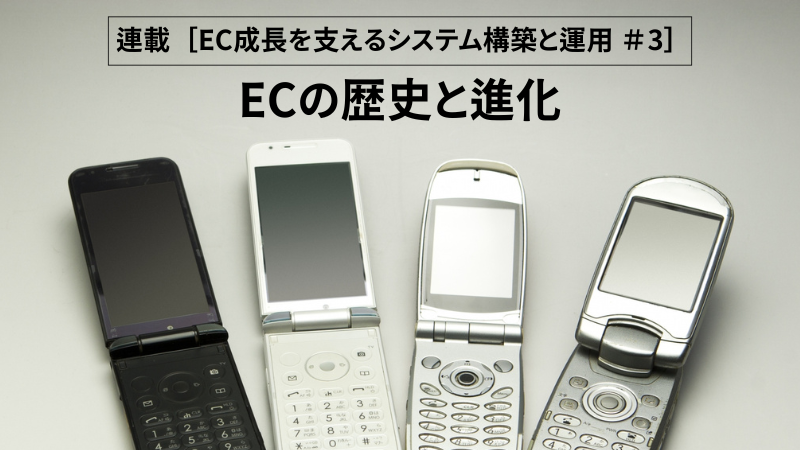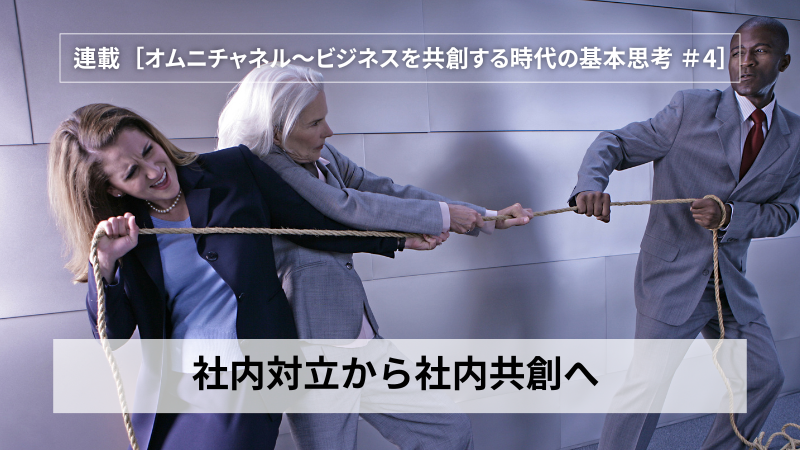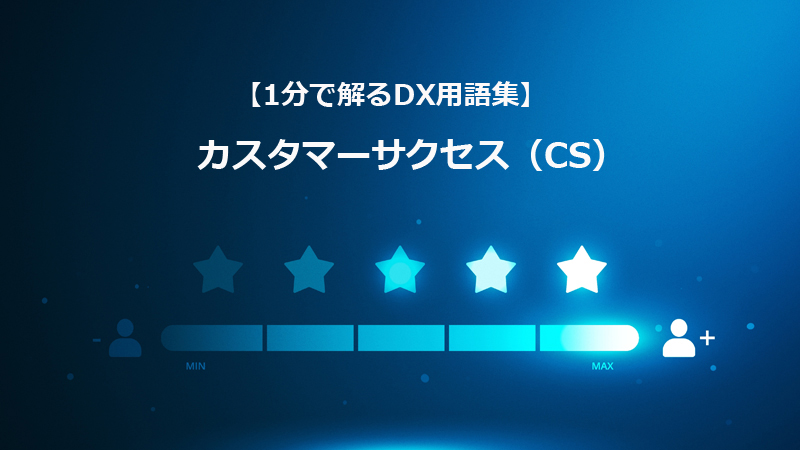日本オムニチャネル協会は2024年1月25日、定例のセミナーを開催しました。今回のテーマは「タイ・シンガポール視察報告会」。同協会が2023年10月に実施した「タイ・シンガポール視察ツアー」の内容をもとに、ツアー参加者が登壇して現地で感じたこと、体感したことを報告しました。
日本オムニチャネル協会は2023年10月、海外視察ツアーを実施。同協会による海外視察ツアーは2022年の米国視察に続いて2度目で、今回は10月13日から10月17日までタイとシンガポールを視察しました。
今回のセミナーでは、視察ツアーで印象に残ったことなどを報告しました。視察ツアーに参加したパルコ デジタル推進部 部長の安藤彩子氏と、コーポレイト ディレクション Managing Directorの占部伸一郎氏がゲストとして登壇。印象に残った商業施設や店舗を紹介しました。
成長著しいタイ・シンガポール
セミナーでは日本オムニチャネル協会 理事の逸見光次郎氏が、タイとシンガポールの現状を解説しました。タイの人口は6995万人、シンガポールの人口は545万人(ともに2021年時点)で、1人当たりGDPは、タイが日本の18.4%となる7233米ドル。これに対し、シンガポールが日本の185.3%となる7万2794米ドルになるといいます。「シンガポールの人口は600万人程度だが、一人当たりのGDPは日本の約1.8倍に相当する。金融業などの比重が高いが、経済的に強い国であるかが窺える」(逸見氏)と考察します。

タイの小売市場については、「小売の形態を分類すると、食品小売店は食品以外の日用品なども取り扱うハイパーマーケットと呼ぶ形態の比率が高い。さらに近年、健康や美容関連商品を扱う専門店、アパレル・靴専門店が成長している」(逸見氏)と分析。さらに全小売の売上に占めるECの割合は、JETROのデータによると2013年の1.1%から2018年には2.0%とほぼ倍増しているといいます。
一方のシンガポールは、「1900万人以上を呼び込む観光産業が依然として好調だ。さらに、スーパーアプリを手掛けるグラブやEコマースのラザダといったユニコーンを輩出したことも特筆すべきだ。日本との関係については、日系企業と地場スタートアップの協業が進んでいる。在シンガポール・日系企業でスタートアップと連携する企業は少なくない」(逸見氏)と指摘。タイ、シンガポールとも、日本と違って大きく成長し、市場としての魅力や国民の熱気が高いことを強調しました。
明確な戦略や店舗運営が魅力
では、視察ツアーに参加した人は何に注目したのか。続いて登壇したパルコ デジタル推進部 部長の安藤彩子氏は、バンコクのショッピング施設「ICONSIAM」を“イチオシ”として紹介します。
安藤氏は「ICONSIAM」の印象を、「ユニークな施設を開発するという目標達成に向けた戦略を忠実に実施している。とりわけ“勝つためのコラボレーション”という戦略を打ち出し、国内外の企業との連携に主軸を置いた施設運営に乗り出している。目標を実現するための戦略をまさに体現した施設だと感じた」(安藤氏)と、「ICONSIAM」を評価します。

さらに、フロアごとにさまざまなコンセプトを打ち出す点についても、「新しいアイデアを常に生み出し、世界中から人を呼び込むための開発に舵を切っている」(安藤氏)と、グローバルな視野を取り入れていることを評価。世界有数の商業施設開発を目指している点に同氏は感心していました。
では、ICONSIAMは具体的にどんな戦略を打ち出しているのか。安藤氏は、「優れたショッピング体験を生み出そうとするのは言うまでもない。世界レベルのイベント実施やタイの芸術を促進するといった役割を担い、タイのデベロッパーとしていかに競争力を高めるかを明確に実践している」(安藤氏)と考察しました。
同じく視察ツアーに参加したコーポレイト ディレクション Managing Directorの占部伸一郎氏は、シンガポールで化粧品などを取り扱う「SEPHORA」を“イチオシ”に挙げます。
占部氏はSEPHORAについて、「店舗のスタッフ全員がiPhoneと決済用端末を携行し、これらを使って決済できるようにしている。来店者はレジを探したりレジを待ったりする必要はない。スタッフはハンディプリンタを使ってレシートも渡せる徹底ぶりだ」(占部氏)と、販売スタッフのオペレーションに関心を示します。

さらにデータ活用も進んでいると占部氏は続けます。「会員システムに登録する購買履歴を端末で確認できる。店舗の購買履歴にとどまらず、オンラインの履歴もその場で確認できるようにしている。こうした仕組みを用意することで、販売スタッフは接客に費やす時間を十分確保できる」(占部氏)とメリットを分析します。加えて「SEPHORA」では、店舗在庫がない場合、他店舗の取り寄せや後日配送の手続きまで端末で手配できる点を評価していました。
タイのコールドチェーン物流市場に注視
物流領域に精通する日本オムニチャネル協会 SCM部会リーダーの小橋重信氏は、タイとシンガポールの物流事情を、これまでの歴史を交えながら紹介しました。

小橋氏はタイについて、「これまではバンコクを中心に物流網が整備されてきた。その後、ASEANの形成により、シンガポールやマレーシアといった近隣国との物流連携も深まった」(小橋氏)といいます。さらに近年は、タイ政府が経済特区の整備を開始。政府主導で経済発展を推進したことにより、「物流インフラのさらなる向上が期待されている。特にラヨーン県では港湾施設も整備し、国際的な物流拠点を構築すると同時に生産拠点としての役割も注目されている」(小橋氏)考察します。
シンガポールは1965年にマレーシアから独立したのを機に、経済の多角化と国際貿易を促進。急速な経済成長とともに国際的な物流ハブとしての地位を確立してきました。2010年代以降の物流事情について小橋氏は、「ASEANの一員として地域的な協力や経済統合を推進している。ASEAN地域内での円滑な物流が促進し、物流ハブとしての地位をさらに強固にしている」と分析しました。
なお小橋氏は、タイの「コールドチェーン物流」の市場を注視すべきと訴えます。コールドチェーン物流とは、生鮮食品などを低温のまま輸送する仕組みで、「タイでは成長軌道にあり、今後も成長が続くとみられる。タイのコールドチェーンビジネスはBtoBが主流で、食品や医薬品、コンビニ、レストランといった市場拡大とともに成長してきた。しかし新型コロナウイルス感染症によりロックダウン政策が実施されたことで、その後のコールドチェーンビジネスはBtoCビジネスへと変換し、新たな需要を創出している」(小橋氏)と分析しました。
関連リンク
日本オムニチャネル協会