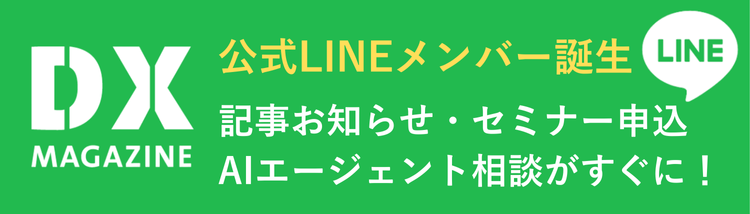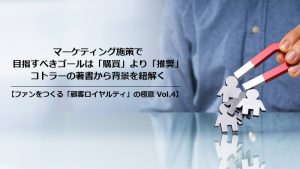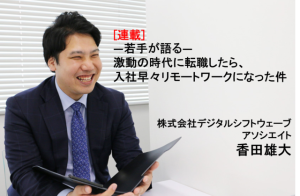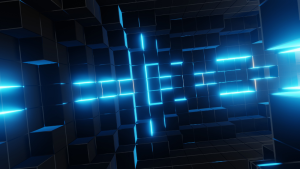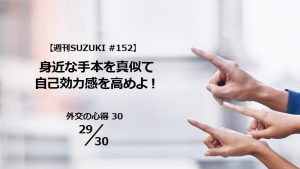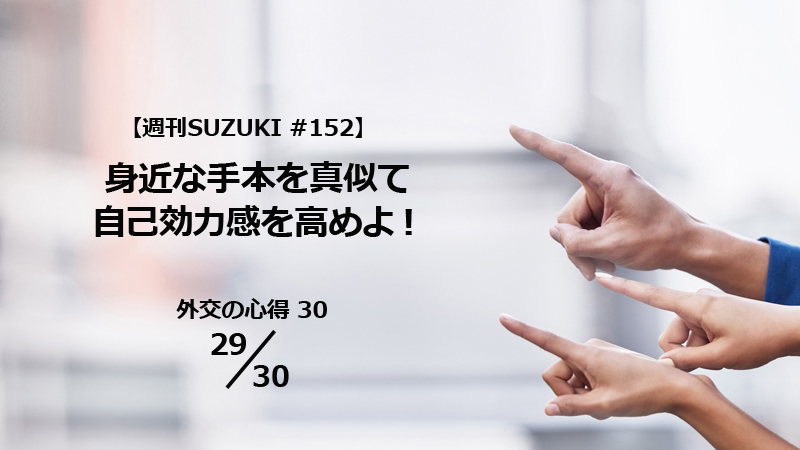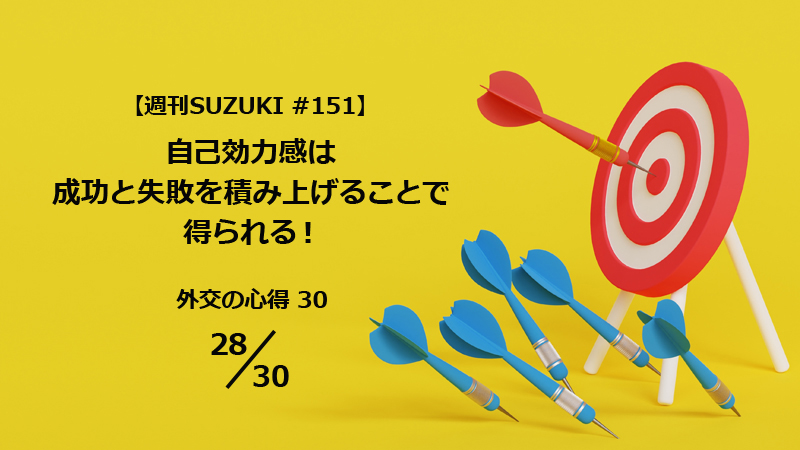はじめまして、ISラボの渡部です。本日から5回に分けてデジタルシフト時代においてマーケターが取り組むべきことに関して解説していきます。どうぞ宜しくお願い致します。
悶々とした日々
筆者は2000年から現在に至るまで、CRM(Customer Relationship Management)領域の業務コンサルタントをしています。CRMが対象とするプロセスは、マーケティング、セールス、サポートとなり、それらの業務改革支援をしています。
そんななか、数年前まで以下の自問自答を繰り返し、悶々とした日々を過ごしていました。 ・マーケティングって、所詮「売らんがな」のための方法論では?
・カスタマーサポート部門は重要部門にも関わらず、なかなか投資されな
い!
・カスタマージャーニー(マップ)という言葉がはやっているが、
広告代理店が広告の次のネタを売るためのバズワードでは? 当時のマーケティング書籍を読むと、顧客志向の考えが大きく取り上げられてはいましたが、自分の中ではなにか釈然としないものがありました。最新のマーケティングでは顧客主導、顧客のニーズに合わせたワン・ツー・ワンマーケティングを展開すべきだとしています。実際やっていることは、市場を洗脳して、買いそうな潜在顧客を効率よく見つけて、買いたくなるメッセージを拡散し、効率よく刈り取る、いわゆるプロダクトアウトのやり方から脱していないのではと感じていました。カスタマーサポート部門はその尻拭いをさせられている部門なのではと思っていました。しかし、企業の財務的目標を達成するためには、これが最適なやり方であろうと自分を納得させていました。
また、最近のマーケティングの重要キーワードである「カスタマージャーニー」の定義に対しても疑問を持っていました。以下にネットで調べたカスタマージャーニーあるいはカスタマージャーニーマップの定義のいくつかをあげてみました。
そんななか、数年前まで以下の自問自答を繰り返し、悶々とした日々を過ごしていました。 ・マーケティングって、所詮「売らんがな」のための方法論では?
・カスタマーサポート部門は重要部門にも関わらず、なかなか投資されな
い!
・カスタマージャーニー(マップ)という言葉がはやっているが、
広告代理店が広告の次のネタを売るためのバズワードでは? 当時のマーケティング書籍を読むと、顧客志向の考えが大きく取り上げられてはいましたが、自分の中ではなにか釈然としないものがありました。最新のマーケティングでは顧客主導、顧客のニーズに合わせたワン・ツー・ワンマーケティングを展開すべきだとしています。実際やっていることは、市場を洗脳して、買いそうな潜在顧客を効率よく見つけて、買いたくなるメッセージを拡散し、効率よく刈り取る、いわゆるプロダクトアウトのやり方から脱していないのではと感じていました。カスタマーサポート部門はその尻拭いをさせられている部門なのではと思っていました。しかし、企業の財務的目標を達成するためには、これが最適なやり方であろうと自分を納得させていました。
また、最近のマーケティングの重要キーワードである「カスタマージャーニー」の定義に対しても疑問を持っていました。以下にネットで調べたカスタマージャーニーあるいはカスタマージャーニーマップの定義のいくつかをあげてみました。

これらは一般的に使われているもので、おそらく読者もごく当たり前に感じられると思います。しかし、筆者はここに記載されているような定義や、セミナーでのカスタマージャーニーの説明内容に、次のような違和感をずっと持っていました。 ①プロセスについて、「購買するまで」と説明されているケースが多い
カスタマージャーニーの対象プロセスのゴールを「購買」に置いているが、購買した後のプロセスも対象にするべきでは。 ②購買動機の見える化や購買意欲を喚起する施策が重要視されている
カスタマージャーニーマップで見える化するお客様の行動や体験は、購買動機が中心になっている。また、立案される施策も、どんな情報をどの接 点で提供すれば購買に至るのかといった販促施策が中心。もっとお客様の 体験の実態を見える化し、顧客接点を改善する施策につなげる描き方をするべきでは。 セミナーにおいても特に広告代理店系の講演では、前述の疑問を感じざるを得ませんでした。購買意欲を喚起させるための情報発信やプロモーション施策につなげるためのカスタマージャーニーマップであり、デジタル技術を使ったMA(Marketing Automation) ツールを導入していくべきであるという結論には、大きな違和感を抱いていました。
カスタマージャーニーの対象プロセスのゴールを「購買」に置いているが、購買した後のプロセスも対象にするべきでは。 ②購買動機の見える化や購買意欲を喚起する施策が重要視されている
カスタマージャーニーマップで見える化するお客様の行動や体験は、購買動機が中心になっている。また、立案される施策も、どんな情報をどの接 点で提供すれば購買に至るのかといった販促施策が中心。もっとお客様の 体験の実態を見える化し、顧客接点を改善する施策につなげる描き方をするべきでは。 セミナーにおいても特に広告代理店系の講演では、前述の疑問を感じざるを得ませんでした。購買意欲を喚起させるための情報発信やプロモーション施策につなげるためのカスタマージャーニーマップであり、デジタル技術を使ったMA(Marketing Automation) ツールを導入していくべきであるという結論には、大きな違和感を抱いていました。
マーケティング4.0の到来
こうした悶々とした状態に光を差し入れてくれたのが、あの、マーケティングの神様、フィリップ・コトラーです。2010年に発売された『コトラーのマーケティング3.0』さらに、2017年夏に発表された『コトラーのマーケティング4.0』で、筆者の疑問は払拭されました。2冊の書籍からマーケティングの変遷を以下にまとめました。

マーケティングは1.0から4.0へと変遷し、なかでも2.0から3.0への進化で大きなパラダイムシフトがありました。
コトラーの言葉を借りると、2.0までは企業と顧客は縦の関係、すなわちハンターと獲物の関係です。すなわち、市場で買いそうな顧客をみつけ、投網をかけて狩猟をするスタイルです。筆者はこれを「狩猟型マーケティング」と名付けました。
一方、3.0以降は企業と顧客は横の関係、すなわち社会の共存共栄関係にならならなければいけないとコトラーは言っています。すなわち、企業と顧客は共創しともに成長していく関係です。筆者はこれを「農耕型マーケティング」と名付けました。
そして筆者のモヤモヤは、「農耕型マーケティング」へパラダイムシフトすることで解消できる問題であることが分かりました。
コトラーの言葉を借りると、2.0までは企業と顧客は縦の関係、すなわちハンターと獲物の関係です。すなわち、市場で買いそうな顧客をみつけ、投網をかけて狩猟をするスタイルです。筆者はこれを「狩猟型マーケティング」と名付けました。
一方、3.0以降は企業と顧客は横の関係、すなわち社会の共存共栄関係にならならなければいけないとコトラーは言っています。すなわち、企業と顧客は共創しともに成長していく関係です。筆者はこれを「農耕型マーケティング」と名付けました。
そして筆者のモヤモヤは、「農耕型マーケティング」へパラダイムシフトすることで解消できる問題であることが分かりました。
マーケティングのデジタルシフトとはデジタル技術を使った狩猟型マーケティングの実践ではない、社会・顧客のデジタルシフトに対応すること
そして、このパラダイムシフトのきっかけになった大きな要因が社会のデジタルシフトです。マーケティング3.0の発表当時は、インターネットの浸透に加えて、SNSが爆発的に拡大していた時代でもあります。役所や企業からのメッセージよりも、SNSを使った生活者からの情報や意見が社会に大きく影響を与える時代が到来したのです。アラブの春といわれた前例のない大規模な反政府デモにSNSが大きな役割を担ったことは、その象徴的な出来事でした。そして現在の4.0時代にはスマホ、高速ネットによる常時接続の時代になり、生活者どうしは常に距離に関係なく常に接続して情報共有できる時代が到来したのです。
こうなると、企業にとって都合の良い情報だけを発信する従来のマーケティング手法が無効化することは言うまでもありません。社会のデジタルシフト時代では生活者どうしは常につながって企業や商品に対する評判をつねにシェアしているのです。
しかし多くのマーケターは、マーケティング2.0から脱却できず、マーケティングのデジタル化とはデジタル技術を使った狩猟型のマーケティングを展開することだと思っています。自社が売りたい商品に関連するキーワードやホームページを閲覧した生活者をデジタル技術を駆使していち早く見つけ出し、湯水のように情報を発信しているのです。
マーケティングの真のデジタルシフトとは、社会や生活者のデジタルシフトに対してマーケティングを変革することなのです。そして狩猟型から農耕型に転換することです。 次回からは、この真のデジタルシフトに向けて具体的になにをするべきかを解説していきます。
こうなると、企業にとって都合の良い情報だけを発信する従来のマーケティング手法が無効化することは言うまでもありません。社会のデジタルシフト時代では生活者どうしは常につながって企業や商品に対する評判をつねにシェアしているのです。
しかし多くのマーケターは、マーケティング2.0から脱却できず、マーケティングのデジタル化とはデジタル技術を使った狩猟型のマーケティングを展開することだと思っています。自社が売りたい商品に関連するキーワードやホームページを閲覧した生活者をデジタル技術を駆使していち早く見つけ出し、湯水のように情報を発信しているのです。
マーケティングの真のデジタルシフトとは、社会や生活者のデジタルシフトに対してマーケティングを変革することなのです。そして狩猟型から農耕型に転換することです。 次回からは、この真のデジタルシフトに向けて具体的になにをするべきかを解説していきます。
渡部 弘毅 (わたなべ ひろき)
ISラボ 代表
1985年日本ユニシス入社、2000年日本IBM、2005年日本テレネットを経て、2012年にISラボ設立。一貫してCRM分野に関わり、プロダクトマーケティング、業務改革コンサルタント、事業企画を経験。現在はロイヤルティマネジメントのコンサルティング活動中。日本オムニチャネル協会、情報処理学会、コールセンタージャパン等、複数の研究会のリーダーを務め、定期的に数多くのセミナーの講師を担当している。
著書:『お客様の心をつかむ心理ロイヤルティマーケティング 「心の満足」と「頭の満足」を測り、科学的にロイヤルティを高める手法』
https://www.amazon.co.jp//dp/B083J3P3PD/