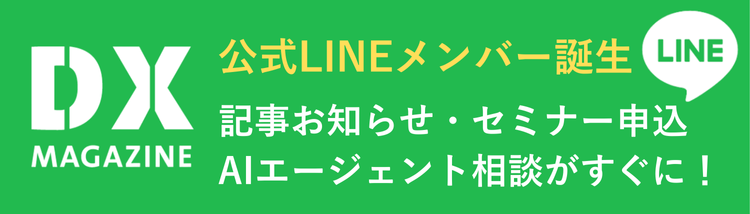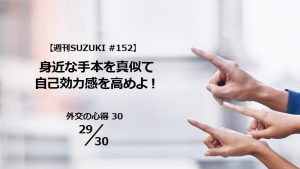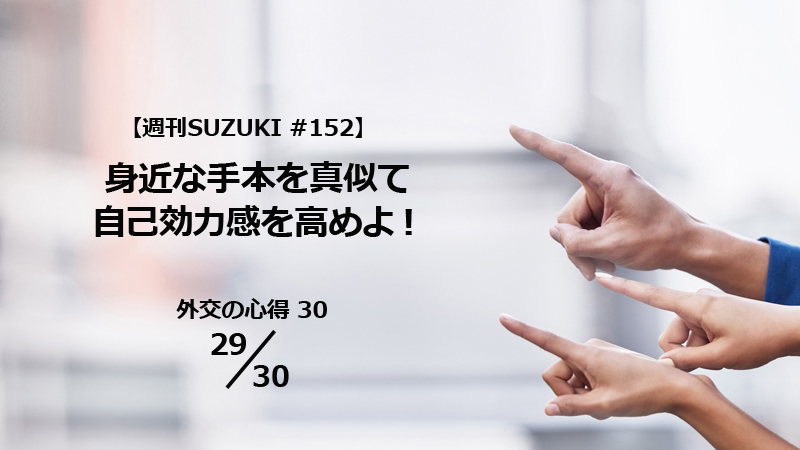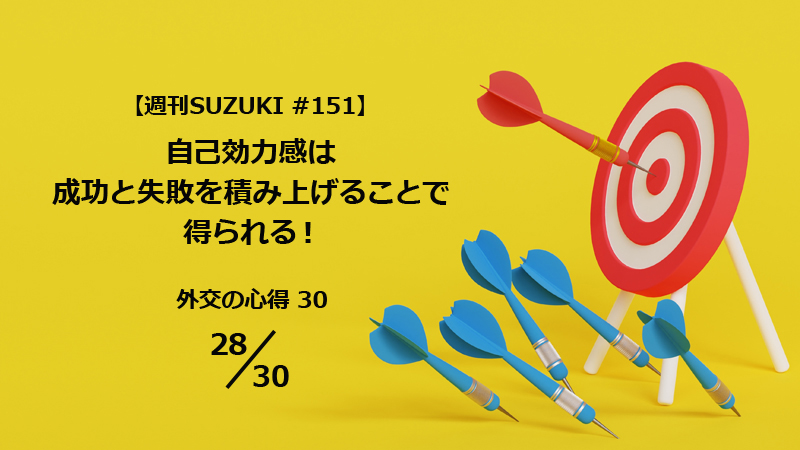オムニチャネルを推進するポイントの1つが、他部署との連携です。前回は、他部署の理解を深める「会議」のあるべき姿について触れました。会議を通して各部署の業務とそのつながりが可視化されると、「各部署内」ではなく、「部署間の業務のつながり」に課題あることが明らかになります。なぜ部署間の業務のつながりに課題が発生するのか。どのように改善すべきか、「業務のつながり」の重要性について考察します。【連載第6回:オムニチャネル~ビジネスを共創する時代の基本思考】
本当の課題は”つながり”!?
前回の記事では、オムニチャネル施策を成功に導く「会議」のあるべき姿について触れました。会議を通じて、他部署が「何を目標としているのか」「どのような課題を抱えているのか」を理解し、各部署の理解を深める重要な役割を果たしています。
では、各部署の目標数値や課題が明確になったら、次に何に注力すべきでしょうか。それは「業務のつながりの可視化」です。具体的には、業務フローを描くことで、自部署と他部署の業務のつながりを明らかにします。この際に忘れてはならないのが、顧客起点であることです。
実際に顧客起点で各部署の業務とそのつながりが見えてくると、ほとんどの課題は「各部署内」ではなく、「部署間の業務のつながり」にあることが明らかになります。自部署内の仕事に整合性を保ちながら一生懸命取り組んでいても、部署を出た瞬間に他部署との整合性が取れていないという事態が発生しているのです。
この原因として多く見受けられるのが「以前から変わらない業務のやり方」です。たとえ各部署が業務改善に取り組み、全社でシステムを導入して業務効率化を図っても、それに合わせた業務手順が変更されなければ、業務効率化は実現しません。さらに、自部署内では手順を変えたとしても、他部署とのつながりに関する業務部分については改善が不十分だったり、そもそも気づかれていないことが多く見受けられます。その結果、「部署間の業務のつながり」に課題が多発します。
したがって、「部署間の業務のつながり」における課題を可視化することで、本当の課題が見えてきます。つまり部署間を“つなぐ仕事”がオムニチャネル施策の要となるのです。
さらに、部署間の業務のつながりは、業務フローを共有することで誰にでもできるものです。若手であれば業務の素朴な疑問を具体的な業務フローの中で提起できますし、ベテランはこれまでの専門知識や経験を踏まえて意見を出すことができます。そして、各部署の中間管理職であれば、幅広い社内人脈と経験を活かして、こうした議論を部署を越えて振ったりまとめたりすることが可能ですし、さらに経営数値とつなげることで、社内の上下左右をつなぎ合わせることができ、現場から経営まで業務と数値で“つなぐ”ことが社内共創につながるのです。
よく引用するのが、ドラッカーの『マネジメント』に出てくるミドルマネジメントの定義です。
「伝統的なミドルは命令する人だった。これに対して新種のミドルは知識を供給する人である。伝統的なミドルは、下に向かって、すなわち自分に報告する人間に対して「権限」を持つ。新種のミドルは、上や横に向かって、すなわち自分が命令できない人間に対して「責任」を持つ。彼らは専門家である。彼らの決定と行動が、組織の方向と能力に直接影響を与える。」(『マネジメント – 課題、責任、実践』)
上意下達の組織ではオムニチャネル化はできず、生き残ることが難しい時代です。このように「上や横に向かって」ミドルマネジメントが働きかける改善活動ができる組織こそが、これからの時代の主役となるのです。そして結果的に、部署を越えたコミュニケーションが行われ、日々改善のためのディスカッションが行われる楽しい職場が生まれるでしょう。

逸見光次郎
CaTラボ 代表取締役
日本オムニチャネル協会 理事
1994年に三省堂書店に入社し、神田本店や成田空港店などで勤務。1999年にソフトバンクに移り、イーショッピングブックスの立ち上げ(現:セブンネットショッピング)。2006年にはアマゾンジャパンに入社し、ブックスのマーチャンダイザーを務める。2007年にイオンに入社し、ネットスーパー事業の立ち上げ後、デジタルビジネス事業戦略担当となる。2011年、キタムラに入社し、執行役員EC事業部長を経て、2017年にオムニチャネルコンサルタントとして独立。現在はプリズマティクスアドバイザーやデジタルシフトウェーブのスペシャリストパートナーなどを務める。
日本オムニチャネル協会
https://omniassociation.com/