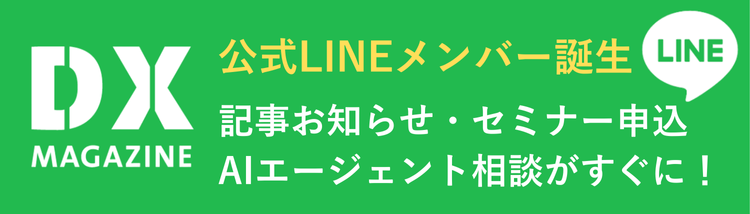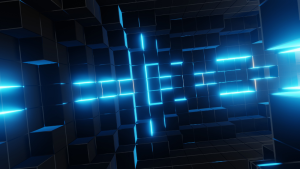プリズマティクスとクラスメソッド、デジタルシフトウェーブの3社は2021年11月9日、共催セミナーを開催しました。「小売業の向かう未来」というテーマのもと、デジタル化した消費者に対応するための取り組み事例を紹介しました。デジタル変革を推進する企業の経営者と実務責任者が登壇し、具体的な課題解決法やDX推進のポイントなどに触れました。ここではセミナーの内容を一部紹介します。
全従業員の理解と定着こそデジタル化の本質
第一部は「カインズのデジタル化戦略のストーリー」と題し、カインズ 執行役員 CDO 兼 CMO 兼 デジタル戦略本部長の池照直樹氏が登壇。プリズマティクス CEOの濱野幸介氏と対談しました。
カインズは関東を中心に225店舗(2021年2月末時点)のホームセンターを展開する企業。2019年には「PROJECT KINDNESS」と呼ぶ3カ年の中期経営計画を発表し、デジタル人材を多く採用するなどしてデジタル化へと大きく舵を切りつつあります。そんな同社がデジタルをどう推進しているのか。根付かせるために何を徹底しているのか。デジタル戦略を主導する池照氏がカインズの現状に触れました。
池照氏は冒頭、デジタル化を進める際のポイントを指摘。「当社には約2万人の従業員がいる。全員がデジタル化の必要性を理解するにはシンプルさを求めることが大切だ。デジタル戦略が2万にきちんと伝わるかを念頭に施策を検討した」と振り返ります。その上で、「まずはデジタル化しやすい、効果が如実に表れやすい領域からデジタル化に踏み切ることにした。当然、全従業員を巻き込めるかも重視する。デジタル化は顧客はもとより、店舗で働く従業員にとってもメリットを見込めなければならない。いかに従業員の業務を効率化し、利益に結び付けられるか。全従業員がデジタル化の恩恵を受けられる取り組みに主眼を置いた」といいます。全従業員が納得した上でITやデジタルを駆使するのが必要だと指摘しました。
例えば顧客向けに発行するポイントカード。購買履歴などを分析する用途に使っているが、必ずしも顧客を細かくセグメントしないと言います。来店頻度が高いか低いか。デジタルを活用してアプローチできる顧客かどうか。顧客をこの4象限に分類し、象限別の分析結果に基づく施策を検討します。「実際の顧客分析は緻密かつ細かい粒度で実施している。しかしその結果を店舗の全従業員が理解するとは限らない。いかに分かりやすく伝えるかを考えたとき、来店頻度の高い顧客はこんな傾向が、低い顧客はこんな傾向がといった4象限くらいに分類した方が、従業員は納得感を得られるし、施策の目的も理解しやすくなる」(池照氏)といいます。さらに、「顧客の満足度を高める施策はいくつも考えられるが、複数の施策を用意すれば従業員が取るべきアクションも状況に応じて複数になってしまう。これでは現場が混乱し、施策による効果も見込みにくくなる。従業員が取るべきアクションを絞り込むことも大事」(池照氏)と続けます。
池照氏はさらに、「みんなで作り上げる」という姿勢も必要だと指摘します。「デジタルを主導する私や専門部署が戦略を押し通すだけでは一時的な施策にとどまってしまう。大事なのは、こうした取り組みが社内に根付き、文化として育まれることだ。そのためにはデジタル化を推進する部署が主導して手柄になるのではなく、全従業員が意見を出し合える環境、いい施策や取り組みにしようと思う姿勢こそ重要である」(池照氏)と強調します。
そのため、一般的に起こりがちなデジタル化推進時の社内への説得は「不要だった」(池照氏)と言います。「全従業員が事業戦略を理解し、成長したいと同じ目標に向かっている。その上でデジタル戦略を打ち出している。正しいと判断したから進めているため、そもそも正しい思えない戦略ならと取り組まなければいい」と続けます。進めようとしているデジタル戦略を従業員などに説得する以前に、自社の事業戦略や目標、ビジョンを明確化し、全員で共有しておくことが大切だと話します。
もっともカインズの場合、デジタルを推進する専門部署などはそもそもなかったといいます。具体的にどう組織を立ち上げ、推進体制を築いたのか。池照氏は、「当社の本社は埼玉県本庄市。エンジニアを採用しても本庄市勤務になるため、優秀なエンジニアを採用できない恐れがある。そこで東京都渋谷区の表参道にオフィスを新設した。エンジニアのスキルアップや昇給・昇格を支援する仕組みもなかったので準備し、働きやすい環境づくりに努めた」と振り返ります。店舗従業員の働き方に寄せているカインズの人事制度を見直すのは時間を要するため、別会社を作ってエンジニア向けの制度などを準備したといいます。現在はUIやUXに携わるデザイナーが約10人、デジタルマーケティングを担当する人が約50人、エンジニアが百数十人の規模まで成長しています。さらに現在、インドに開発拠点も設立。インドのスタッフ約50人も開発をバックアップできる体制を構築します。「ホームセンターを展開する同社では、やらなければならないテーマがいくつもある。これらに取り組むとき、IT導入やシステム化を外注しては間に合わない。内製化して早期展開できる体制づくりにも注力している」(池照氏)と述べました。
リアル店舗の強みを最大限活かす
第二部は「サツドラホールディングスに学ぶ消費者との向き合い方」と題し、サツドラホールディングス 代表取締役社長 兼 CEOの富山浩樹氏が登壇。デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長 日本オムニチャネル協会 会長の鈴木康弘氏と対談しました。
サツドラホールディングスは、北海道を中心に約200店舗のドラッグストアを運営。さらに商品開発や卸売、地域マーケティング、エネルギーなどの多彩な事業を展開しています。2021年5月期の売上高は832億円、従業員数は2600人を超えます(2021年5月時点)。同社はDXをどう進め、どんな未来を目指しているのか。
鈴木氏は冒頭、DXを成功させるための最初のステップとして経営者の意識を変え決意を促すことが大事だと指摘します。これに対し富山氏は、「チェーンストアはいずれ収れんされる、そんな考えを常々持っている。北海道に限ると、当社のドラッグストア事業は2番手に位置する。これではいずれ、1番手の企業などに事業を買収されるのではという危機感を持っていた。こうした危機感こそ、DXに取り組む要因の1つだった」と、デジタルを武器に変革することが必要だったと振り返ります。
もっとも当時は、デジタル化を推進して効果を上げるには不十分な状況だっといいます。「取り組みの1つとしてPOSシステムを使い、顧客に寄り添ったサービス創出を考えたが、当時のPOSシステムでは実現しにくかった。改修にはコストも数年単位の時間もかかる。そこで自前でPOSシステムを構築できる体制づくりに努めた。危機感とともに、やりたいことができないもどかしさ。これがDXや組織づくりを推進する起爆剤となった」(富山氏)といいます。現在はシステム開発会社との合弁企業に約20人のエンジニアを要する体制を構築しています。
ITと業務の関わりが強くなったことを受け、情報システム部門の役割も変えつつあると富山氏は続けます。「ITの保守や運用業務が中心となる情報システム部門とは別に、業務と業務に関連するシステムをセットで考える業務改革チームを業務部門内に設けた。業務改革に必要なシステムの要件をまとめたり、システムを使うためのマニュアルを作ったりする作業をチームに任せることで、より現場に寄り添ったシステムを構築・運用できるようにした」(富山氏)といいます。現場や業務を理解するスタッフによるイノベーションを創出しやすい体制づくりを目指します。
ではデジタルを駆使し、顧客にどんなサービスを提供しようと考えているのか。富山氏はECサイトが台頭する現状を踏まえつつ、「ECの利便性や価値を否定するわけではないが、リアル店舗を構えるという当社ならではの強みを打ち出すことが重要だと考える。モノを売る施設と割り切らず、多くの人が利用する施設と考えれば、それだけで十分な価値があるのではないか。例えばAmazonの場合、ECサイトに多くの人が集まるからこそ、AWSやマーケットプレイスといった新たなサービスを提供できる。多くの人が集まるリアル店舗も同様だ。その強みを価値として最大限利用することが顧客サービスの創出につながる」(富山氏)と強調。ネット店舗にはないリアル店舗ならではの可能性を追求するビジョンを見据えます。
将来は地域にこだわった店舗づくりも視野に入れます。「モノを売るだけではなく、生活者の暮らしをサポートするコンシェルジュとしての役割を担う店舗づくりを描く。例えば洗剤を1つ売って暮らしを支えるのではなく、洗濯や掃除、引いては暮らし全体を包括的に支えるサービスを提供するのが望ましい」(富山氏)と考えます。生活面のさまざまな情報を提供する「スーパーアプリ」が注目される中、リアル店舗を通じてさまざまな情報や価値を提供する理想を描いています。