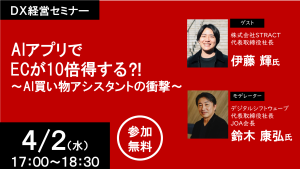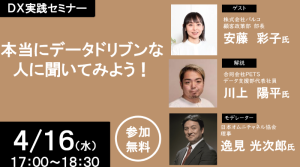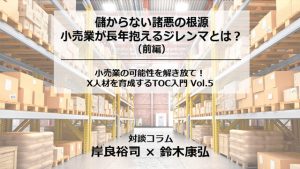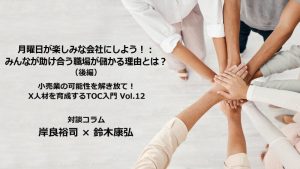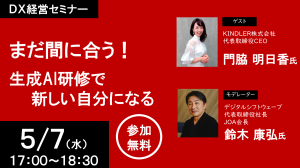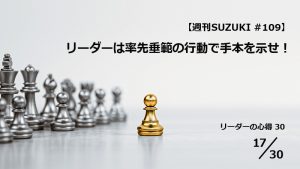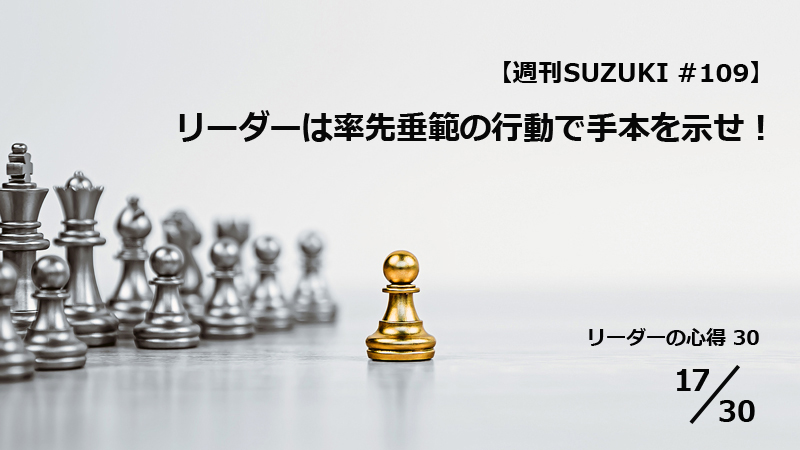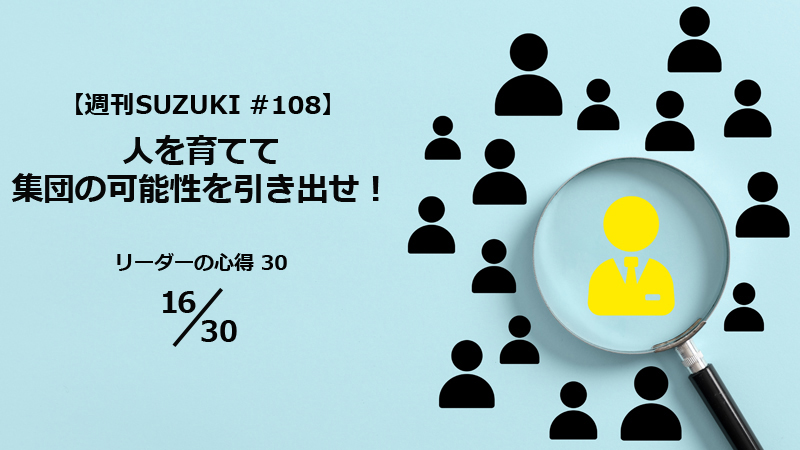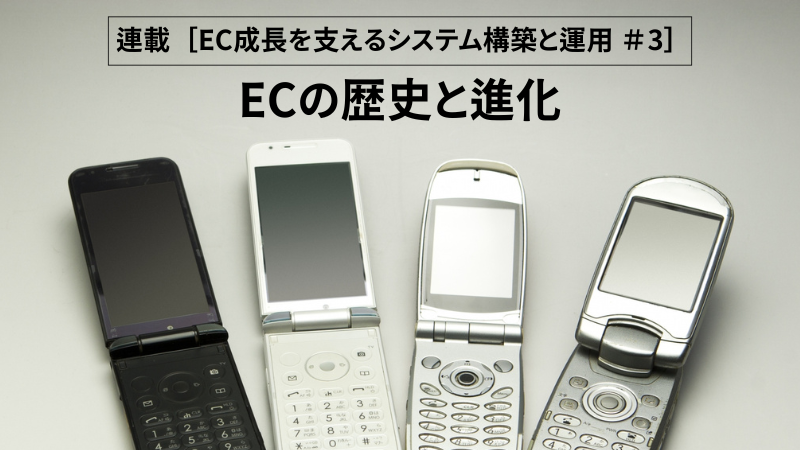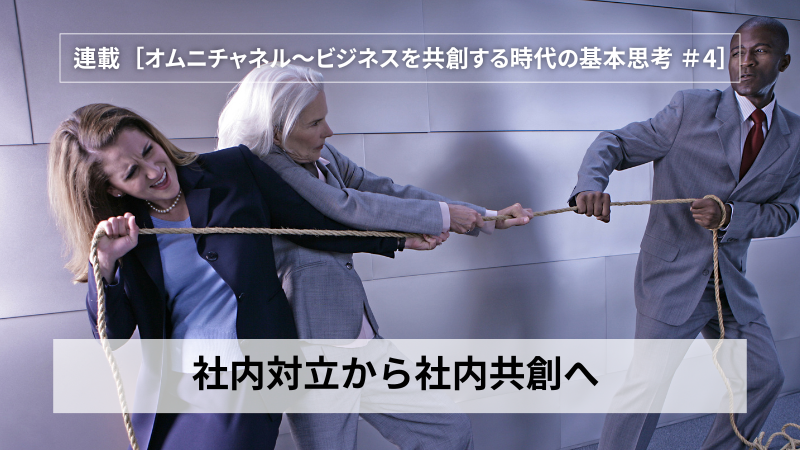DXを進めて変革を目指すなら、社内に変革が定着するまでを考え抜くことが大切です。このとき、変革を嫌う抵抗勢力の対処法まで描いておくのが有効です。では抵抗勢力に対し、具体的にどうアプローチすべきか。ここではそのポイントを紹介します。なお、本連載はプレジデント社「成功=ヒト×DX」の内容をもとに編集しております。
変革は定着しなければ成功とは言えない
DXの推進は最終段階である「変革の定着」こそ、もっとも大事なプロセスです。変革が現場に定着しなければ、どんなに素晴らしい変革も、絵に描いた餅で終わってしまいます。
とはいえ、定着させるのは極めて難しいこと。DXを推進するプロジェクトのスタッフを中心に進めてきた変革を全社員に理解させ、実行させるのは並大抵の取り組みではありません。現場の人の中には、今までの仕事のやり方が変わることに心理的な抵抗を抱く人もいるはずです。
では、変革を受け入れようとしない抵抗勢力とどう向き合うべきか。まずは人がなぜ、変革に抵抗しようとするのか。その心理的なメカニズムから探ってみたいと思います。
変革に抵抗する理由を知る
変革を浸透させようとすると、個人と組織からの抵抗が発生します。個人は、慣れた状況が危うくなる、未知なるものへの不安、自分が聞きたくないことは無視しようとする防衛本能などに起因します。組織は、新しいことを嫌う企業風土、既得権益が損なわれる恐れ、予算や人材縮小への脅威などに起因します。
via プレジデント社「成功=ヒト×DX」
双方に共通するのは、「現状が変わることへの恐れ」「新しいものへの不安」です。抵抗勢力と向き合うには、まずはこうした恐れや不安を抱えていることへの理解が必要です。
変革への抵抗にどう対処すべきか
抵抗にどう対処すべきか。具体的には、正しい情報を伝え、不安を取り除くために参加を促し、新しい環境への適応を支援します。組織なら、大きな勢力を持つ人と交渉し、抵抗を戦略的に弱めるようにします。最終手段として、組織的な強制力を働かせて、抵抗を抑え込むのが有効です。
相手の立場に立ち、段階的な対処を心掛けるのがポイントです。
抵抗から目を背けるな
では変革の定着に向け、具体的にどういったアプローチを図ればよいのか。まずは、社内に変革の意義と内容を粘り強く伝えることから始めます。なぜ変革が必要なのか、具体的に何をすればいいのかを、社員の立場になって伝えます。
次に、現場の人たちにプロジェクトに参加してもらいます。DX推進プロジェクトのスタッフが実際に変革の現場に入り、一緒に変革を進めるのも有効です。多くの社員を巻き込むことで社内の雰囲気が変わり、変革は大きく前進するはずです。
via プレジデント社「成功=ヒト×DX」
このタイミングで抵抗が発生することがあります。特に大きな権力を持つ役員や中間管理職による抵抗は見過ごしてはなりません。こんなときは交渉を進め、合意を取り付けるようにします。多くの場合、変革後をイメージできず、変わることを恐れているに過ぎません。具体的に何を新しく始めるのか、これまでと何が変わらないのか、何を捨てるのかを話し合います。この話し合いの中で、反対する人が答えを出せるよう導くのが望ましいでしょう。話し合いは、もっとも反対している人、もしくはもっとも強面の人から進めるとよいでしょう。社内への影響力が大きいからです。もし合意に至れば、これほど頼もしい見方はいません。
これでも抵抗する人には、最終手段として組織の強制力を働かせます。つまり、トップに登場してもらって対応します。
変革によって全社員が皆幸せになるとは限りません。多くて8割の人が幸せになればよいと考えるべきでしょう。残りの2割は反対することを覚悟します。こうした人に対して例えば、適材適所に配置転換するなどの策に打って出ることも検討すべきです。変革を前進させるためには、情に流されないことも大切です。迅速な対応により、反対する人に与える傷に小さく済みます。復活するチャンスを与えることにもつながります。
筆者プロフィール
鈴木 康弘
株式会社デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長
1987年富士通に入社。SEとしてシステム開発・顧客サポートに従事。96年ソフトバンクに移り、営業、新規事業企画に携わる。 99年ネット書籍販売会社、イー・ショッピング・ブックス(現セブンネットショッピング)を設立し、代表取締役社長就任。 2006年セブン&アイHLDGS.グループ傘下に入る。14年セブン&アイHLDGS.執行役員CIO就任。 グループオムニチャネル戦略のリーダーを務める。15年同社取締役執行役員CIO就任。 16年同社を退社し、17年デジタルシフトウェーブを設立。同社代表取締役社長に就任。 デジタルシフトを目指す企業の支援を実施している。SBIホールディングス社外役員、日本オムニチャネル協会 会長、学校法人電子学園 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授を兼任。
前回までの記事はこちら
#1 他人任せの意識がDXを停滞させる
#2 「デジタル格差」が迷走に拍車をかける
#3 社内の人材育成が、DXを成功に導く
#4 「経営者の決意」が変革の第一歩
#5 DX推進に消極的な経営者を説得せよ、経営者タイプに応じた効果的な説得方法とは?
#6 リスクは回避せずに受け入れろ! 弱腰な経営者のもとでDX成功はあり得ない
#7 DXの成否を決める「推進体制」、構築に必要な3つのポイント
#8 優秀なメンバーを集めるだけでは不十分、DXを進める体制構築で最も大切な6つの極意
#9 DXプロジェクト始動時の注意点、抵抗勢力との衝突を想定した対策を
#10 業務改革の課題解決に役立つ3つの視点、迷走しない進め方とは
#11 業務の流れと課題を丸裸にする業務フロー図の描き方
#12 業務の課題を原因や優先度で分類、3つの方法で課題解決を模索せよ
#13 ITは自社でコントロールし、クラウドを前提とした柔軟なシステム像を描け
#14 システム全容を見える化し、機能・技術・費用・組織の4視点で課題を追求せよ
#15 ITシステム導入を成功へ導くならクラウドファーストとノンカスタマイズが鉄則
#16 DXによる変革は「定着」がカギ、継続的な意識改革で6割の社員を味方につけよ
#1 他人任せの意識がDXを停滞させる
#2 「デジタル格差」が迷走に拍車をかける
#3 社内の人材育成が、DXを成功に導く
#4 「経営者の決意」が変革の第一歩
#5 DX推進に消極的な経営者を説得せよ、経営者タイプに応じた効果的な説得方法とは?
#6 リスクは回避せずに受け入れろ! 弱腰な経営者のもとでDX成功はあり得ない
#7 DXの成否を決める「推進体制」、構築に必要な3つのポイント
#8 優秀なメンバーを集めるだけでは不十分、DXを進める体制構築で最も大切な6つの極意
#9 DXプロジェクト始動時の注意点、抵抗勢力との衝突を想定した対策を
#10 業務改革の課題解決に役立つ3つの視点、迷走しない進め方とは
#11 業務の流れと課題を丸裸にする業務フロー図の描き方
#12 業務の課題を原因や優先度で分類、3つの方法で課題解決を模索せよ
#13 ITは自社でコントロールし、クラウドを前提とした柔軟なシステム像を描け
#14 システム全容を見える化し、機能・技術・費用・組織の4視点で課題を追求せよ
#15 ITシステム導入を成功へ導くならクラウドファーストとノンカスタマイズが鉄則
#16 DXによる変革は「定着」がカギ、継続的な意識改革で6割の社員を味方につけよ