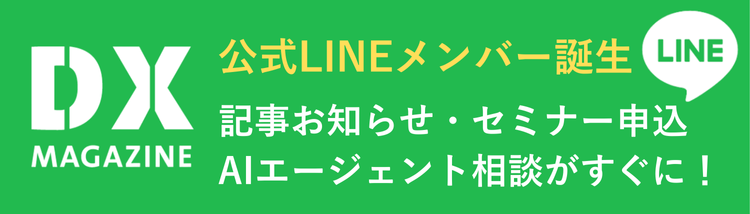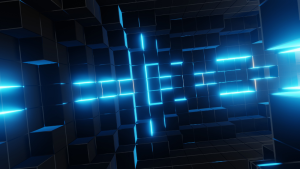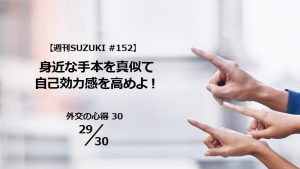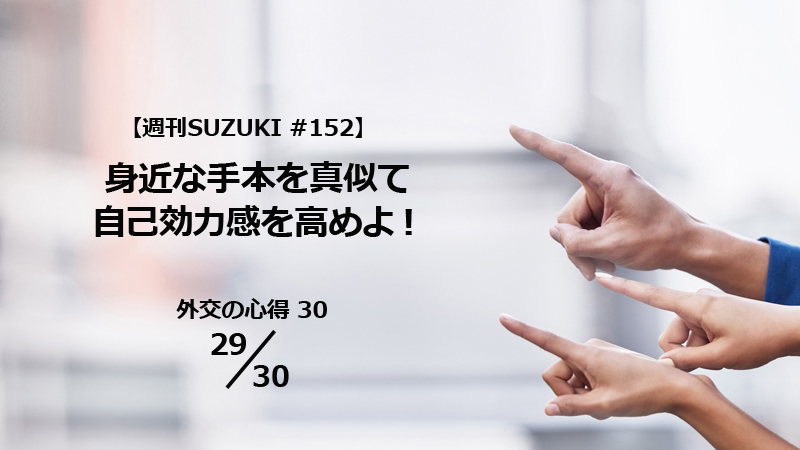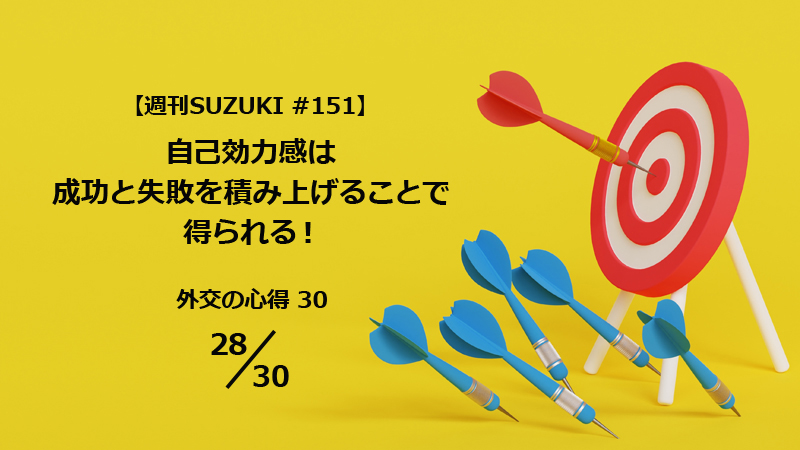DXを推進する企業の多くが、デジタルを活用することによる生産性向上を期待します。人材不足といった喫緊の課題をDXで解消しようと考える企業は少なくありません。では、デジタルで生産性向上を図ろうとしたときに考えられる課題とは。デジタルによる生産性向上が必要な背景と、生産性向上を拒む要因について考えます。なお、本連載はプレジデント社「成功=ヒト×DX」の内容をもとに編集しております。
労働人口は必ず不足する
DXがもたらす変化の1つに「デジタル活用による生産性の向上」があります。ITやデジタルを徹底的に使い倒すことで既存業務を見直し、生産性を引き上げられる。そう考える企業は決して少なくありません。
企業がDXに期待する背景には、少子高齢化による労働人口減少の問題があります。
2030年の労働市場の未来推計を見ると、7073万人の労働需要に対して労働供給は6429万人にとどまります。644万人分の労働力が不足することが予想されます。国や企業は、女性の就労機会を高めるための支援策を充実させたり、シニアの就労機会を創出したりするなどの制度改正に取り組んでいます。
しかし、これらの対策を打ったとしても、不足する644万人の半数程度しか労働力を確保できず、半分弱の298万人の人手不足を解消できないと言われています。この足りない労働力を埋めるため、DXによる生産性の向上が期待されているのです。
DXによる生産性向上への期待
DXによる生産性向上に期待するのはなぜか。これは、従来の生産性向上策とDXによる生産性向上策の違いを知ることで理解できます。
従来の生産性向上は、業務の効率化に集約されます。既存の仕事の進め方やプロセスを変えず、無駄をなくしてコストを下げるという考え方です。作業時間や人の動き、在庫数を適正にコントロールするなどして効率化を実現してきました。
DXによる生産性向上は、デジタルを使って業務を抜本的に見直します。その上でビジネスモデルを改革します。デジタルを活用することで、従来成し得なかった人の仕事を肩代わりすることが可能になります。
では、デジタル化をどう進めるべきか。アプローチは大きく3つあります。
1つはコミュニケーションのデジタル化です。リモートワークに代表されるように、コミュニケーションをデジタル化することで場所や時間をはじめとする壁をなくすアプローチです。
2つ目は定型作業の省力化です。RPAに代表されるように、定型化された単純作業をソフトウエア型のロボットが代行・自動化するアプローチです。
3つ目は複雑な作業の省力化です。AIに代表されるように、人が取り組むには複雑で、複数の答えがある場合に有効です。何億ものパターンをシミュレーションし、最適な解を導き出します。
これらのアプローチを組み合わせてデジタル化を進めることで、仕事のプロセスを劇的に変化させられます。単なる業務効率化とは異なる大きな効果を期待できるのです。
現在では、定型業務や複雑な作業の省力化が、デジタル生産性を高める特効薬のように言われています。そんな中でも筆者は、コミュニケーションのデジタル化こそ、デジタル生産性をもっとも高めると思います。
生産性向上を拒む人の習慣
なぜ、コミュニケーションのデジタル化が生産性向上に大きく寄与するのか。実際に筆者が代表を務める会社でも、コミュニケーションのデジタル化が大きな効果があると実感しています。新型コロナウイルス感染症の影響でリモートワークが進んだ環境下でも、リアルとリモートをうまく使い分け、生産性を2倍以上に高めることができたのです。
例えば、社内会議やクライアントへの報告会議はリモートで実施し、ディスカッションを要する会議はリアルで実施するといった具合です。不都合なこともありましたが、解決しようと新しいやり方を取り入れるなどの努力を重ねてきました。そうした積み重ねを習慣化したことにより、生産性向上を実現できたと思います。
逆に習慣化するまで我慢しないと、生産性を落としてしまうこともあります。
ある企業の経営者は、「リモートワークはダメだ。社員からの不満も多い。来週から全社員を出社させることにした」と言い、せっかく導入したリモートワークを撤回したのです。リモートワークの実施期間はわずか1週間です。
その理由を聞くと、経営者や現場担当者の反応は良かったものの、中間管理職の仕事がなくなったからだと言います。中間管理職からの直訴もあり、リモートワークを断念したそうです。
とはいえ、リモートワーク環境の準備やコストがゼロになるわけではありません。元のオフィスワークに戻した結果、生産性はかえって下がってしまったのです。
人は、自分の慣れ親しんだ習慣を変えることを極度に嫌います。デジタルシフトが進んだときも、一番のブレーキになるのが人の固定概念であり、慣れ親しんだ習慣です。特に成功体験を持つベテラン社員ほど、染みついた習慣を変えられません。DXを極端に恐れる傾向もあります。
DXを進めるときは、こうした社内の抵抗もあると予測すべきです。その上で不退転の覚悟を持って、習慣化するまで継続することが大切です。
魅力的な職場づくりを行う会社が生き残る時代へ
リモートとリアルがうまく組み合わさると、時間や場所に左右されず、その人に会った生活リズムで働けるようになります。すると生産性の向上はもちろん、職場の魅力も増します。働き方の選択肢が増えたことで、今後は出産や子育てなどの時間制約のある人も働きやすくなるでしょう。年齢を重ね、体力に自信のない人も同様です。
当社もハイブリッド・ワーキング体制に移行してから、社員の生活が一変しました。時間や距離の制約から解放され、それぞれに合った仕事の進め方をできるようになりました。出勤やクライアントへの移動時間も減り、生産性は大幅に向上しています。
採用活動においても、距離や時間に縛られることがなく、幅広い人材を採用しやすくなりました。世の中が人材不足になる中、リアルとリモートの融合は大きなアドバンテージになると考えます。
DXによって今後、潜在的な労働力の掘り起こしが進むのは確実です。超高齢化社会を迎える日本は、労働力の減少を割けることはできません。DXで積極的に生産性を向上させ、魅力的な職場づくりに取り組み企業が、新たな労働力を確保し、時代を先導することになるのです。
筆者プロフィール
鈴木 康弘
株式会社デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長
1987年富士通に入社。SEとしてシステム開発・顧客サポートに従事。96年ソフトバンクに移り、営業、新規事業企画に携わる。 99年ネット書籍販売会社、イー・ショッピング・ブックス(現セブンネットショッピング)を設立し、代表取締役社長就任。 2006年セブン&アイHLDGS.グループ傘下に入る。14年セブン&アイHLDGS.執行役員CIO就任。 グループオムニチャネル戦略のリーダーを務める。15年同社取締役執行役員CIO就任。 16年同社を退社し、17年デジタルシフトウェーブを設立。同社代表取締役社長に就任。 デジタルシフトを目指す企業の支援を実施している。SBIホールディングス社外役員、日本オムニチャネル協会 会長、学校法人電子学園 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授を兼任。
前回までの記事はこちら
#1 他人任せの意識がDXを停滞させる
#2 「デジタル格差」が迷走に拍車をかける
#3 社内の人材育成が、DXを成功に導く
#4 「経営者の決意」が変革の第一歩
#5 DX推進に消極的な経営者を説得せよ、経営者タイプに応じた効果的な説得方法とは?
#6 リスクは回避せずに受け入れろ! 弱腰な経営者のもとでDX成功はあり得ない
#7 DXの成否を決める「推進体制」、構築に必要な3つのポイント
#8 優秀なメンバーを集めるだけでは不十分、DXを進める体制構築で最も大切な6つの極意
#9 DXプロジェクト始動時の注意点、抵抗勢力との衝突を想定した対策を
#10 業務改革の課題解決に役立つ3つの視点、迷走しない進め方とは
#11 業務の流れと課題を丸裸にする業務フロー図の描き方
#12 業務の課題を原因や優先度で分類、3つの方法で課題解決を模索せよ
#13 ITは自社でコントロールし、クラウドを前提とした柔軟なシステム像を描け
#14 システム全容を見える化し、機能・技術・費用・組織の4視点で課題を追求せよ
#15 ITシステム導入を成功へ導くならクラウドファーストとノンカスタマイズが鉄則
#16 DXによる変革は「定着」がカギ、継続的な意識改革で6割の社員を味方につけよ
#17 変革を社内に根付かせるなら、抵抗勢力と真正面から向き合え
#18 DXの成功にもっとも必要なのは「人」、社員の自立とマルチスキルを支援してデジタル変革者を育成せよ
#19 DXがもたらす4つの変化、新たな社会常識を踏まえて変化に備えよ
#20 デジタルとアナログの適正なバランスが「ハイブリッド・ワーキング」の可能性を広げる
#1 他人任せの意識がDXを停滞させる
#2 「デジタル格差」が迷走に拍車をかける
#3 社内の人材育成が、DXを成功に導く
#4 「経営者の決意」が変革の第一歩
#5 DX推進に消極的な経営者を説得せよ、経営者タイプに応じた効果的な説得方法とは?
#6 リスクは回避せずに受け入れろ! 弱腰な経営者のもとでDX成功はあり得ない
#7 DXの成否を決める「推進体制」、構築に必要な3つのポイント
#8 優秀なメンバーを集めるだけでは不十分、DXを進める体制構築で最も大切な6つの極意
#9 DXプロジェクト始動時の注意点、抵抗勢力との衝突を想定した対策を
#10 業務改革の課題解決に役立つ3つの視点、迷走しない進め方とは
#11 業務の流れと課題を丸裸にする業務フロー図の描き方
#12 業務の課題を原因や優先度で分類、3つの方法で課題解決を模索せよ
#13 ITは自社でコントロールし、クラウドを前提とした柔軟なシステム像を描け
#14 システム全容を見える化し、機能・技術・費用・組織の4視点で課題を追求せよ
#15 ITシステム導入を成功へ導くならクラウドファーストとノンカスタマイズが鉄則
#16 DXによる変革は「定着」がカギ、継続的な意識改革で6割の社員を味方につけよ
#17 変革を社内に根付かせるなら、抵抗勢力と真正面から向き合え
#18 DXの成功にもっとも必要なのは「人」、社員の自立とマルチスキルを支援してデジタル変革者を育成せよ
#19 DXがもたらす4つの変化、新たな社会常識を踏まえて変化に備えよ
#20 デジタルとアナログの適正なバランスが「ハイブリッド・ワーキング」の可能性を広げる